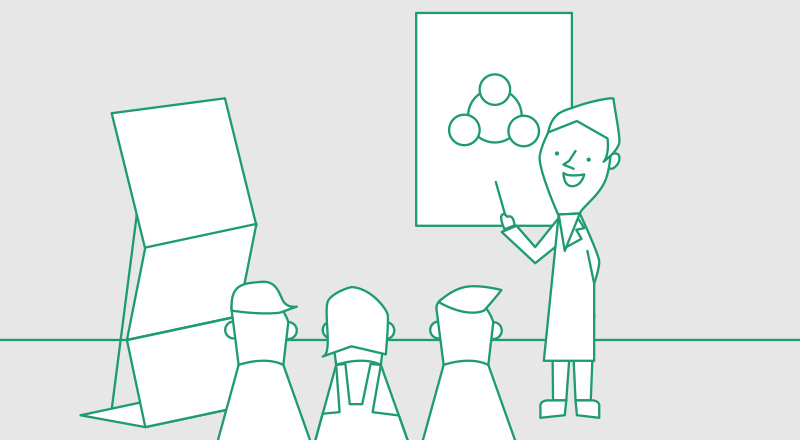Lecture
生き物のしなやかさ
節分のときに生まれたので「節人」の名がある岡田先生。 講談調の味のある話しぶりはつとに評判です。大学者が語る生き物講談、さてどのように進展しますやら、聞いてのお楽しみということで・・・。
生命維持策戦としての再生
地球上にすむさまざまな生き物たちは、その姿・かたちを見ただけでも、なんと多様な魅力に富んでいることでしょうか。奇怪なかたちをもったランの花、華麗な装いを身につけたチョウの 羽、すべて自然が生み出した精緻極まりない造形美の極みといえるでしょう。もう少し深く生き物を知るならば、姿・かたちだけでなく、それぞれが生命を維持するためのなんとも巧妙な策戦を展開していることに気づきます。私たちヒトのもっている脳の働き、あるいは私たちのからだが外界から進入してくる病原体と戦うための免疫のしくみなど、まさにそういった例です。
さらには、この地球上にすんでいるさまざまな生物のほとんどが共有している、生命維持の必須の仕掛けとして、受けた傷害を自ら治癒するというものがあります。この仕掛けは、かなりの生物でもっともっと大がかりなものとなります。傷を治癒するだけでなく、失われてしまったからだの一部をもう一度(ときには二度、三度と)元と同じ姿に複製するのです。極端な場合では、体のごく一部さえ残っていれば、それから全体を復元できるものも少なからずあります。まことに生物はさまざまです。こうした失った部分を元に復元できる性質を再生といいます。
再生は、まさに生き物の生命維持のために展開される、もっとも大規模な策戦でありましょう。そこで私たちが見るのは、生き物とはいかに”しなやか”であり”したたか”であるかということです。
生き物の”しなやかさ”に魅せられた人たち
さて、再生という事実を科学のテーマとして取り上げてみるとき、二つの特別 な局面に気づきます。その第一は、原則として生きている生物に実験という手だてをもって手を加えない限り、再生という能力の存在を認識することができない、ということです。従って、再生の研究は観察ではなく、実験が導入された最初の生物学の分野でした。それというのも再生というのは、目で生き物を観察しただけでわかる変化-例えばアオムシのチョウへの変化-ではなく、生き物のもっている潜在的な能力であるからです。第二は、再生はあまりにも常識を越えた大規模な変化なので、かえって科学の対象となり難い面があることです。実際、ここ半世紀の生物学は、この問題を少なからず敬遠してきた傾向が大なのです。
第一の点に戻れば、あえて実験をしてみなくても、自然の生き物の観察だけでわかる再生の例がないわけではありません。有名なのは”トカゲの尻尾切り”です。このことは、1686年の夏に、パリの科学アカデミーにおいてデモンストレートされたそうです。もう一つの例は、エビやカニの仲間についてのもので、18世紀のフランスの海岸にすんでいた人たちは、こうした動物がときとして小さなハサミを持っているのを知っていて、これは再生されたものだと考えついたと言い伝えられています。
これを耳にしたフランスの古典的な万能科学者レオミュール(Fershault René-Antonie Réaumur,1683-1757、寒暖計の発明者)は、実際に実験によってザリガニの脚やハサミを取り除いても再生することを、1712年に発表しています(右図)。やがてトランブレー(Abraham Trembley,1700-1784)は、ヒドラを用いた詳細な再生実験の結果を発表し(1744)、再生の事実を不動のものとすると同時に、彼は実験生物学の祖として位置付けられるようになりました (下図)。
.png)
ザリガニの脚やハサミを取り除いても再生する(江口吾朗画)
もう一つ愉快な話をつけ加えておきましょう。カタツムリの頭を切り除いても、新しくつくられる、という伝承がフランスに伝わり、数多くの同国の自然愛好者やインテリのアマチュアたちが、1768年に何千匹というカタツムリの頭を切りまくったそうです。その中の一人にかの著名な文学者・思想家のヴォルテール(F.M.A Voltaire,1694-1778)がいました。彼は「人間の手になる実験の結果として、個体の精神と霊のやどる構造(頭)がつくられるのを見るなんて、これはまことに深刻な問題だ」と驚嘆した由です。
私が、こうした昔話をあえて長く語っているのは、ここにはそれなりの現代的な意義があると考えているからなのです。一つは、再生研究は実験生物学の中の起源であり、1992年になって”遺伝学は発生学の子供”という指摘がなされたのも、こうした古典の意義がようやく理解され始めたからです。さらに重要なことは、18世紀において、ヴォルテールまでも巻き込んで、再生という現象が世人の強い関心の的であったことです。

実験生物学の開祖トランブレー。左手の池で採集したヒドラで再生実験を行い、教え子たちに供覧した(Trembley,1744より)
細胞のもつ”しなやかさ”
ここで話を少し個別な例へと進めます。右図を見てください。ここにはなにやら奇妙な、どちらかというと不恰好な動物たちが並んでいます。これらはどういう連中であるかというと、眼からレンズが失われたり、あるいは網膜の細胞の相当部分が失われても、ちゃんと再生できる-従って視力は完全に修復できるという、実に有り難い策戦を遂行できる動物たちなのです。
失われたレンズは、どこから再生してくるのかですって?これがなんとも素晴らしいことに、残っているレンズとは別 の、例えば網膜の黒い色素細胞など(ときには角膜)が変化してレンズになってしまうのです。つまり、細胞そのものが危急存亡の時に応じて、別 のタイプの細胞へと転身できるしなやかさをもっているのです。従って、私の言う生き物のしなやかさは、細胞の性質にまで及ぶのです。ヒトのレンズは取り除くと再生できません。しかし、ヒトの眼の細胞が細胞としてしなやかさをもっていることは、江口吾朗教授(国立基礎生物学研究所)らが、ヒトの眼の網膜を試験管の中に培養して、レンズに転身できることに成功したことからも明らかです。

レンズの再生能力をもった動物たち
(江口吾朗画)
実際、細胞のもつしなやかさは、DNAを調べても充分にうなずけるのです。私たちのからだは、ごく大ざっぱにいうと約200の異なったタイプの細胞から成り立っています。しかし、タイプは違っても遺伝子DNAの組成については、本質的に違いはありません。つまり、一個の細胞である受精卵から出発して、200もの細胞タイプの違いが生ずるのに、遺伝子DNA組成における変化は原因になっていないのです。だから赤血球の細胞にも、レンズの細胞でだけさかんにつくられるクリスタリンというたんぱく質をコードする遺伝子が、ちゃんとあります。逆にレンズの細胞は、赤血球の看板であるヘモグロビンというたんぱく質の遺伝子をもち続けています。言うまでもないことですが、赤血球におけるクリスタリン遺伝子は、ふつうは細胞の一生において、一度として使われることはないでしょう。実に無駄 なことなのです。しかし、こうした無駄があればこそ、細胞のしなやかさは保証されることになります。
いや、話を逆に考える方が面白そうです。数多くの細胞タイプのつくり出されるプロセス-これを細胞分化というのですが-は使われない遺伝子をそのまま貯えこんだ、実に無駄 の多い道程です。生き物が細胞分化のためにこうしたやり口を選んでしまったのは、このことがすべての生き物は修復のためのしなやかさを、生命維持の策戦として駆使しなければならないことの準備にもなっているわけです。もし、クリスタリンの遺伝子が不要だという理由で、網膜の黒色細胞から失われてしまっていたら、イモリは泣けど騒げどレンズを再生できるわけはありますまい。
私がここで語ったお話は、いわば、実験によって初めて知ることのできる、生き物たちの素晴らしいパフォーマンスの物語であります。ここらで18世紀の人たちの素朴なまなこに帰って、さまざまな生き物たちの”しなやかさ”を見直す意義が大きかろうと、私は思うのです。
実際、18世紀においてはヴォルテールまでも巻き込んで、実験で知られる生物のパフォーマンスは万人の関心を集めたのです。また、実験生物学の祖、トランブレーは自らのヒドラの観察を、子供たちに供覧しつつ、研究を続けていたのです。生物学研究と一般社会の対話をもくろんだ生命誌研究館のあり方の、素朴な原点をここに見る想いがします。このことはまた、生き物の”しなやかさ”の問題は、私たちの研究テーマとして実にふさわしいことを語っています。
最後に、長く再生研究を行ったアメリカのゴス(R.J.Goss)の言葉を引用しておきます。
”再生がなければ、生はあり得ない。何でもかんでも再生するならば、死はない”(1969)。
(おかだ・ときんど/生命誌研究館館長予定)
※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。

イモリの眼からレンズを取ると、黒い色素細胞からレンズが再生してくる(中央の黄色い部分、左側の層は角膜)
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)