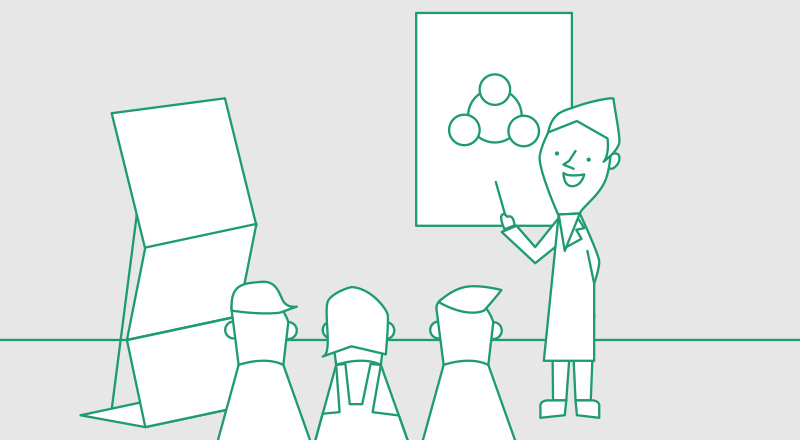Special Story
ゲーリング博士が語る 目の進化の物語
トンボの複眼、タコの目からプラナリアの目まで、動物界に見られる目の形はじつにさまざまだ。 いったい多様な目はどうやって登場してきたのだろうか。 遺伝子の研究が明らかにする目の進化の物語。
1. 目の多様性と進化
昆虫の頭部を電子顕微鏡で拡大したところを見てみよう。髭のような突起がたくさん生えている怪獣のような頭に、巨大な目が見えるはずだ。しかもその目は、私たち人間の目とは似ても似つかない。たくさんの小さな目(個眼)が集まってできた複眼と呼ばれるものである。
昆虫の複眼に限らず、動物界に見られる目という器官は、いずれも光の刺激を受け取って、ものを見るというはたらきをもっているが、その詳細な構造は、動物ごとにずいぶん違う。
いったいさまざまな動物の目は、どのようにして進化してきたのか。スイス・バーゼル大学のゲーリング博士は、その問題に今、遺伝子レベルで迫ろうとしている。
「目がどのように進化してきたかということは、進化の理論にとってとても厄介な問題でした。ダーウィンは、『種の起源』の中で1章を割き、進化の理論で説明するのが難しい現象を自ら取り上げて議論しています。その一番初めに取り上げられているのが、目の進化の問題なのです。現存の動物がもつ完璧な構造の目を見ると、それが突然変異と自然淘汰の組み合わせでできたとは考えにくい。そこで議論をいろいろ重ねて説明をしようとしています。しかし、結局は初めに生まれた原始的な構造の目が、しだいに変化してきたのだろうという程度の説明しかできていません。しかも、その原始的な目が、いつどのようにして登場したかについては、何も語っていないのです。

目を作るPax-6遺伝子のはたらき
①ショウジョウバエで、将来目になる部分でPax-6遺伝子がはたらいている様子(青く染まった部分)。
②目ができないアイレス突然変異では、Pax-6遺伝子の発現がみられない。
③④Pax-6遺伝子は、マウスでも目をつくるのにはたらいている。上は普通のマウスで、下はPax-6遺伝子がはたらかなくなったスモールアイ突然変異体。
(写真=Walter Gehring)
現在私たちが知っているさまざまな動物を見てみましょう。たとえば、私たち人間などの脊椎動物の目と、昆虫の複眼、それからタコなどの軟体動物の目は、でき方も構造もずいぶん違います。そこで、ダーウィン以後の進化学者たちは、さまざまな系統の動物に見られる目は、別々に生まれて進化してきたのだとずっと考えてきました。いわゆる収斂(しゅうれん)進化というものです。
進化生物学の大御所マイヤーも、少なくとも40、もしかすると60くらいの系統で、別々に目という器官が登場したと言っています。具体的にいくつの系統があるかは意見が分かれるところですが、とにかく生物学の教科書にいはみな同様のことが書かれています。じつは私自身も数年前に作った教科書の中でそう書きました。ところが私たちが今行っている研究から、それが完全な間違いだったということが明らかになってきているのです。」
動物たちの多様な目
昆虫の複眼からタコやイカの目、貝の目にいたるまで動物界に見られる目はじつにさまざまである。

⑧ヒオウギガイの目。二枚貝のなかには外套膜の縁にたくさんの目をもつものがあり、この貝やホタテガイの目にはレンズまである。
⑨⑩ボウズコウイカの目。まぶたを開閉することができる。イカやタコの目は、脊椎動物に匹敵するほどよく発達しているが、細かい構造や個体発生におけるでき方は大きく違う。(写真=⑧~⑩楚山勇)
2. 偶然に見つかった目をつくる遺伝子
目の進化の問題は、ダーウィンだけでなく多くの生物学者を悩ませてきた。つまりこれは、『種の起源』以降1世紀にわたり無数の生物学者たちが取り組んできた問題なのだ。それほどの大問題について、教科書に載っている考え方を否定するような結論を出す研究とは、いったいどのようなものなのか。
「私は、30年前、ショウジョウバエの研究で有名なチューリッヒ大学のハドーン教授の研究室の大学院生だった時から、ずっと動物の体づくりの遺伝子の研究をしてきました。とにかく力を入れて研究したのは、ホメオティック遺伝子という体全体の構造を決める一群の遺伝子です。その一連の研究の中から10年ほど前に生まれた、昆虫と脊椎動物に共通するホメオボックス遺伝子群の発見は、とてもエキサイティングなものでした(下記『ホメオボックスの発見』加藤和人 参照)。その後は、それらを含めた体づくりの遺伝子が、どのような順序ではたらいて体の構造ができるかの詳細を調べようと研究を続けてきました。

ゲーリング博士
「体づくりはいくつもの遺伝子が段階的(カスケード状)にはたらくことで進む。今私たちは、Pax-6遺伝子の指令からはいくつのステップを進めば、レンズをつくるクリスタリンや視物質のロドプシンなどの遺伝子に行き着くのかを調べている。いずれは目をつくる遺伝子のカスケードの全貌を明らかにしたい」。生命誌研究館にて。(写真=外賀嘉起)
目の形をつくる遺伝子パックス6(Pax-6)は、そういった体づくりの遺伝子の研究の中からまったくの偶然で見つかってきたものです。大学院生の一人が、ショウジョウバエの初期胚ではたらく、ある遺伝子に注目して、その遺伝子のはたらきをオンにしたり、オフにしたりする遺伝子を探そうと実験をしていました。ところが探していた遺伝子は全然見つからずに、予想もしなかったまったく別の新しい遺伝子が見つかってきたのです。それがPax-6遺伝子でした。Paxというのは、すでにマウスで体づくりに関係があることがわかっている遺伝子につけられた名前です。数字の6は、それまでに見つかったたくさんの仲間のうち、6番のものと似ているからです。
私たちは、さっそく新しい見つかったショウジョウバエのPax-6が、いったい何をしているかを調べにかかりました。ショウジョウバエでは、20世紀初めの偉大な遺伝学者モーガン以来多くの研究者が見つけた、形態に異常を起こす突然変異体がたくさんあります。その中の一つ、『アイレス』という目のできない突然変異が、Pax-6遺伝子の異常による突然変異だということがわかりました。一方、脊椎動物のマウスや人間にあるPax-6遺伝子も、目の形づくりに関係しているということがわかっていました。マウスの突然変異体はとくに『スモールアイ』と呼ばれ、目が小さくなる異常が起こります。Pax-6遺伝子は、哺乳類でもショウジョウバエでも目をつくるのに重要なはたらきをする遺伝子だということが明らかになったのです」
ホメオボックスの発見 加藤和人
ショウジョウバエでは、個体発生の初期に、頭、胸、腹などの体の構造をつくるのに「ホメオティック遺伝子」という一群の制御遺伝子がはたらいている。各遺伝子は、体のどの部分をつくるかの役割分担が決まっており、あるものは頭の部分をつくり、また別のものは胸や腹をつくるのにはたらく。
80年代の初め、ゲーリング博士らは、ホメオティック遺伝子をDNAのレベルで解析し、それらの遺伝子に共通の短い配列があることを見つけた。「ホメオボックス」と名づけられたその配列をもつ一群の遺伝子(ホメオボックス遺伝子群と呼ぶ)は、その直後、カエルやマウスなどの脊椎動物にも見つかり、しかもそれらの遺伝子が、ショウジョウバエと同じように、頭から尾の各部分をつくるのにはたらいていることを予想させる実験の結果も出るようになった。
当時、昆虫と脊椎動物のような離れた系統で共通の体づくりの仕組みがあるとは誰も予想しなかったので、系統を超えた共通の機構の存在を示唆する発見に、世界中が大騒ぎをすることになった。
ホメオボックス遺伝子群は、今ではプラナリアからウニ、線虫にいたるまで非常に多くの動物に見つかっている。初期の頃、体の節構造をつくるのにはたらくと思われたが、現在では節の有無にかかわらず、多くの動物で、頭から尾に至る体の各部の違いを決めるはたらきをすると考えられている。(本誌・加藤和人)

ホメオボックスたんぱく質の一つ、アンテナペディアたんぱく質(左半分の青と紫の部分)が、DNAの2重らせん(右の黄)の溝の中に一部入り込んで結合しているところ。Pax-6遺伝子がつくるたんぱく質も、同じようにDNAに結合する。
(写真=Walter Gehring)
3. 動物の目の祖先は1つ?
ゲーリング博士たちは、さらにPax-6が本当に目をつくるのに重要なはたらきをしている遺伝子かどうかを調べるために、実験的にPax-6遺伝子をハエの体のいろいろな場所ではたらかせてみた。するとなんとPax-6遺伝子がはたらくだけで、体中のさまざまな場所に目ができたのである。1個の遺伝子がはたらいただけで、脚の先にも、触角の先にも目ができる(写真右)というのはじつに驚きだった。本来とはまったく別の場所に目をもったハエの写真は、専門外の人々にはかなりセンセーショナルなものとして受け入れられ、必ずしもすべてのメディアが実験の目的を正しく伝えたとは言えなかった。しかし、体づくりのメカニズムの研究という立場からすると、Pax-6遺伝子がはたらくだけで目ができるというのは、真に重要な発見だったのである。

さらに、博士たちが、マウスのスモール・アイという遺伝子をハエの体ではたらかせたところ、やはり脚や触角に過剰な複眼が形成された。
これは、いったい何を意味するのか?
「Pax-6遺伝子がはたらくだけで、体のいろいろな場所に目ができたということは、Pax-6遺伝子が、目をつくるための最初の指令を出す遺伝子だということを意味します。そのような遺伝子のことを専門用語で『マスター制御遺伝子』と呼ぶのですが、それは『支配権を握る遺伝子』というような意味です。つまり、Pax-6遺伝子がはたらくことで目をつくるために必要なたくさんの遺伝子が次々とはたらきだす。Pax-6遺伝子は、そのための一番初めの指令を出す遺伝子だということなのです。
さらに、マウスのpax-6遺伝子がショウジョウバエの体の中でも、ショウジョウバエの遺伝子と同じようにはたらいて目をつくったということは、目をつくるメカニズムのうち、少なくともPax-6という初めの指令は、両者に共通しているということを示しています。私たちは、すでに軟体動物のイカ、扁形動物のプラナリアでPax-6遺伝子を見つけており、イカの遺伝子は、やはりショウジョウバエに複眼をつくらせることを確認しました。
結局、さまざま動物の目は、一見異なった構造をしているように見えても、驚くほど共通のメカニズムをもっているということです」
4. 原始の目はプラナリアに似ていた?
はじめにも紹介したように、ハエ、マウス、タコ、プラナリアといった異なる仲間に属する動物の目は、進化の過程ですべて別々に登場してきたのだと考えられてきた。ところがゲーリング博士らの発見は、目をつくるためのPax-6遺伝子がいずれの動物にも共通だということを教えてくれた。そこから、動物の目の進化についての新しい見方が生まれつつある。
「今、プラナリアの目にとても興味をもっています。プラナリアの目にはレンズがなく、光を感じるための視細胞と光を反射するための色素細胞もごく少数しかありません。種によっては、視細胞と色素細胞をそれぞれ1個ずつしかもたないものもいます。
太古の動物がもっていた目が、今のプラナリアの目とどれくらい同じだったのかはわかりません。しかし、おそらくプラナリアの目と同じような単純な構造をもった目が動物の進化の初期に登場し、それが動物そのものの多様化とともにいろいろな形へと進化していったのではないでしょうか。そう考えると、今の動物に見られる多様な目も、あえてたくさんの起源を考えずに、1つの祖先形からの変化として説明がつくと思います。」
こうして、動物の目はただ一度だけ登場したというゲーリング博士の説が生まれたのである。
「私は、よく細胞の話を引き合いに出して説明します。今の生物のもつ細胞を見てみましょう。細胞の形は、ニューロン、皮膚の細胞、色素細胞、筋肉の細胞とじつに多様です。しかし、誰もそれを見て、別々のものから独立に登場したとは考えないでしょう。一見まったく違う形をしている細胞も、同じ祖先から変化してきたはずです。目の進化についてもまったく同じことがいえるのです」

5. 形づくりのスイッチ遺伝子を求めて
こうして、思いがけないことから始まった目の進化の研究だったが、ゲーリング博士のグループによる研究のすべてが偶然によると考えるのは、正しくない。
目の形づくりに関する博士たちの研究がいかにして生まれてきたかを理解するには、博士のこれまでの研究の歴史を見る必要がある。そうすれば、博士がいかに、偶然の発見を、逃がさずに自分のものにしたかを理解することができる。
「30年前に大学院生としてショウジョウバエの研究を始めた頃、アンテナペディアという突然変異体を見つけました。そのハエでは、触角(ラテン語でアンテナ)の変わりに脚(ラテン語でペディア)が生えてくるのです。その前にハドーン教授のもとで、一度運命を決定された胚の器官が運命を変えるという『決定転換』の研究をしていたこともあって、この突然変異体を見つけたときから、脚や翅、触角などの動物の器官をつくるときに、スイッチを入れるようにはたらく制御遺伝子があるに違いないと信じていました。もちろん30年前は、誰もそんなことを信じてくれませんでしたが、私はどうしてもその方向で研究を進めたくて、大学院を終えたあとに、大腸菌で遺伝子のはたらきを研究していたエール大学のギャラン博士のところに留学しました。そんな経験がやがて80年代のホメオボックス遺伝子の発見や今回のPax-6遺伝子の発見につながったのです」
「生物学の知識を正しく理解するためには、多くのこと、それもじつに広い範囲のことを知る必要があります。私は、子供の頃のチョウの飼育にはじまり、高校時代のバードウォッチング、大学時代の動物の行動や生態に関する勉強とじつにいろいろなことを学んできました。大学院でも、修士課程では、周りのみんながショウジョウバエの研究をしているのに私一人でチューリッヒ周辺の鳥の移動に関する研究をやったくらいです。
もちろん誰もが私のような経験ができるわけではないでしょう。とくに最近では、分子生物学を学ぶ学生は動物の行動のことなどを学ぶ機会が全然ありません。しかし、もしもその人が優秀ならば、必ずあとから取り返せるはずです。ショウジョウバエの神経の研究で有名なベンザーを見てみなさい。彼が神経の研究を始めたのは、かなり年をとってからのことです」
生き物の体づくりに取り組む発生生物学は、今や分子レベルの共通性という大きな武器を手にして、生き物の多様性と、多様性を生み出してきた進化の歴史について、じつに雄弁に語りだしている。今こそゲーリング博士のように広い視野をもった研究者の活躍により、普遍と多様、ミクロとマクロをつなぐ、まさに生命誌が求めている研究が繰り広げられる時代が、到来しているのである。
(文・構成:本誌・加藤和人)
※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)