検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)

Music
自然の中のかくれた秩序
野村仁
1945年兵庫県生まれ。京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)専攻科修了。同大学美術学部美術科彫刻専攻助教授。時の経過に目を向けた独特の作風の写真や彫刻、インスタレーションなどで知られる。国内外を問わず、多くの個展やグループ展を実施。94年8月に作品集『Time-Space』を発行。
キーワード

Science Topics
レンズはどのようにして作られるか
高橋直
レンズはどのようにして作られるか:高橋直

Art
意識を描く ー生命と想像力
潘微
意識を描く ー生命と想像力:潘微


TALK
生命の色いろいろ
志村ふくみ × 中村桂子
滋賀県生まれ。民芸協団の創設者・柳宗悦に勧められて織物を始めた。植物染料における日本の色の研究と並行してゲーテやシュタイナーの色彩論も研究。重要無形文化財保持者。著書に『語りかける花』『一色一生』『織と文一志村ふくみ』など


SCIENTIST LIBRARY
ホヤから私へ — 脳と心の進化を追う
藤田晢也
1931年大阪生まれ。55年京都府立医科大学卒業。同大学病理学教室助手を経て、講師となる。パーデュー大学にアシスタント・プロフェッサーとして迎えられ、帰国後、京都府立医科大学病理学教室教授に就任。87年より、学長を2期務める。95年3月退官。現在、京都パストゥール研究所所長。専門の病理学におけるテーマは癌の発生。写真の背景は、療病院医学校(京都府立医科大学の前身)のあった青蓮院の大楠。博士は、研究人生のほとんどをこの大学で過ごした。
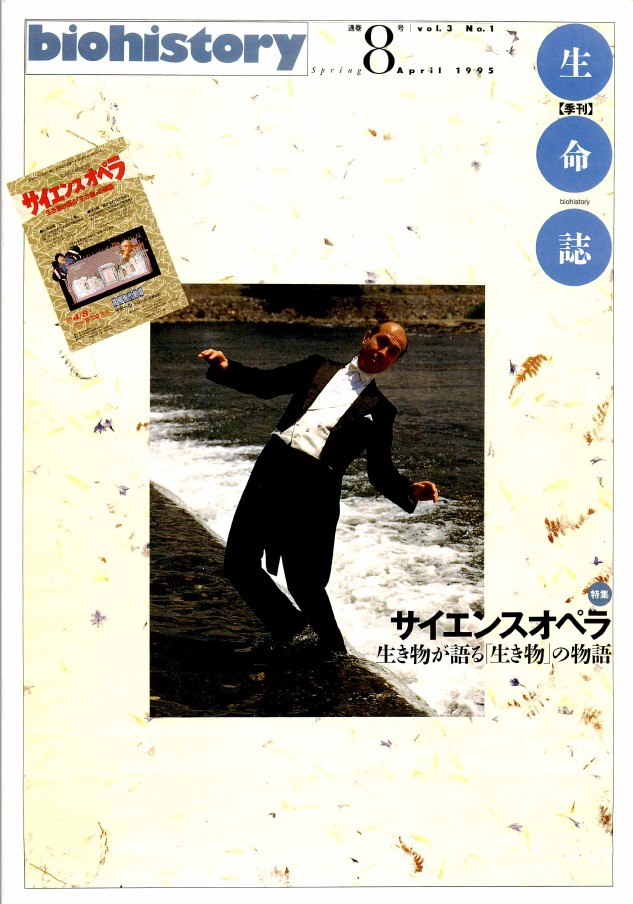
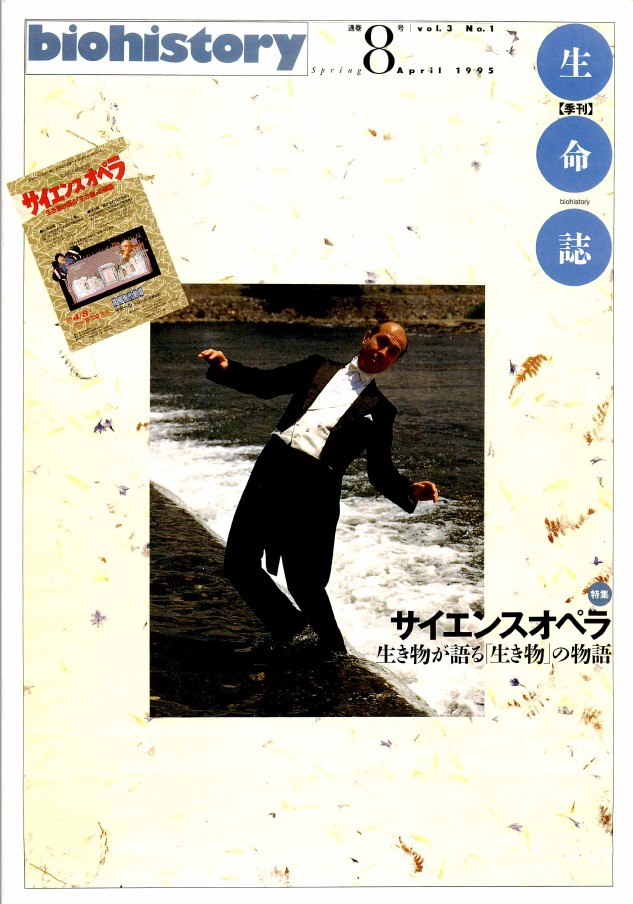
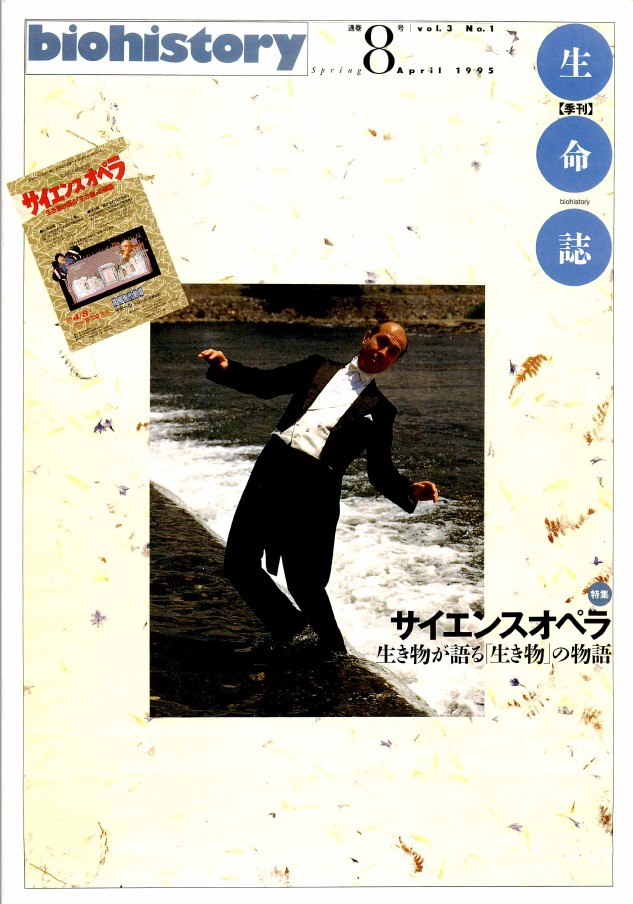
Science Opera
生き物のダンス
ハイディ S. ダーニング
Heidi S. Durninng
東京都生まれ。ダンス・アーティスト。日本人を母に、スイス人を父にもつ。日本舞踊の名取りでもあり、一方でコンテンポラリー・ダンスのレッスンも開く。公演では、幕間に、踊りながら次のシーンのしつらえをする黒衣(くろご)役で登場する(写真=外賀嘉起)
キーワード
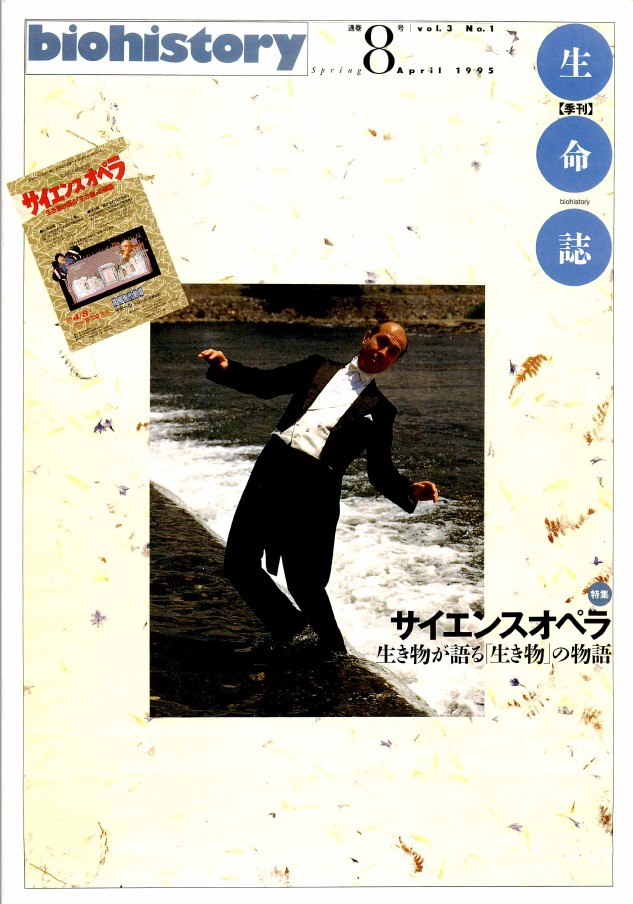
Science Opera
無次元・無時間の舞台
マダ ジュンコ
熊本県生まれ。オブジェ作家。古代生物や爬虫類などをモチーフに、鏡やガラスをモザイク状にちりばめた、表情豊かで不思議な生き物オブジェで知られる。今回の公演では、舞台美術のデザインを担当。近作のシーラカンスを前にして
キーワード
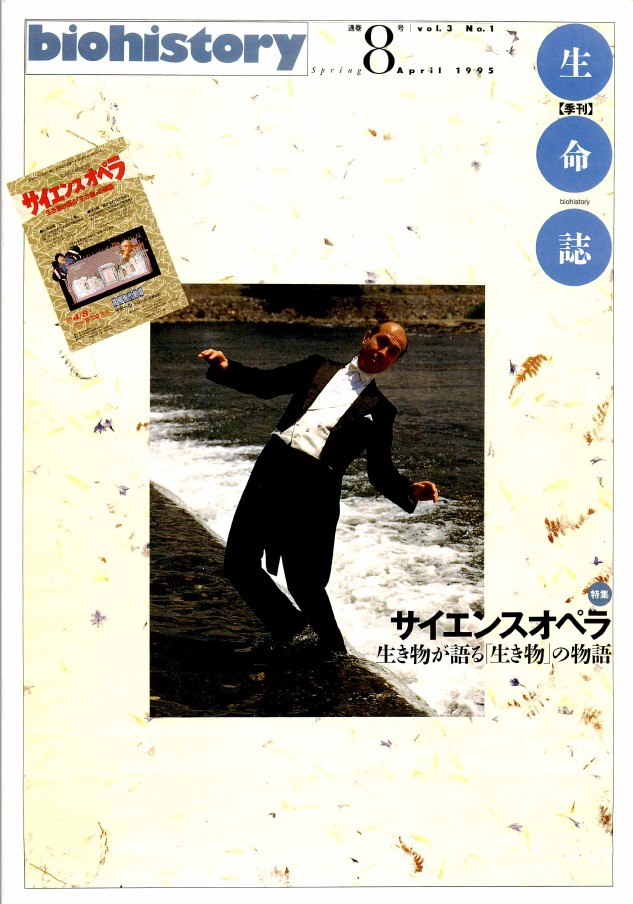
Science Opera
音楽の嫌いな者よってこい
井上道義
京都市交響楽団音楽監督・常任指揮者。1946年生まれ。桐朋学園大学で斎藤秀雄氏に師事。71年イタリア「ミラノ・スカラ座」主催のグィド・カンテルリ指揮者コンクールに優勝し、世界的な活躍を始める
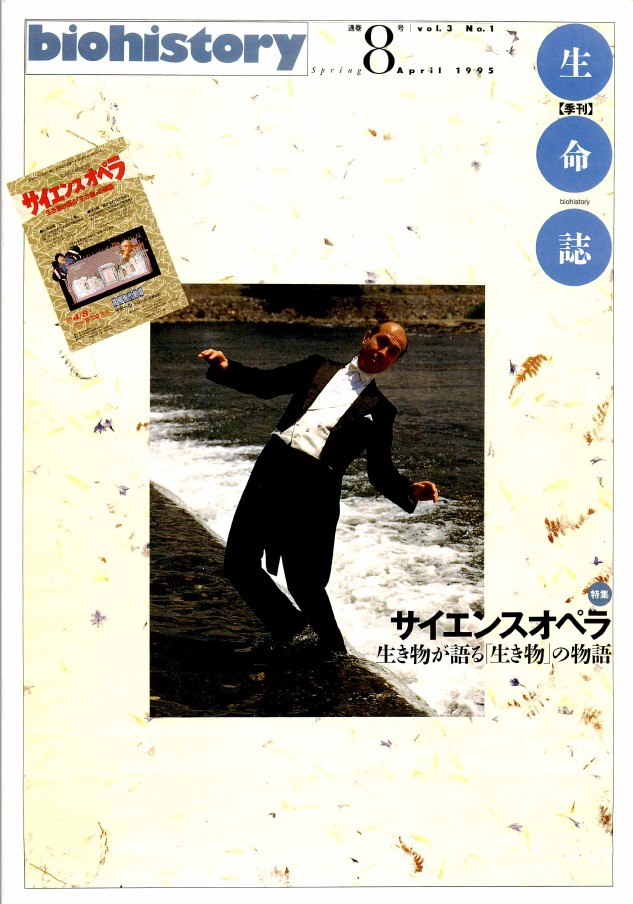
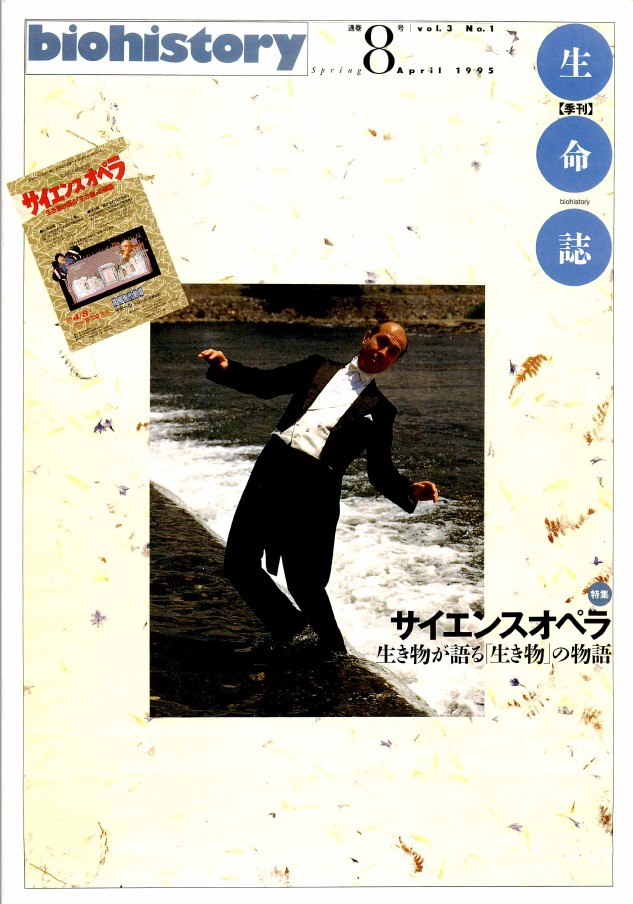
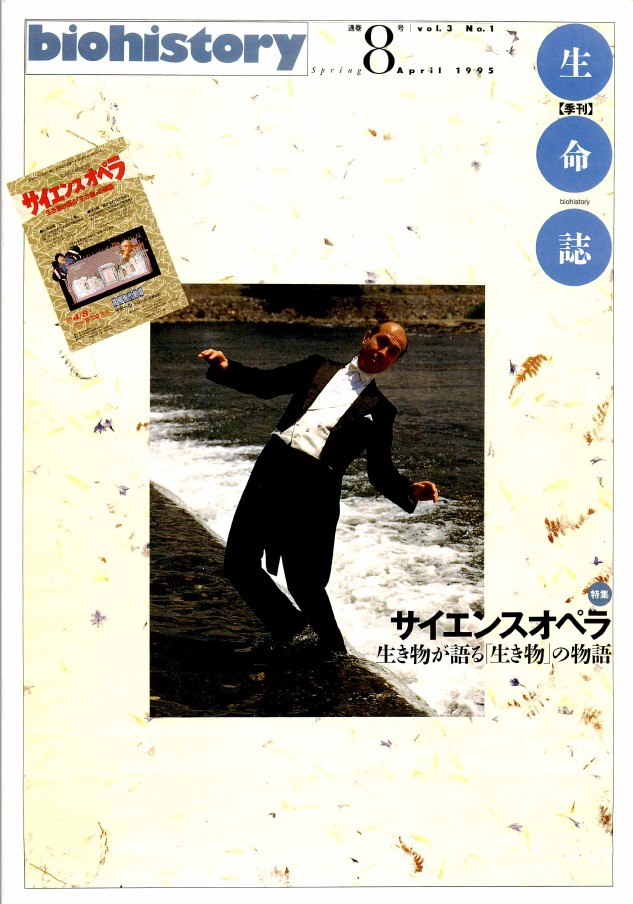
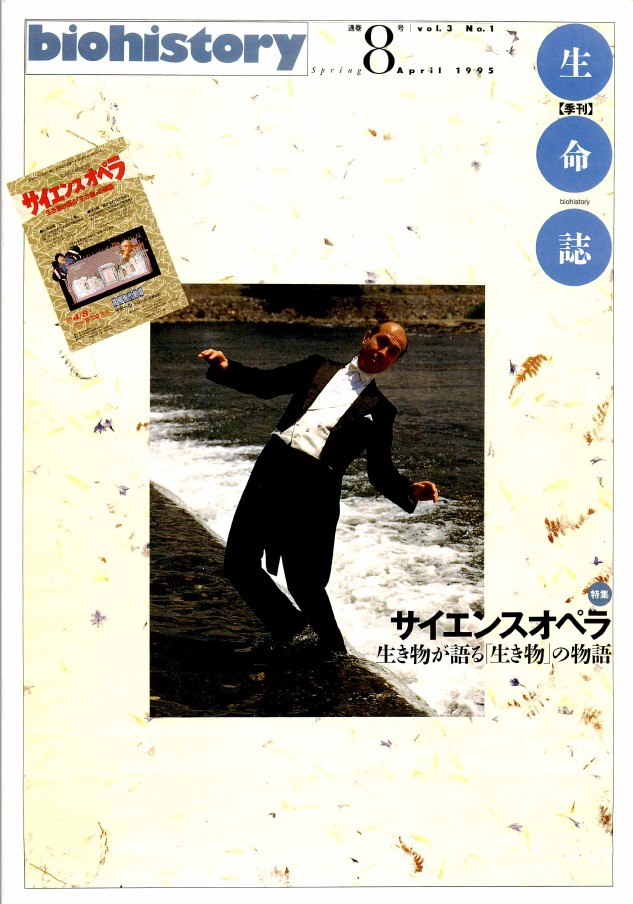
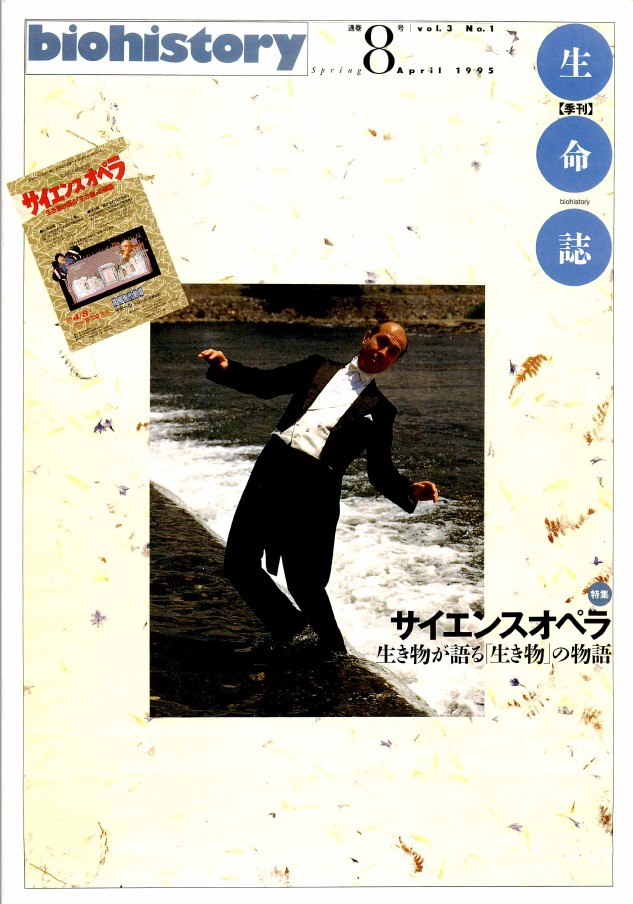
Music
無門斎コンサート
都一中
1952年生まれ。一中節は、今から約300年ほど前に京都で生まれた浄瑠璃の一流派。流祖の都太夫一中は、京都・御池堺町、明福寺の次男で、音楽の道に特別な才能を示し、さまざまな流派の浄瑠璃節を統一して一中節を起こしたといわれる
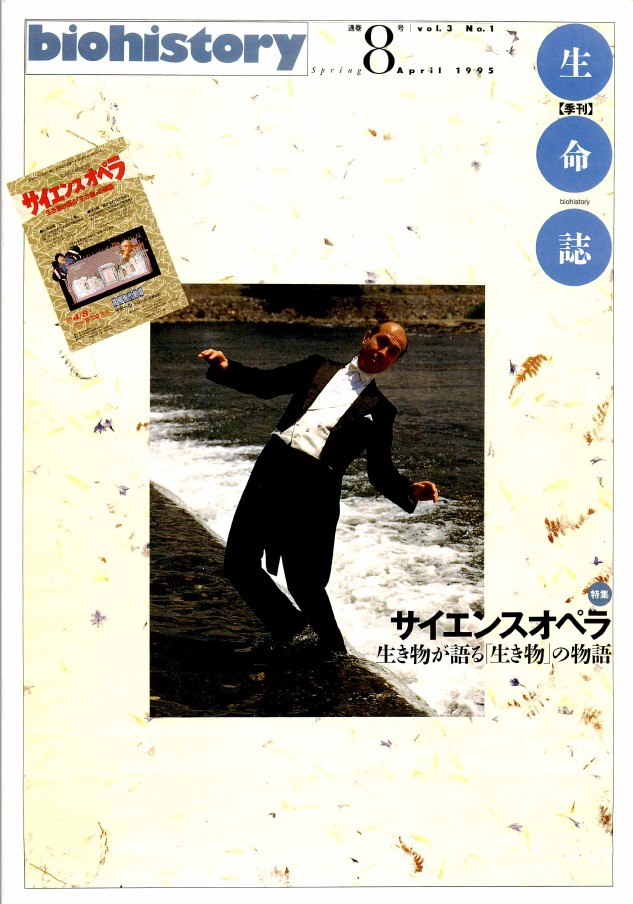
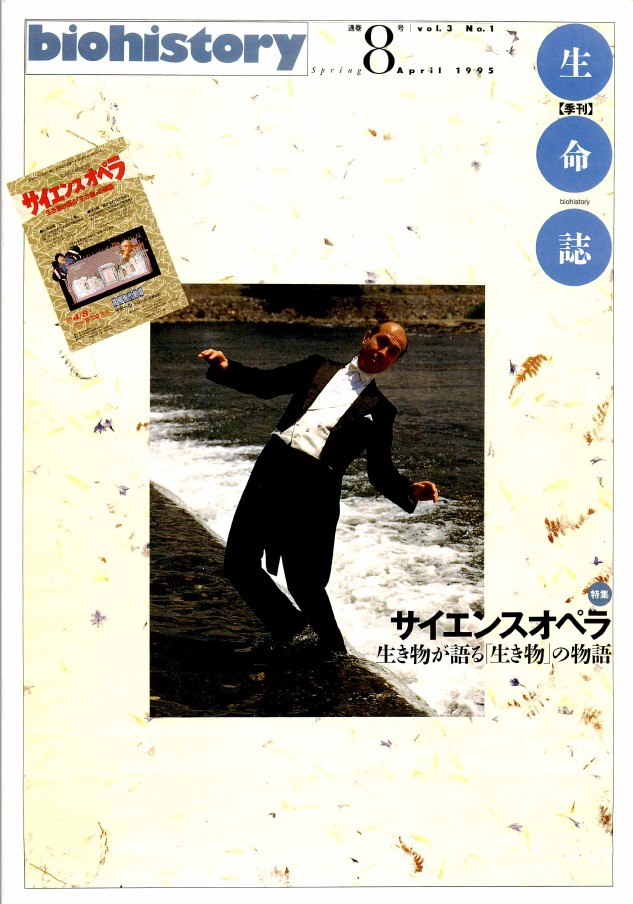
Gallery
生命の波の色さがし ―古代蓮染<蓮の舞>
滝沢布沙
埼玉県行田市生まれ。藍染・草木染デザイナー。埼玉県女流工芸作家協会会員。「藍 is 愛」の会を主宰。各作品に短い詩を添えて想いを語る。行田の古代蓮(市指定の天然記念物)を使った染色に、市長より<蓮の舞>の名を贈られた
-
2025年
地球というわたしたち

-
2024年
あなたがいて「わたし」がいる
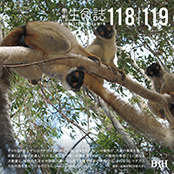
-
2023年
生きものの時間2
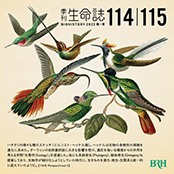
-
2022年
生きものの時間
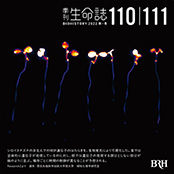
-
2021年
自然に開かれた窓を通して
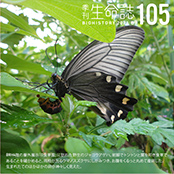
-
2020年
生きもののつながりの中の人間
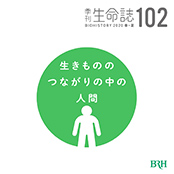
-
2019年
わたしの今いるところ、そしてこれから
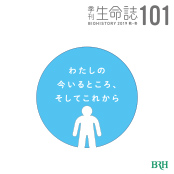
-
2018年
容いれる・ゆるす
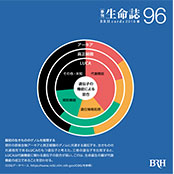
-
2017年
和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-
2016年
ゆらぐ
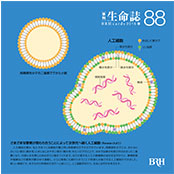
-
2015年
つむぐ

-
2014年
うつる

-
2013年
ひらく

-
2012年
変わる

-
2011年
遊ぶ

-
2010年
編む
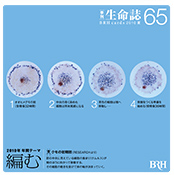
-
2009年
めぐる

-
2008年
続く

-
2007年
生る
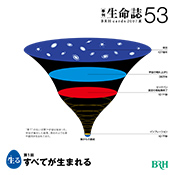
-
2006年
関わる

-
2005年
観る
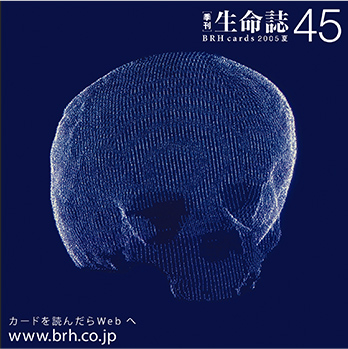
-
2004年
「語る」 「語る科学」
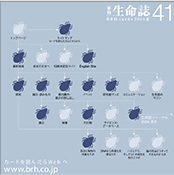
-
2003年
「愛づる」 「時」

-
2002年
人間ってなに?

-
2001年
「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-
2000年
「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-
1999年
「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-
1998年
「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-
1997年
「花が咲くということ」ほか

-
1996年
「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-
1995年
「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-
1994年
「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-
1993年
「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、
多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。
さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。
-
![]()
動詞で考える生命誌
生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命誌の世界観
科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。
- PC閲覧専用コンテンツです。
-
![]()
生命研究のあゆみ
日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。
- PC閲覧専用コンテンツです。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)




