TALK
生物学が豊かだったころ
-18世紀フランスに実験生物学の萌芽を見る-
目のご不自由なマダム・デュ・デファン
かたつむりにとっては気の毒なことですが、悪い目がよい目に置き換わる可能性があるということは、あなたにとって悪いことではないでしょう。
将来再生の研究が進めば、いつか頭全体を置き換えることもできるかも知れません.
新しい頭への置き換えがけっして悪くないと思う人も多いでしょう。
(18世紀フランスの思想家ヴォルテールが目の不自由な親しい女友だちに送った手紙 Newth, D.R. 1958. New (and better ?) parts for old. New Biology 26より)
CHAPTER
実験生物学の源流
岡田
私は常々、発生や再生といった実験的な生物学の一つの創世というべき事態が18世紀フランスにあったことに、非常に関心をもっておったんです。当時、カタツムリの頭は切ってもまたはえてくるといううわさがフランス国内で広まり、多くの科学者や自然愛好家がカタツムリの頭を切りまくったのですが、ヴォルテールもその一人でした。生物を実験によって知るというのは、生物を観察することとも測定することとも違います。生き物を操作することでどんなことが起こるかということから生物を理解しようとします。イギリスの博物誌とはまた違ったこの実験的な生物学が、18世紀からしてすでにフランスにあったということの精神的土壌を、ぜひ中川先生の研究されたところから知ってみたいのです。
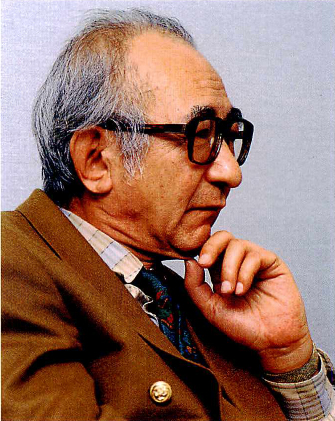
岡田節人生命誌研究館館長(写真=外賀嘉起)
中川
自然科学の発展の歴史が一般的にそうなのですが、いまの生物学は豊かな可能性を切り捨てることによって、先細りしながら、しかしそれによって理論的に洗練されながら伸びてきたように思われます。もちろんそれは進歩です。しかし人文科学では、一般的にもっと幅広いものを中に包み込んでいますから、多様な可能性を捨てないで、生かすことを考える。生物学も多様な可能性をはらんだ元の幅を見直す必要があるのではないか。多様性と可能性を最大限に追求したヨーロッパの18世紀に関心を抱く人間として、私はいつもそう思っています。
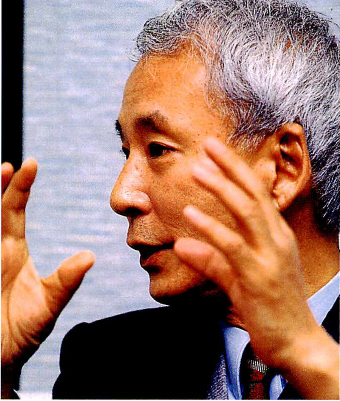
なかがわ・ひさやす
パリ第7大学客員教授、パリ国立東洋言語文明研究所客員教授、京都大学文学部教授などを歴任し、本年3月退官。京都大学名誉教授。4月から近畿大学教授。フランス共和国文部省よりパルム・アカデミック勲章を贈られる。『自伝の文学—ルソーとスタンダール』(岩波書店)、『ディドロ』(講談社)、『啓蒙の時代と比較の視点』(仏文、パリ、PUF社)ほか、著書、編著、論文、翻訳多数。
岡田
確かに現在の生物学は「テーマが貧弱になる」という犠牲の下に「進歩」をしてきましたが、もう少し前の時代にずいぶん宝があったのではないかと思います。たとえば、18世紀フランスにおいて実験生物学が起きました。その背景にはディドロやルソーなどの当時の啓蒙主義哲学と、その一方でやはり神学があるのでしょうね。
中川
実験的生物学の成立は、すでにその前から試みられていた人体の解剖と密接に関係していると思います。解剖が大きく発展したのは、デカルトの学説が出てからなのです。デカルトの理論では、人間の中にある精神、あるいは魂の部分は神と直接結びついているのですが、肉体の部分はたんなる機械にすぎない。要するに二元論です。そうしますと、肉体、すなわち機械には自由に手を加えることができますので、この機械の内部構造を知るために解剖が頻繁に行なわれはじめます。デカルトもオランダに滞在していたころには習'慣的に屠殺場を訪れていますし、自分で解剖も試みています。ただ、このような時代でも、生きた人間には手を加えられませんので、人間以外の生物に手を加えてみる。そういう風潮が、実験的生物学が始まる一つの原因であったと思われます。
漁師の知識から素朴な実験へ
岡田
ところで、温度計の発明者として知られているレオミュールが一生にしたことをみると、まあ半信半疑と言わざるをえないくらい、本人自体が『百科全書』ですね。フランスの啓蒙主義を現実に体現した人間として登場してくるわけですか。
中川
18世紀は、レオミュールに典型的に見られるように、認識すると同時に、自分から進んで現実に働きかけて実験を行なった人たちの時代です。このような形で全人間的な能力を開花させている。ミミズの再生実験をしたボネも、岡田先生のビデオ(生命誌研究館ビデオライブラリー)に登場するトランブレーも、先駆的な仕事をした実験的生物学者レオミュールに影響を受けました。
岡田
エビ・カニの左右の前脚の大きさが違うのは、失った片方がもう一度出てきたからであることを当時のフランスの漁師はすでに知っていた。それが本当か嘘かをレオミュールが実験するんですけれども。そんな素朴な科学はもう二度とできませんが、いまの科学をやるにしても、意識しておきたい立場ではありますね。
存在の大きな連鎖
中川
トランブレーの名前がフランスとヨーロッパにあまねく知れわたったのは、1751年、ディドロが『百科全書』第1巻に非常に長い項目「アニマル」の中でトランブレーのヒドラの実験について、初めて紹介したからです。『百科全書』は相当な部数で売れていました。第1巻が2050部です。
岡田
それはいま流の言葉で言えば、 本当にフロンティア中のフロンティアの研究ですもんね。しかし、実験に対する宗教的反発のあるカトリックの国で、よくヒドラを切り刻んだりしましたなあ。それはやっぱりデカルトやディドロというような知性が、そういうことにあえてチャレンジするという精神的根拠になるんでしょうね。
中川
その当時、 生物学者だけでなく、 ヨーロッパの知識人全体がなぜあれほどトランブレーの実験に熱狂したかと申しますと、ヨーロッパには"the great chain of being"、「存在の大きな連鎖」という思想が存在していたからです。神は最高の善であり、充満しているというプラトンの考えが最初にありました。その充満を流出させることで、神はこの世界を順次造っていった。最初に天使を造り、次に人間を造る。それから動物と植物を造る。鉱物を造る。こういうふうに、存在するもの全部が大きな連鎖をなしている。この連鎖には隙間がないはずですから、動物と植物のあいだにも何かがある。生物学者も、ライプニッツのような哲学者もそれを発見しようと努めた。このような神学的・哲学的背景と、生物学とが一緒になって、18世紀に流れ込んでいるのです。この流れの中でたんなる生物学の狭い枠を越えて、思想家から神学者、僧侶までをも巻き込んで、トランブレーのヒドラの再生実験が大問題になったわけです。
岡田
そうなんですね。その当時トランブレーの実験が一種の危機的社会事件として扱われたらしいことを知って、なるほど当時の科学のあり方というのは、いまとはえらく違うということと、全知識人が、やっぱり科学を包含していたのだということをおおいに思うんです。トランブレーという人の、まことに天才的に意表をついているのは、動物と植物のどっちであるかをただ観察や飼育だけでなく、積極的にまっぷぷたつに切って承て、植物なら2つになるが動物なら2匹にならないはずと設問して実験をやったことです。もちろん結論は間違っているんですけれども、どのようにしてアイディアがわいたのかということの重要性は変わらない。おそらく当時としては、実験して調べるというのは、非常に革新的なことだったと思いますね。
再生は神による設計
中川
トランブレーもボネも晩年になると、自分たちの思想を哲学、神学的な著作としてまとめます。こういうこともやりますから、普通の生物学者の手におえなくなって、無視されてしまうんです。
岡田
ボネはおもしろい実験をやっています。イモリの脚を切ったらもう一度生えてくるという実験で、脚に座標軸を1、2、3、4、5、とつけましてね。切られた痕が覚えていたら、ちゃんとこの位置に生えてくるはずだというセオリーなんですが、なんと1990年代のわれわれが使う「位置情報」という考えと同じです。これは直感プラス神学的なことがあるんでしょうな。
中川
神によるデザインが最初にある。神によってあらかじめ設計されている場所。そういうものとしてすでに与えられている。
岡田
それはまさに近代の生物学が行き着いたところの説明とまったく同じです。位置情報はちゃんとボネのスケッチの中に書いてあるんですね。逆に、現在の生物学はテーマとしては、一歩ずつ昔へ帰っている傾向もあるんです。なぜかというと、昔のほうが多様にして、かつ豊かな生き物の現場を見せていましたから。トランブレーのやった実験の中の一つに、いまでもできないものがあるんですよ。手袋をそのまま脱ごうとすると、裏表逆になるでしょう。ヒドラをそうすると、もとと同じようになるという実験なんです。裏と表がどうやって変わっていったのかというようなことは、生物学ではかなり大事になりますのでね。発生生物学の大御所でノーベル賞をもらったシュペーマンは、これをリピートしようとしてできなかったが、トランブレーの観察したことは現在の研究で見ればどうなっているか。電子顕微鏡で見ればどうなるか。知的遺産としての大きさというのはたいしたものですね。
中川
生物学の中にそういう多様性と豊富さがふたたび戻ってくることを願っています。
岡田
生命誌研究館はそのような昔に舞い戻されたようなものも採り上げてみたいと思っております。プラナリアは20世紀の初めには花形の動物だったんですがね。しかし、スターの位置は、もうとうに失いました。これは切っても切っても再生しますから、じつにおもしろいことがいろいろ起こります。
中川
私が「生命誌」に魅力を感じるのは、反科学に陥らないで、すでに獲得された自然科学の手法は使いながら、生物学を多様な可能性の広がりの中で見ていったらどうなるか、という点に着目されているからです。「生命誌」という命名一つにしても、それに込められているメッセージがある。これからどういうことをなさるのか、非常に強い関心を抱いています。
中川久定(なかがわ・ひさやす)
パリ第7大学客員教授、パリ国立東洋言語文明研究所客員教授、京都大学文学部教授などを歴任し、本年3月退官。京都大学名誉教授。4月から近畿大学教授。フランス共和国文部省よりパルム・アカデミック勲章を贈られる。『自伝の文学—ルソーとスタンダール』(岩波書店)、『ディドロ』(講談社)、『啓蒙の時代と比較の視点』(仏文、パリ、PUF社)ほか、著書、編著、論文、翻訳多数。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)














