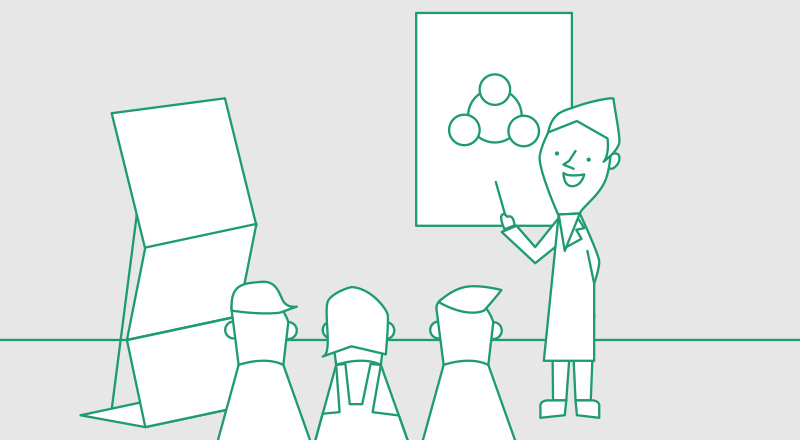Special Story
共生・共進化 時間と空間の中で
つながる生きものたち
モリモリ葉っぱを食べるチョウの幼虫の食欲のすごさをご存知の方も多いでしょう。これも,雌チョウが,幼虫の好んで食べる葉っぱを見分けて卵を産み付けているからです。雌チョウは前脚の感覚毛によって食草の化学物質を味わっているのです。味を感じる受容体があるはずだ。その遺伝子も見つけたい……受容体遺伝子から,アゲハチョウと食草が共進化してきた道を辿ろうという試みが生命誌研究館で始まっています。
CHAPTER
厳しい食草選択
食通で知られる19 世紀初頭フランスのJ.A.ブリア-サヴァランは,味覚は,最も滋養に富む食物を選ぶと同時に,日常のストレスを解消して精神的愉悦を引き起こすと言った。あれこれ味覚を楽しむ人間に比べて,昆虫はどうか。アオスジアゲハがクスノキを食べてストレスを解消しているとは思えないし,糞虫の好物が滋養たっぷりとは言えない。
チョウは一般に単食性だ。それでもモンシロチョウはアブラナ科の多くの種を選択するが,ギフチョウになるとウマノスズクサ科のカンアオイ一種しか食べない。“学問は間違っても,本能は誤りを犯さない”とファーブルが言うように,親チョウは食草にしか産卵しないし,幼虫は餓死しても間違った植物を食べない。昆虫の味覚には明快な進化の理屈が隠されているはずだ。

②カラスザンショウの葉にドラミングしているモンキアゲハ。(写真=吉川寛)
③チョウの前脚ふ節。上が雄,下が雌。雌の方により多くある色の薄い細い毛が,味を感じる感覚毛。(写真=小野肇/JT生命誌研究館奨励研究員)
チョウの味覚と産卵誘導物質
雌チョウはどうやって幼虫の食草を「見分ける」のだろう。飛びながら植物を探す時は,視覚と嗅覚に頼るだろうが,産卵前には,前脚で葉の表面をたたくドラミング行動をする(1937年に発見)。これがチョウの「味見」だ。前肢の先端(跗節(ふせつ))に感覚毛が生えており,毛の内部にある5個の細胞は,長く伸びて脳に繋がる典型的な感覚神経細胞だ(そのうち4個が味を感じる。図④)。アゲハチョウの場合,雌には節あたりに数十本の感覚毛があり,雄には10分の1以下しかない。幼虫には口器に同様の感覚毛がある。もちろん成虫は蜜を吸うためのもう一つの味覚器官をストロー状の口器にもっている。足の味覚は子供のため,口器の味覚は自分のためだ。
食草選択に関わる物質の探索は60年代にヨーロッパで始まり,73年にはキャベツの害虫オオモンシロチョウの産卵誘導物質,カラシ油グルコシドが発見された。85年,京都大学の西田律夫グループがアゲハチョウの産卵誘導物質を発見(『生命誌』通巻5号参照)。その後,広島大学の本田計一らと競い合った精力的な研究で,アゲハやクロアゲハの産卵誘導に,ミカンの葉に含まれるフラボノイド,桂皮酸,サイクロトール,アミノ酸,アデノシンなど6~10種類の物質が同時に必要なことがわかった。ジャコウアゲハは,食草のウマノスズクサにのみ含まれるアリストキア酸で,産卵や,幼虫の摂食も誘導される。この物質は,食草特異的な味覚物質として注目されている。

④節の感覚毛の分布と,感覚毛内部の細胞の様子。5つある細胞のうち,4個が味を感じ,1個は機械的な刺激を感じる。
味覚の受容体遺伝子 ― ハエとチョウ
味や匂いを認識する化学物質受容体の存在は30年代に記述されているが,実体が明らかになったのは,ゲノム研究の時代に入った91年のことだ。マウスゲノムから1000個を超える嗅覚受容体遺伝子ファミリーが発見されたのだ。その後10年,哺乳類を中心に嗅覚受容体による嗅覚物質の認識や,脳へのシグナル伝達の仕組みが急速に解明された(⑤)。その間,味覚の研究者は欲求不満の時期を送ったが,ようやく2000年に哺乳類とショウジョウバエから味覚受容体遺伝子が発見され道が開けた。苦難の遺伝解析によりショウジョウバエのトレハロース(糖の一種)受容体を発見した谷村禎一に始まり,アメリカではショウジョウバエゲノム全配列から,構造上,味覚受容体遺伝子と思われるものが検索され,実際味覚細胞で発現した。ハエの味覚は哺乳類と同じように複雑で,総計五十数種の遺伝子が8個のファミリーを作っているらしい。ハエはすごいグルメなのだろうか。


アゲハチョウの産卵誘導物質は多くても10種類程度なので,雌チョウの前脚の味覚細胞では約10種類の受容体が予想される。残念ながらアゲハゲノムの配列はわかっていない。味覚受容体は種ごと物質ごとに変化が激しいので,ハエの受容体と構造の似た遺伝子を探索するのも難しい。残された道は味覚細胞で発現している受容体のメッセンジャーRNAから遺伝子をクローニングするという地道な方法だけだ。ゲノム情報が豊かなハエの研究を横目に,チョウ特有の味覚と食草の共進化を解き明かそうと,日々努力している。
受容体の進化
味覚受容体が所属する受容体ファミリーは細胞の表面にあり,外部からのあらゆる刺激(光,化学物質,ホルモン,フェロモンなど)を受けて細胞内の主要なシグナル伝達物質であるGタンパク(GTPによる制御タンパク)を仲介に細胞内での種々の働きを引き起こす。生物の内と外を結ぶ特異性の高い「窓」なのだ。細胞膜を7回貫通するという特殊構造をもつ受容タンパク質は,真核生物ゲノムの1~3%を占める最大の遺伝子ファミリーの産物だ。この遺伝子の起原は古く,真核生物が多細胞化して神経細胞を進化させた段階で急激に増えたようだ。ゲノム進化のうえでは,遺伝子重複と変異の組み合わせで遺伝子ファミリーを増加させてきたお手本だ(⑥)。
昆虫では古く水棲時代に味覚受容体が進化し,4億年前の陸上進出の後,その一部が嗅覚受容体に変化したと推測されている。チョウの産卵誘導物質に対する受容体は産卵前のドラミング行動と連携するので,チョウと食草の関係が成立した比較的最近に進化したに違いない。この遺伝子が見つかれば,チョウと食草との関係の歴史をたどることもできるはずだ。これまではチョウと食草の関係を個別に見る研究が主流だったが,アゲハ類の種分化と食草選択の変化や,食草の物質とチョウの受容体の双方の多様化の比較など,共進化の視点から全体をまとめる方向の研究に踏み込んでいきたい。

チョウの味覚レセプター遺伝子の多様化と,食草の成分の対応を調べ,チョウと食草の共進化を探る。味覚レセプターが多様化するに従い,食用とする植物を開拓してきたと考える。起源の古いチョウは,レセプターが少なく食草も限られるが,より多くのレセプターをもつチョウは,現在の食草は決まっていても,以前感じていた味を覚えているかもしれない。まだまったくの仮説だが。カッコの中の遺伝子は通常は働いていないと仮定している。
(よしかわ・ひろし/JT生命誌研究館顧問)
※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)