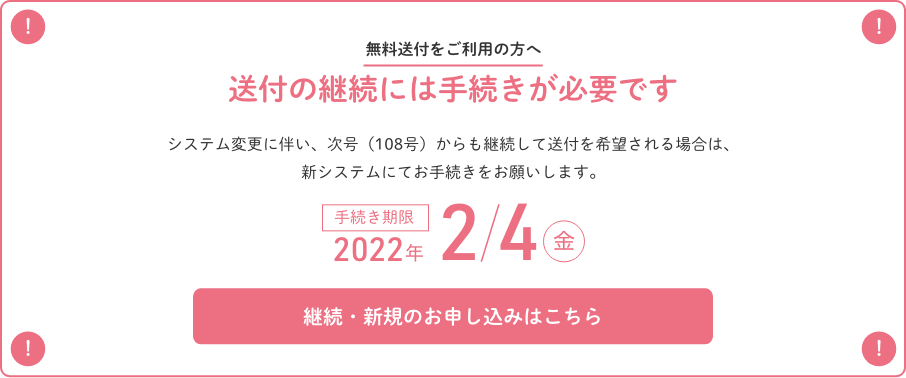RESEARCH
植物の毒とチョウの食草転換
チョウの幼虫の食べ物を選ぶのは母親です。母チョウは前脚で植物の化合物を認識し、食草を選んで産卵します。しかし時に選択がゆらぎ、他の植物に産卵してしまうことも。ここで未知の植物に対応しようとした幼虫の挑戦が、食草転換につながったかもしれません。
1.チョウと植物の深い関係
地球上に存在する昆虫の過半数は、植物を食べる植食性昆虫である。昆虫から動いて逃げることができない植物は、天敵が嫌がる化合物や、毒になる化合物をつくり出して身を守っている。多くの場合、植食性昆虫は体が小さく限られた解毒能力しかもたないため、ごく一部の植物しか食べることができない。
植食性昆虫が、それまで食べていた植物と異なる種の植物を利用するようになることを「食草転換」と呼ぶ。チョウの場合、幼虫が食べられる植物は種によって決まっており、食草転換は新しい種の登場につながるきっかけになったと考えられている(図1)。

(図1)アゲハチョウの仲間(アゲハチョウ科)の系統と食草の対応関係
図の詳しい解説は特設サイト「Ω食草園」WEBへ
現在のチョウと植物のつながりは、互いに関係しながら進化した結果と解釈されてきた。例えば、新たな植物が誕生して新たな化合物をつくり出しチョウの幼虫に食われるのを防いだとする。しかし時が経てば、その化合物を克服する新たなチョウが登場することがある。するとさらにそのチョウを防ぐ新たな植物が生まれ…という具合に、食う・食われるの関係が互いの進化を促したと考えられているのだ。関わりから生まれるこのような進化を「共進化」と呼び、チョウと植物はその代表例とされてきた。
植物と昆虫という、全く異なる生き方をする生きものが関わることで何が起こるのか。そこから生きているとはどういうことかを探りたいという思いから、私たちはチョウの食草転換と種分化について研究を続けている。
2.食草が変わる条件とは?
昆虫にとって、食草を変えることは容易ではない。食草転換が起きるにはどのような条件が必要だろう。チョウの場合、移動能力が低く自力で食草を探せない幼虫のために、飛ぶ事ができる母親が幼虫の食べられる植物を選んで産卵する。食草が変わるには、幼虫が新しい植物を食べられるようになることに加え、まず母チョウがその植物に産卵するようになる必要がある。またこの変化が一代限りで終わるのではなく、成長したチョウが同様の性質をもつ個体と選択的に交尾し、次世代に受け継がれなくてはならない(図2)。

(図2)食草転換が起こるには?
これら最低限の条件を考えただけでも関わる遺伝子は多数あり、全ての変化がかみ合う確率は非常に低いことがわかる。食草転換は実に謎の多い、さまざまな問いを含んだ現象なのだ。
3.食草を選ぶ母チョウの「味見」のしくみ
母チョウの産卵行動について考えてみよう。そもそも母チョウがなぜ、数ある植物の中から幼虫の食草を選んで産卵できるのかは、ファーブルの時代からの謎だった。かつては、チョウの高度な視覚がその判別を可能にしていると考えられていた。しかし1937年、オオモンシロチョウが産卵にどのような視覚情報を用いているのか観察していたイルゼという研究者が、母チョウが産卵する直前に、葉っぱの表面を前脚で素早く叩いていることに気づいた(動画)。
(動画) アゲハチョウのドラミング
ドラミングは、肉眼ではわからないほど素早い動きだ。後半のスローモーション再生で確かめてほしい。
動画の詳しい解説は特設サイト「Ω食草園」へ
葉を叩く行動は「ドラミング」と名づけられ、のちに行われた前脚の解剖学的な研究の結果、前脚の先端にある「ふ節」という組織に植物の化合物を感知する毛(化学感覚毛)があることがわかった。ここで感知するのは、ヒトが味覚で感じるのと同様に不揮発性化合物(水溶性・脂溶性)の化合物である。つまりチョウは前脚で植物を「味見」することで食草を判断していたのだ。
ミカン科の植物を利用するナミアゲハは、日本で最も身近なチョウの一つだが、産卵につながる「味」の実体が解明されている数少ないチョウでもある。日本の研究者により、ナミアゲハの産卵の決め手となる化合物(「産卵刺激物質」と呼ぶ)が、ミカン科植物に含まれるカイロイノシトールやシネフリン、スタキドリンなど10種類の化合物であることが明らかされており、食草選択のしくみを探るのに最適な材料なのだ。
ナミアゲハ前脚の「ふ節」にある化学感覚毛には、4つの味覚神経細胞がある。味覚神経細胞の表面にある味覚受容体がセンサーの役割を果たして化合物を捉え、脳に情報を伝える(図3)。

(図3) チョウが前脚で味を感じるしくみ(上:チョウの前脚、下:ふ節の毛の拡大断面図)
図の詳しい解説は特設サイト「Ω食草園」へ
私たちは味覚受容体をつくる遺伝子の一つを特定することに成功した。この遺伝子は、ミカンに含まれる化合物・シネフリンを受け取る受容体をつくる遺伝子である。シネフリンとカイロイノシトールを混合した溶液を感知すると、通常の母チョウは高い確率で産卵するが、この遺伝子のはたらきを人為的に阻害した母チョウは、同じ混合溶液に触れても産卵しない。おそらくシネフリンを感知できなくなったためだろう。チョウの食草選択が味覚受容体の遺伝子によって制御された行動であり、遺伝子が変化すれば食草の判断が変わりうることを示す、世界で初めての成果である。
常に正確に見える母チョウの食草選択だが、遺伝子や化合物などが変化しなくても、極めて小さな変化によって認識のしくみが変化し、好みが変わる可能性がある。実際、羽化後長い日数を経過したメスはしばしば食草ではない植物に産卵してしまうことが報告されており、母チョウの間違いは私たちが思うより頻繁に起きているのかもしれない。食草転換の第一歩となる、母チョウ食草選択の変化が過去にどのような形で起きたのか、探っていきたい。
4.幼虫が利用できる植物の範囲はどう決まる?
チョウと植物は共進化の典型とされてきたが、世界に1万種以上生息するチョウと植物の関係は、未だ十分に理解されているとは言い難い。そこで私たちは、過去の図鑑や論文に膨大に蓄積された、日本にいるチョウとその幼虫が利用する植物の関係をビッグデータ化し、両者の関係を見渡す解析を行った(図4)。

(図4)植物・チョウの系統関係と植物の化合物の関係
チョウと植物の対応関係は、植物に含まれている化合物が重要であることがわかった。
出典:Muto-Fujita et al, Scientific Reports 7:43368 (2017) Adapted この図の詳しい解説は特設サイト「Ω食草園」へ
チョウと植物が共進化したならば、新たな化合物をもつ植物が分岐した後、それを利用する新たなチョウが分岐したはずである。この場合、植物と昆虫の系統樹の形が一致すると予想されるが、そのような傾向はみられなかった。基本的にはチョウは科という分類のまとまりごとに、決まった科の植物を利用する傾向があったが、これは植物に含まれる化合物が似ていることに起因しているだろう。チョウの幼虫が新たな植物を食べられるかどうかは、含まれている化合物が似ていることが重要のようだ。植物はチョウを避けるために化合物を進化させて、チョウがそれを追いかけるように種分化してきたわけではなく、チョウが類似した化合物の植物を渡り歩くように食草転換を繰り返してきたのではないだろうか。チョウと植物は、これまで共進化の文脈で語られてきたような競争関係ではなく、もっとゆるやかなつながりをもちながら進化してきたというストーリーもあったのではないかと考えている。
植物がつくる化合物には、昆虫に対して明確な毒性をもつものや苦いと感じさせるもの、刺激になるものなどがある。チョウの幼虫にとって食べられる・食べられないを分ける、より決定的な化合物はどのようなものなのだろう。私たちは、昆虫に対して毒性をもつ化合物のみに着目し、さらなる情報を文献から収集し解析を行った。その一部を以下に示す(図5)。

(図5)昆虫に対する毒となる成分の組成
同じ科の植物がもっている毒の種類を集計した。科によって、多くもっている化合物のタイプが明瞭に異なることがわかる。
昆虫に対する毒性という観点からみると、主要な毒は科レベルで特徴的なものもあることがわかる。興味深いことに、キアゲハの食草であるセリ科と、ナミアゲハの食草であるミカン科は、共にフラノクマリン類が主要な毒成分であるという点で似ているのだ。
キアゲハはアゲハチョウのグループの中では新しく出現した種であり、ナミアゲハと近縁で見た目もよく似ている。アゲハチョウ属の多くのチョウが、かんきつ類やサンショウなどのミカン科植物を食べるのに対し、キアゲハの仲間はミツバやアシタバを含むセリ科植物を食べる。ミカン科とセリ科は、人にとっては味も香りも異なるし、植物の分類群としても遠縁なのに、なぜキアゲハの仲間がセリ科を食べるようになったのかは謎だったが、フラノクマリン類に対する解毒能力がその鍵なのではないかと考えた。

(図6) ミカンに産卵するナミアゲハ(左)とアシタバ(セリ科)に産卵するキアゲハ(右)
5.秘められた幼虫の柔軟さ
ミカン科とセリ科は毒の成分が似ているとしても、ナミアゲハがセリ科を食べることはできない。同じミカン科の植物の間でもフラノクマリン類の含量や種類が異なるため、ナミアゲハとミカン科植物を使って、幼虫がフラノクマリンの変化にどのように対応するかを探ることにした。
餌に使ったのはミカン科のハッサクとカラスザンショウである。ハッサクはフラノクマリン類をわずかにしか含まないのに対し、カラスザンショウはフラノクマリン類の化合物を複数種含む。私たちは兄弟の幼虫たちを2グループに分けて、それぞれの葉っぱを食べさせ、幼虫の体ではたらいている遺伝子の発現量を網羅的に調べるトランスクリプトーム解析を行った。その結果、餌のちがいによって解毒機能に関与すると予想される遺伝子のいくつかが、カラスザンショウを食べた場合にだけ発現量が上昇していることを見つけることができた。これらの遺伝子が属するCYP6B遺伝子群の中には、メスクロキアゲハなど他のアゲハチョウで、フラノクマリンの解毒に関わっていると報告されているものがある。このことから、カラスザンショウが持つフラノクマリンの影響で、ナミアゲハのCYP6Bファミリーの発現量が上昇したのではないかと考えた。
CYP6Bに属する遺伝子はアゲハチョウ科のチョウに広くみられ、相同性が高い遺伝子はキアゲハにもみられる。キアゲハの祖先は、ミカン科を食べるために使われてきた解毒の遺伝子をセリ科の毒に転用し、食草転換に成功したのかもしれない(図7)。

(図7)異なる食草を利用している、ナミアゲハとキアゲハの来た道を推測する
また、ナミアゲハ・キアゲハの祖先よりさらに時代を遡ったアゲハチョウ科全体の共通祖先が、マメ科を利用していたと考えられている。マメ科にも、ミカン科やセリ科ほど豊富ではないもののフラノクマリンが数種含まれており、アゲハチョウはこの時代からフラノクマリンに対応するCYP6B遺伝子をもっていたのだろう。母チョウが産卵する植物を間違えると、産まれた幼虫は死んでしまうことの方が多い。だがアゲハチョウの仲間は、祖先から受け継いだ解毒の遺伝子を柔軟に転用し、新たな食草を開拓してきたのかもしれない。

尾崎克久(おざき・かつひさ)
生命誌研究館 昆虫食性進化研究室
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)