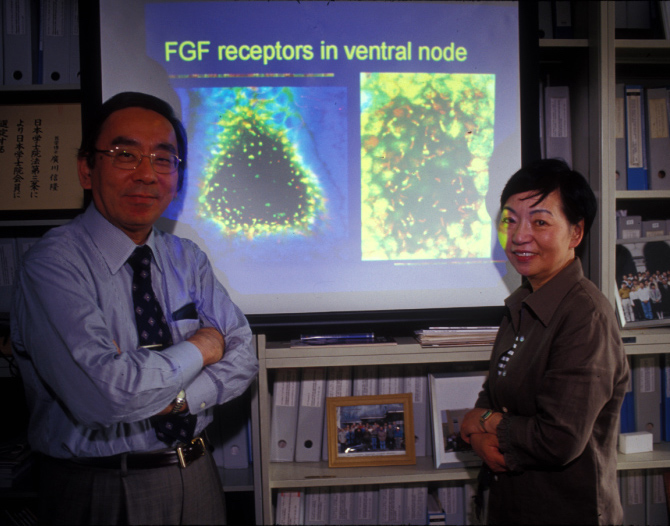
TALK
動きを観る
ミクロの解剖学から体全体へ
1. 瞬間から動きを取り出す
中村
 私共の今年のテーマは「観る」です。本来、観察から始まった生物学がミクロの世界に入って化学反応を追ってきました。たとえば、生化学や分子生物学。でも、観ないとわからないという気持ちがあります。一方でミクロを観る技術がたくさん開発され、分子の姿も見られるようになった今、改めて「観察」の大切さが浮かんできたと思います。たとえば細胞は光学顕微鏡で見ると水がチャポチャポみたいで構造など見えませんでしょ。でも、今の講義を伺って細胞内の物質輸送にさまざまな視点から迫ると、こんなに豊かな生きものの姿が見えてくるのだという迫力を感じました。生きている細胞内の動きを実際に見て確認できるのは魅力的ですね。「観る」という言葉には時間の流れも入れたいと思っていたのですが、まさにそれです。様々な可視化手法を駆使しての研究に「観る」というテーマがつまっていると思い、楽しみです。
私共の今年のテーマは「観る」です。本来、観察から始まった生物学がミクロの世界に入って化学反応を追ってきました。たとえば、生化学や分子生物学。でも、観ないとわからないという気持ちがあります。一方でミクロを観る技術がたくさん開発され、分子の姿も見られるようになった今、改めて「観察」の大切さが浮かんできたと思います。たとえば細胞は光学顕微鏡で見ると水がチャポチャポみたいで構造など見えませんでしょ。でも、今の講義を伺って細胞内の物質輸送にさまざまな視点から迫ると、こんなに豊かな生きものの姿が見えてくるのだという迫力を感じました。生きている細胞内の動きを実際に見て確認できるのは魅力的ですね。「観る」という言葉には時間の流れも入れたいと思っていたのですが、まさにそれです。様々な可視化手法を駆使しての研究に「観る」というテーマがつまっていると思い、楽しみです。
廣川
自分の目で確認しなくては気が済まないたちなのですよ。医学部の授業の中で最も好きだったのは組織学(註1)。実習の時に光学顕微鏡で内耳を見たのですが、ものすごく美しく精妙にできている組織に感動しました。異なる細胞に分化したものが見事に統合して我々は生きているという事実を目の当たりにした気分になりましたね。
中村
観る作業には美しいという判断が入るところが面白いと思うのです。科学は客観的にと言いますが、美しいと思うことが大事ですよね。内耳は学生時代に誰もが見るわけですが、美しいと感じる人と、さっと通りすぎる人とがいるのでしょうか。
廣川
どちらかに分かれますね。私は視覚的に理解する人間で、まず構造、そしてその背後にある機能をわかりたいという欲求が強いのです。
中村
観ることで、構造と機能を結びつけることがやっとできる時代になってきましたね。
廣川
研究を始めた若い頃は電子顕微鏡しかなかったのに、今ではX線結晶構造解析、クライオ電顕、一分子生物物理学など、さまざまな角度から生きものを観る研究ができますから本当に幸せです。 学部卒業後に臨床の脳外科に入りました。内科は生化学ですが、外科は解剖学。腫瘍などを手術するには、血管を傷つけずに出血を少なく到達して、それを摘出する必要がある。脳外科に限らず、血管の走行が頭に立体的に入っていることが正確な手術をする第一歩です。外科とはまさに観る世界なのです。 脳外科の中でも腫瘍に興味があったので、摘出した腫瘍の組織標本を顕微鏡でせっせと見ました。電子顕微鏡が入ったばかりで、新しく見えてくる姿に興奮したのを覚えています。しかしガン研究は腰を据えないと根本的な解決にはつながらず、基礎的な研究が必須ですが、臨床研究では新しい診断法や治療法の開発が主体です。
中村
外科から解剖学研究室に移られたのは知に対する根源的な欲求の方が強かったためですね。
廣川
僕は研究者になるなら、迷うことなく生きものの構造を対象にしようと思っていました。
中村
でも当時の医学は細胞内の反応を調べる生化学の全盛期でしたよね。
廣川
実は戦後の基礎医学分野での方法論の大きな進歩として、生化学の超遠心分離法(註2)と解剖学の電子顕微鏡、それから生理学では電気生理学がありました。僕は構造とその背後にある機能を見たいとの思いから電子顕微鏡を選んだのです。
中村
その情熱で電子顕微鏡の世界で急速凍結法を開発された。
廣川
理論的には1960年代の初めから可能とわかっていましたが、誰も成功していませんでした。日本で挑戦したのは私達だけで、手作りの凍結装置で研究を始めました。
中村
新しいことをやろうと思うと装置から手作り。そこまで苦労しても、挑戦した急速凍結法の魅力は何ですか?
廣川
 とにかく自然な状態を見たかったのです。従来の電子顕微鏡法では化学的な固定をするために細胞内の反応を完全に止めるまで時間がかかります。例えばシナプス(註3)の情報伝達機構はミリ秒の単位で起きるから、化学固定ではとても間に合わない。見るためには瞬間的に凍結する必要があるのです。
とにかく自然な状態を見たかったのです。従来の電子顕微鏡法では化学的な固定をするために細胞内の反応を完全に止めるまで時間がかかります。例えばシナプス(註3)の情報伝達機構はミリ秒の単位で起きるから、化学固定ではとても間に合わない。見るためには瞬間的に凍結する必要があるのです。
中村
なるほど。急速凍結は、細胞の時間を瞬間で止めるからこそ逆に時間の流れがわかるのですね。
廣川
瞬間を積み重ねれば、流れが見えるでしょう。生きものは動いています。生物を理解するにはその動きを見なければ。
(註1)組織学
機能的・構造的な細胞の集団つまり組織についての学問。いわば細胞の社会学。
(註2)超遠心分離
超高速回転によって、低速回転では沈降しないタンパク質やウィルスなどの分離、濃縮や、細胞内の構造体を分けることができる。
(註3)シナプス
神経細胞の軸索の末端ともうひとつの神経細胞の細胞体や樹状突起に接合する部分のこと。お互いの細胞の膜は接しているが、つながってはいない。ここに放出される物質を介して神経細胞の興奮が伝えられる。
2.電子顕微鏡写真に現象を閉じこめる
中村
観るための手段として、電子顕微鏡だからできたという体験にはどんなことがありますか?
廣川
 解剖学教室に移って、最初にシナプスの形成機構を電子顕微鏡で解析しました。感覚細胞に神経細胞が接合する時のシナプス接合のできかたと、感覚細胞の分化や神経支配の関係を見てみたいと思ったのです。当時、ヘビ毒のバンガロトキシンの中に神経伝達物質(註4)の受容体を阻害するαフラクションと神経伝達物質の放出を制御するβフラクションがあるということがわかっていた。ニワトリの胚にそのβフラクションを打ったところ、卵の殻の中にいる胚は生きているのに孵らなくなってしまったのです。横紋筋や神経、特に運動神経が変性していました。ただ不思議なことに、心臓はまったく問題がなく、生きているんです。それで、内耳を見ると、有毛細胞はあるのに知覚神経がなくなっていました。驚いてすぐに論文にまとめました。それが、電子顕微鏡を使って興奮した初めですね。
解剖学教室に移って、最初にシナプスの形成機構を電子顕微鏡で解析しました。感覚細胞に神経細胞が接合する時のシナプス接合のできかたと、感覚細胞の分化や神経支配の関係を見てみたいと思ったのです。当時、ヘビ毒のバンガロトキシンの中に神経伝達物質(註4)の受容体を阻害するαフラクションと神経伝達物質の放出を制御するβフラクションがあるということがわかっていた。ニワトリの胚にそのβフラクションを打ったところ、卵の殻の中にいる胚は生きているのに孵らなくなってしまったのです。横紋筋や神経、特に運動神経が変性していました。ただ不思議なことに、心臓はまったく問題がなく、生きているんです。それで、内耳を見ると、有毛細胞はあるのに知覚神経がなくなっていました。驚いてすぐに論文にまとめました。それが、電子顕微鏡を使って興奮した初めですね。
中村
止まった姿、形を見るよりも、廣川さんは構造を強調しながら構造の裏にある動きを探る姿勢ですね。
廣川
構造という立脚点を拠り所にしているけれど、実際に知りたいのは生きものです。美しいと思ったのが出発点だったけれど、美しさしか見いだせないのなら、生命科学ではなく芸術でしょう。
中村
分子生物学がすすみ、モノ、つまり遺伝子は山ほど分かってきました。遺伝子がつくるタンパク質も次々と明らかになっています。ですから、還元的に研究してきた人たちがあまりの情報の多さに行き詰まるわけです。解決方法として、統計的な処理だけでなく、観ることも大切な視点です。
(註4)神経伝達物質
神経細胞の軸索末端から放出されて隣接する神経細胞に興奮を伝える物質
3.ブラックボックスを覗く
廣川
電子顕微鏡の急速凍結方法を開発したので、誰も見たことのない新しい構造をみることができました。幸せでしたね。
中村
そこから対談前に話して下さった現在のわくわくする話が始まるわけで、楽しみです。
廣川
どれもこれも見たことがないものの中で、気になるものが一つ。オルガネラと微小管との間の構造です。後に細胞の物質輸送を担うモーター分子であることがわかりました。私とモーター分子との出会いであり、まさに現在の仕事の原点です。
中村
子どもの頃に玉ねぎの組織を顕微鏡で覗きますが、原形質流動(註5)という言葉の影響もあり、中はジャブジャブしたイメージを持っている方が多いと思うのですが、細胞骨格という言葉を初めて聞いたとき、なるほどと思いました。
廣川
実際に電子顕微鏡写真を見ると、細胞は実に複雑で込み入っていて、ものがたくさん詰まっています。細胞の中にはレールが走り、さまざまなものが動き、うまく生命現象を保っている。
中村
 私たちの体を形づくる細胞も、分子から見たらかなり大きいので骨格で支え、しかもそれがものを運ぶレールのはたらきをしているのですからうまくできていますね。構成するのは分子やオルガネラ。まるで人がいて、小さな家も高層ビルも建っている街のようです。そこを電車や自動車が走り物を運ぶ。でも、そのように細胞を想像する方はまだ少ないと思うのです。
私たちの体を形づくる細胞も、分子から見たらかなり大きいので骨格で支え、しかもそれがものを運ぶレールのはたらきをしているのですからうまくできていますね。構成するのは分子やオルガネラ。まるで人がいて、小さな家も高層ビルも建っている街のようです。そこを電車や自動車が走り物を運ぶ。でも、そのように細胞を想像する方はまだ少ないと思うのです。
廣川
静的な細胞像が流布していますからね。最近は、タンパク質に蛍光を発する分子をつけて様子を観察するGFP技術(註6)が広まり、細胞内の分子が規則的に動いていることや、輸送されることを研究者自身も実感しやすくなりました。 ところが、多くの神経科学者は細胞膜に埋まっているチャネルや受容体などに注目していて、彼らにとって神経細胞はまるで細胞膜に包まれたブラックボックスなのです。本質の理解には中を観る必要があります。
中村
人間が作った高速道路はよく交通渋滞を起こすのに、細胞内では複雑なことをうまくやっているものですね。
廣川
微小管上にはモーター分子が動くことのできる13本の細いレールがあります。モーター分子は容易に隣のレールに乗り換えることができます。一本のレール上を進む傾向があるモーター分子があれば、ふらふらレールを横に追いかけながらまるでダンスをするようなものもある。たとえぶつかってもトラックのように堅いものではないので、すり抜けるのでしょう。
中村
神経細胞の末端に運ばれるだけでなく末端から細胞体へ戻すものもあるのですか?
廣川
神経細胞の細胞体から軸索の末端までたどり着いた用済みモーター分子が壊されると同時に、反対へ向かうお帰り用のモーター分子が活性化します。これが廃棄物や細胞内にとりこんだ成長因子などを運び、核の中で遺伝子のスイッチを入れたりするのです。
中村
運ばれる分子の道のりを想像すると、指の先が動くということが改めてすごいと感じます。
(註5)原形質流動
細胞質や細胞小器官が流れるように動く現象のこと。
(註6)GFP技術
GFPという緑色の蛍光を発するタンパク質をつくる遺伝子を知りたい遺伝子につなげる。すると知りたい遺伝子のつくるタンパク質が生きた細胞内や個体のどこではたらいているかが分かる。細胞生物学や分子生物学などの分野で威力を発揮している技術である。
4.階層を貫く動き
中村
細胞内の現象を分子、特に遺伝子で説明しようというのが現在の研究の主流です。例えば、ガンならガン遺伝子を思い浮かべる。しかし、遺伝子を調べるだけでは細胞の反応経路内のある箇所が欠けたときにがん化するという因果がわかるだけで、具体はわかりませんでしょう。
廣川
本質への近道は観ることです。我々はあるカドヘリンとβカテニンを運ぶモーター分子がはたらかないと、ガンになるという現象を明らかにしました(註7)。神経細胞での実験ですから、脳腫瘍になりましたが、他の細胞でやればその組織のガンになるでしょう。
中村
生命の基本は細胞。分子の集まりが細胞、細胞の集合が個体ですから、細胞内の全ての動き、ついで臓器の中での細胞の動きを観るというようにして全体をつないでいくこと。それもDNA→RNA→タンパク質という流れだけでなく動きを観ることが大事なのですね。
廣川
非常に重要な切り口だと思います。先ほどのガンの話だけでなく体の左右軸の決定(註8)が典型的な例です。
中村
その最近のお仕事はとても魅力的でこれぞ生物研究と思いました。左右の決定ではNodal(註9)というタンパク質が注目されていましたから。
廣川
 体の左右軸の決定に関する研究は思いかけず発生生物学に飛び込むきっかけを与えてくれました。モーター分子のはたらきを知りたくてモーター分子KIF3のノックアウトマウス(註10)を作成したら、左右軸がきちんと決まらなかった。"Jump into the developmental biology with very big splash"。つまり、大きな水しぶきを上げて発生生物学に飛び込んでしまったのだ。左右軸の決定に関する研究はみな遺伝子だけに注目していたのですごい反響でした。
体の左右軸の決定に関する研究は思いかけず発生生物学に飛び込むきっかけを与えてくれました。モーター分子のはたらきを知りたくてモーター分子KIF3のノックアウトマウス(註10)を作成したら、左右軸がきちんと決まらなかった。"Jump into the developmental biology with very big splash"。つまり、大きな水しぶきを上げて発生生物学に飛び込んでしまったのだ。左右軸の決定に関する研究はみな遺伝子だけに注目していたのですごい反響でした。
中村
遺伝子だけでなく、細胞内でなにが起きているのかと観た結果。今の研究のあり方にも一石を投じましたね。
廣川
科学雑誌「ネイチャー」も我々の左右軸研究の発表後に発生生物学にとって細胞生物学的な見方が重要だと特集しました。まさに、中村先生が言われた視点です。私自身、繊毛が回転して細胞外液の左向きの流れを作り、分子を運ぶことで体の左右が決まるとは予想もしませんでした。
中村
遺伝子は基本ですが、分子や細胞の動きを忘れてはいけないという、ある意味では当たり前の視点が抜け落ちていた。研究ってある方向が出されると皆それしか見なくなりますから。
(註7)モーター分子KIF3とガンの関係
モーター分子KIF3はゴルジ体から細胞膜へカドヘリンやβ-カテニンを運ぶ役割がある。KIF3がうまくはたらけずに、β-カテニンが細胞質にたまると腫瘍を形成してしまう。モーター分子がガン形成に関わる可能性を初めて示した。
(註8)モーター分子KIF3と体の左右軸の関係
モーター分子KIF3がはたらかないマウスでは、内臓の左右が逆になるものがある。原因をさぐると、胚発生の初期にノードという部分で胎児外液の左向きの流れがなくなっていることが分かった。KIF3がはたらかないと、ノードの左向きの流れをつくる繊毛ができず、その流れに乗って運ばれるシグナル分子がノードの左側に到達できず、その分布が変わる。そのため、遺伝子をはたらかせるシグナル分子がノードの左側だけでなく右側の細胞に作用し、内蔵の左右決定がランダムになる。
(註9)Nodal
ほ乳類や鳥類、は虫類は胚発生の初期に体の左側だけ、つまり非対称にはたらくタンパク質のこと。
(註10)ノックアウトマウス
特定の遺伝子がはたらかないように遺伝子操作されたマウスのこと。
5.近道は自分ですべてを
中村
廣川さんの教室の名前が細胞生物学・解剖学であるのが象徴的だと思うのですが。
廣川
医学部には医師の職業教育と学問としての基礎医学があります。基礎医学は大きく解剖学、生化学、分子生物学、生理学等に分けられます。今は分子細胞生物学者と名乗りますが僕のルーツは解剖学です。今の生命科学には構造を主体とした立場、遺伝子などのモノを主体とする立場、それからもうひとつ、現象を主体とする立場があります。それぞれ学問のルーツがありますが、細胞の中で起こっていることは学問を意識して分かれているわけではない。我々も、生化学や分子生物学を使います。今や違った切り口を多く持つことが大切です。僕たちはモノを可視化する方法論を開発しながら、切り口全てを取り入れて問題を解いているわけです。
中村
マクロの世界の構造を見てきた解剖学と、モノを知ろうとしてきた学問が今、細胞でつながっているという歴史を示す教室名ですね。
廣川
生きものの構造は静的ではありません。当然、動きをさまざまな角度から観ることが生きものの理解には必要です。X線結晶構造解析などによって、原子レベルまで構造の情報が分かるようになり、細胞内の分子が動くしくみがわかっているのですから、とてもエキサイティングですね。
中村
廣川さんの居室には雑誌の表紙がずらっと並んでいる。自分の研究が表紙になるって研究者の一つの夢でしょ。よいお仕事をなさっているからだけれど、決め手が写真であるというのは、まさに「観る」強みとも言えますね。
廣川
 光学顕微鏡でも、電子顕微鏡でもよい仕事の時は美しいんです。例えばこの電子顕微鏡写真、うまく凍結したから微小管の径がすっと一定ですし、膜小器官もふっくらとしているでしょう。大きな氷晶形成によってできる壊れた構造がないのです。
光学顕微鏡でも、電子顕微鏡でもよい仕事の時は美しいんです。例えばこの電子顕微鏡写真、うまく凍結したから微小管の径がすっと一定ですし、膜小器官もふっくらとしているでしょう。大きな氷晶形成によってできる壊れた構造がないのです。
中村
表紙を見比べると電子顕微鏡以外にもさまざまな手法を取り入れていますね。モーター分子の生体内での意味などを知ろうという目的が明確で、そのためにはあらゆる技術を駆使する姿がすごい。全体を見渡しているのがよくわかります。
廣川
僕は細胞内の分子の輸送機構に大きな問いをみつけました。鍵となる主役はモーター分子。それを知るために分子細胞生物学、分子遺伝学、行動生物学、X線結晶解析、クライオ電顕、生物物理学など徹底的にいろんな方法を駆使しました。必要とあらば、新しい手法を取り入れることに抵抗はありません。大したことないと思えばこちらの勝ちですから。もちろん、全部自分でやるわけにはいかないので、大学院生を派遣して、新しい手法を勉強させて、それから私が勉強するのです。技術導入は研究室の財産として次の人たちにも受け継がれます。
中村
問いに対する答えを得るために、この方法だと思ったら自分たちでやる。
廣川
共同研究として「この実験を助けてくれませんか」と頼んでも、その相手は自分の仕事を持っていますから、困難な問題ほど解決に時間がかかります。結局は自分達でやる方が結果に確信も持てる上に速いのです。
6. 複雑な全体像を観る
中村
モーター分子を通して細胞を観てきた廣川さんが次に狙うものは何でしょう?
廣川
生きた全体像を観ることを目指してます。生きた細胞が観たい。モーター分子にGFPをつけると、マクロレベルの細胞内でモコモコ動いているのが見えます。それを取り出して微小管の上で一分子だけを見ることができます。電子顕微鏡で原子レベルの構造も見られます。しかし、まだ見るために切り出してきたものと細胞内の間には隔たりがある。モーター分子に関していえば、細胞内ではまだ分かっていない輸送の制御分子が、複雑な物質輸送を全体として成り立たせているはずです。その生きた全体像を理解したいのです。
中村
それには何が不足しているのですか。
廣川
まずは生きた細胞の中を可視化するための分解能。それと単一のものだけでなく、幾つかの異なる要素の関係を観るための方法です。当然、動きも入って来ます。そこが一つのゴールでしょう。細胞内の出来事が我々の体に大きな影響を与えますから。モーター分子KIF3のはたらく細胞が体の左右軸決定に関わりますが、KIF3以外にも物質輸送に関わるモーター分子はたくさんありますから、それぞれについてもっと詳しく観てみたいですね。細胞内の物質輸送がもたらす生体への意味は予想ができません。モーター分子は我々を予想もできないところに連れていってくれるのです。
中村
モーター分子が大活躍する細胞はまさに活気ある街のイメージですね。生命誌研究館では「細胞くん」と題して細胞内の複雑な世界をCGで表現し、そのイメージを伝えることを始めました。その時CGを作ってくれた若者が「細胞ってとても広いんですね。」としみじみ言ったのです。分子の動きを作っているうちに分子の気持ちになったのですね。まるで東京のような細胞内を分子が間違いなく渋滞もなしに運ばれることに本当に驚きます。
廣川
 以前の生命誌の記事(生命誌10号:生命をささえる運び屋分子)で、モーター分子が人の大きさだとすると直径数mぐらいの土管の上をね、10tトラックを担いで秒速100mで地球を2週半も走り回っている状態だとたとえていただきました。さまざまな種類のモーター分子が常にそれだけの大仕事をやっているわけですよ。それに方向性の制御があり、神経細胞だと樹状突起と軸索の方向に必要な分子を送り分けているのです。東北新幹線と東海道新幹線のように。それから終着駅に着いたら荷物を下ろさなければいけません。その機構も、まだまだわからないことだらけです。
以前の生命誌の記事(生命誌10号:生命をささえる運び屋分子)で、モーター分子が人の大きさだとすると直径数mぐらいの土管の上をね、10tトラックを担いで秒速100mで地球を2週半も走り回っている状態だとたとえていただきました。さまざまな種類のモーター分子が常にそれだけの大仕事をやっているわけですよ。それに方向性の制御があり、神経細胞だと樹状突起と軸索の方向に必要な分子を送り分けているのです。東北新幹線と東海道新幹線のように。それから終着駅に着いたら荷物を下ろさなければいけません。その機構も、まだまだわからないことだらけです。
7. 新しいマクロの始まり
中村
お話を伺っていると、マクロとミクロの世界をつなぐイメージが生まれて楽しいですね。
廣川
我々の方法論では、遺伝子を発見すると、それが分子として細胞でどうはたらくかと同時に、個体レベルでの機能や行動も明らかにできるところが面白いんです。そういう意味で、従来の記載するだけの解剖学とは一線を画した新しいマクロの時代が始まったと思います。「ヒトの体では心臓は左側、膵臓、脾臓は右側と非対称にある」と記載する従来のマクロだけでなく、どの様にして体の非対称性が生ずるのかという我々の体の成り立ちの仕組みが分子のレベルから分かるという、新しいマクロに挑戦できるのです。
中村
まさにおっしゃる通りで、生命科学全体において、遺伝子からマクロまでつながっているということを、頭では想像できても実践されている方は本当に少ないですよね。遺伝子を探す人はそれが目的ではないのに遺伝子を20個探しますなどという目標を立ててしまう。
廣川
個々の事象ではなく、生命現象を観たい。細胞の中での物質輸送の機構を探るきっかけになった急速凍結法による細胞の電子顕微鏡写真には、おそらく全ての役者が見えているはずだけれど、私たちが理解しているのはほんのわずかです。ここに見えているもの全てを理解したいという気持ちが研究する動機です。
中村
 一枚の写真から小胞と微小管の間にある小さな分子に眼をつけ、これが運び屋じゃないかと直観した廣川さんのセンスが素晴らしい。観るの基本に直観ありですね。最近、プロジェクト型科学研究の影響で、問を立てずに研究する人が増えているのが気になります。プロジェクト型研究では、数に追われて「これが知りたい」という問いを立てることが少ないでしょう。分子生物学会の要旨でも、網羅、網羅と並んでいる。
一枚の写真から小胞と微小管の間にある小さな分子に眼をつけ、これが運び屋じゃないかと直観した廣川さんのセンスが素晴らしい。観るの基本に直観ありですね。最近、プロジェクト型科学研究の影響で、問を立てずに研究する人が増えているのが気になります。プロジェクト型研究では、数に追われて「これが知りたい」という問いを立てることが少ないでしょう。分子生物学会の要旨でも、網羅、網羅と並んでいる。
廣川
まるで工場みたいですから本当に危ないです。問いを立てることが生命科学だと言ってもよいのに。
中村
今、国の科学技術の中で一番重視されている生命科学は社会からとても盛んだと思われていますけれど、本来の問いを立てるという点では曲がり角にあると思うのです。
廣川
研究の進め方に問題があります。基礎研究ではなく、創薬や診断法を開発するなど応用研究が重視されている。基礎科学の、知りたいという気持ちは根源的な本能ですし、文化の礎となります。基礎科学に対する姿勢で国の見識が問われるのです。 すぐに芽が出なくても、予想外の結果を基礎研究がもたらすこともあります。フレミングがカビの周りはバクテリアが生えないことをじっくり見ることで抗生物質を発見した。基礎研究の所産です。DNAの二重らせん構造は、ワトソン、クリックがとことん考えることを許された基礎研究の成果です。しかし、それがその後の応用研究の成因となった訳です。さまざまな例があります。
中村
DNAの場合、大きな可能性を持つことは明らかですが、方向性を見つめながら研究が進んでいるとは思えません。ちょうどワトソンやクリックが考えたように新しいことを求めて考える必要があるのにその時間がないのが現状です。今よりも貧しく手探りだった頃は暇も手伝ってか、よく問いを出し合ったものです。
廣川
時間と余裕をもった評価が必要でしょうね。追いかけられるように結果を出す状況では研究が細切れになります。それから自分達の独自性を常に意識して、人と違うことをやって、またそれが許される環境も大切です。もちろん、評価は厳しくする必要がありますが。
8. 体の分子生物学を目指して
中村
分子生物学の教科書として、ワトソンが書いたMolecular Biology of the Gene(遺伝子の分子生物学)があります。私たちはそれを勉強してきました。1989年にワトソンが若い仲間を集めてMolecular Biology of the Cell(細胞の分子生物学)という素晴らしい本を作り上げた。
廣川
もう、第4版が出ましたよね。
中村
つまり、今から20年前に基本は細胞であるという視点が出てきたと言うことです。それが重要と思い、若い方に読んでもらいたくて訳しました。第一版では、ついに細胞の時代になったと感慨深かったものです。中でも細胞骨格の章がとても面白かった。それまでの分子生物学には構造が大事だという発想がなかったのです。
廣川
それは細胞生物学の歴史そのもので、細胞骨格は随分遅くまで明らかになりませんでした。アクチン、中間径フィラメント、微小管は見えていても、それらを架橋するタンパク質やモーター分子は分かっていませんでしたから。
中村
繊毛の構造が原生生物からヒトまで共通だと書いてあり、精子とゾウリムシの泳ぎの共通性が見え、分子細胞生物学の世界が一気に広がりました。
廣川
細胞骨格には動きの概念が出てくるんですよ。
中村
形と動き。遺伝子の分子生物学にはなかった視点で面白かった。遺伝子、細胞と来たら次はやはり体。細胞の分子生物学は松原謙一先生と一緒に訳したのですが、次は『体の分子生物学』という教科書ができるのかなとか言っていました。まだまだ遠いかもしれませんが。
廣川
方法論としては強力なものが増えていますから、これからは我々の体のでき方と遺伝子がつながっていくのではないでしょうか。
中村
1989年の第一版では、細胞もすぐにわかる時代になったのだと書いているのですよ。ところが、2004年の第四版には、細胞がわかるには今世紀中かかるだろうって。
廣川
それはつまり、研究の細分化によって、細胞全体を俯瞰的に見ることがなかなか難しいということですね。
中村
 細部がわかってきたら難しさがはっきりしてきたということもあると思います。もっとも、教科書だから若い人達に向けて、いっぱいやることあるよと書いてあるのが面白い。
細部がわかってきたら難しさがはっきりしてきたということもあると思います。もっとも、教科書だから若い人達に向けて、いっぱいやることあるよと書いてあるのが面白い。
廣川
勇気づけられますね。確かに、画像や映像に写っているのに、私たちには理解できていないものがたくさんありますから。
中村
まだ理解しきれていないものの動きを観察し考えること、つまり「観る」ことを大事にして新しい展開をすることですね。今日はありがとうございました。
対談を終えて
廣川信隆
まずこの対談に先立って私の研究について長時間におよび辛抱強く話しをお聞き下さった事を感謝したい。テーマである“観る”は、実に意味の深い言葉であり中村先生の生命科学への深い洞察と造詣を感じた。先生とのお話のなかで幾つか大いに同感した点がある。まず第一は、生命現象の中の大きな“問い”のある研究の重要さである。研究の意義、深さ、そして拡がりは、どのような“問い”を持つかでほとんど決まると私は思っている。あとはその問いに解答を与えるべくあらゆる方法を駆使して努力するだけである。第二は、中村先生にとって生命科学は、ゲノムの分子生物学から始まり、細胞の分子生物学を経て体の分子生物学へと向かっているという方向性である。私の場合は、光学及び電子顕微鏡を用いた組織、細胞、細胞内小器官、細胞骨格までの観る世界から生化学・分子生物学そして分子遺伝学を用いた物質、遺伝子、機能の解析そしてビデオ顕微鏡、クライオ電顕、X線結晶解析、1分子生物物理学を用いた分子、原子レベルの動的構造解析へと発展して来た。出発点は異なるが分子遺伝学を通して遺伝子から個体そして行動まで一連のものとして観る事ができるようになったという終着点については同じである。分子を可視化できる電子顕微鏡写真の中に私の知りたいと思う、すべての細胞機能の根幹にあるダイナミックな細胞内の物質輸送の仕組みを担うすべての役者が見えている。モーター分子群を主役とし、レールの微小管、運ばれる多彩なカーゴそして輸送を制御する分子達。しかしまだ私たちの理解の及んでいない多くの役者が居るはずである。知れば知るほど新たな問いが生まれる。まさに“見れども観えず”。このダイナミックな現象のすべてを観てみたいと思うものである。
廣川信隆(ひろかわ・のぶたか)
1946年横須賀生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学の中井準之助東大名誉教授(故人)のもとで神経細胞の研究を始める。同学部助手を経て、79年から米国カリフォルニア大学およびワシントン大学に留学。81年ワシントン大学助教授、83年同準教授。83年より現職。日本学士院会員
対談の前に
中村桂子
裏話から始めよう。対談のお願いに、予定の3時間のうち1時間ほど仕事の話をしましょうと言って下さった廣川さん。特別講義が聞けるとは素晴らしい!ところが、1時間では止まらず、こちらも面白いのでつい聞き入って・・・。こうして残り時間はわずかとなり、実は対談のために再度、休日におじゃますることになった。生命誌研究館の少人数で伺うのはもったいないような密度の濃い、ダイナミックで熱のこもった講義は廣川さんそのもの。研究は研究者の人柄が反映されるという生命誌研究館の基本的な考えが証明された。内容の全てをお伝えしたい気持ちを抑えて要点だけをまとめておこう。
研究の発端は自ら開発した方法で急速凍結した神経細胞の電子顕微鏡観察。神経細胞では核のある細胞体から樹状突起と長い軸索が伸び、他の神経細胞や筋肉など他の細胞とつながっている。運動神経の場合、細胞体は脊髄にありそこから例えば手の指先まで軸索が伸び、そこの筋肉細胞と接続している。神経細胞でのタンパク質合成は細胞体でしかできないので、軸索を通って運ばなければならない。長さは1mを越えることもあるのに、タンパク質はどのように運ばれるのか。廣川さんの観察が見事な答えを出した。軸索内の微小管がレールの役目をし、その上を脚のついたモーター分子がさまざまなタンパク質だけでなく、ミトコンドリアまで運んでいる様子が顕微鏡写真で明らかになったのである(写真1)。実はこの写真、BRHの開館直後に行った「細胞展」で中心的な役割を果たした。モーター分子という考え方が普及した今では私たちにも「脚」が見えるけど、これを「脚」と直観したのはそれまでの長い観察あってのことである。最初発見したのは2本脚だが、1本脚のものも。すぐに10個のモーター分子を発見した。その後、遺伝子を解析し、モーター分子群キネシンスーパーファミリータンパク質(KIFs)として45種類の遺伝子を明らかに。ミトコンドリアを運ぶもの、シナプス小胞の材料を運ぶもの、受容体を運ぶものなど、それぞれのモーター分子の役割をも明らかにしていった。ひとつひとつの分子の立体構造も解き、分子としてのはたらきかたを解明していくと同時に各遺伝子のノックアウト(それぞれの遺伝子がはたらかないようにする)マウスをつくり、個体の中でのはたらきも見た。感心するのは、顕微鏡で観るから始まり、遺伝子、タンパク質構造、個体の発生と、現在使用できる生物学の技術は全てを駆使して神経細胞のはたらきの全体像を観るという研究姿勢。モーター分子という切り口と技術は何でも使うという方法で「はたらき」を知るのである。
たくさんのKIFsの話の中から一つ、KIF17について高校生に話をした時のエピソードを紹介しておこう。このモーター分子は樹状突起の中にあり、NMDA型グルタミン酸受容体を含む小胞を運ぶことがわかった。この受容体は記憶・学習に関わることが知られているので、早速KIF17を過剰発現するマウスをつくったら、確かに記憶力が向上していた。そこで高校生がKIF17を過剰発現するにはどうしたらよいか、熱心に聞いてきたそうだ。「訓練、訓練。勉強すれば増えるよ。」と答えたと笑う廣川さん。後ほど対談で紹介する体の左右の決定へと思いがけない展開をしたモーター分子研究はまた次の思いがけなさを抱いているような気がする。

(写真1)電子顕微鏡で捉えた細胞内の瞬間
(Hirokawa N. : Science 1998より)
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)
.jpg)
.jpg)











