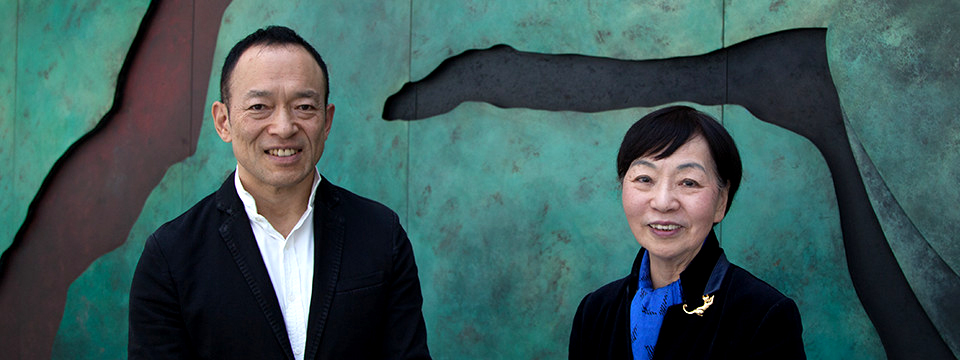
TALK
やわらかに和して同ぜず
1.調和の世界を築きあげる
中村
先日、選句について、俳句は読むものでなく、パッと見た文字の印象でわかるので六千句を二時間で見ると書かれていてちょっとびっくり。
長谷川
その印象が本当に大事なんです。
中村
漢字仮名まじりのおかげもありますでしょう。斜め読みもできる。これって大発明だと思うのです。
長谷川
その通りです。仮名はどのように生まれたのかと考えると、例えば「まつ」という掛詞は、松の木とも、あなたを待つともなります。歌は、私たちの祖先にとって文字さえ変えてしまうほどに大事なものだったのだろうと思います。大和言葉は本来、文字はありませんでしたから、変幻自在にアルファベットまで受容して豊かですよ。
中村
『和の思想』(註1)で、異質なものを受容しそれを変化させていく日本文化の力を語っていらっしゃいますが、言葉がまさにそれですね。
長谷川
いつの間にか今日の本題に入っていました(笑)。
中村
毎年、動詞を一つ選んで「生きる」を考えています。息をして、食べて、歩いて、話をして…という具体から「生きる」を考えようという気持ちです。昨年は「ゆらぐ」でした。
長谷川
漢字は瞬時に意味を想起でき便利ですが、仮名はその意味を考える人の気持ちのやわらかさが伝わりますね。とくに元にかえって物事をやわらかに考えるには動詞がよいですね。僕もできるだけ漢字を使わずに動詞を書こうと思っています。

中村
毎年、皆で翌年の動詞について話し合います。ところが今年は、私が、今の社会の動きを考えて、どうしても「和」の一字から離れられないのです。動詞なら、なごむ、やわらぐ、あえるですが、そのどれか一つにはどうしても絞れず、三つを行き来してあれこれ考えたい。とくに「和える」にこだわっています。
長谷川
印象としては、お料理の言葉ですね。
中村
ええ。例えば、白和えは、ほうれん草や蒟蒻や椎茸などを胡麻とお豆腐で和えます。白和えをいただく時、お豆腐の味、ほうれん草の味、椎茸の味…それぞれを味わいながらも一体となっていますね。
一方、サラダはいろいろな野菜をドレッシングで馴染ませたものですが、サラダをいただく時、トマトはトマト、キュウリはキュウリとして味わいませんか。和えものには素材の味があり、かつ素材の混ざり合った味わいがある。食べるという日常に見られるこのことが私には、長谷川さんの『和の思想』そのものに思えるのです。
長谷川
僕が書いた以上のことを読んでいただけてとても嬉しいです。「和」は中国語の字です。もともと大和言葉で、あえる、なごむ、やわらぐと考えていたところに中国から来た「和」という字をあて、「和する」という新たな動詞も作られたわけです。
中村
気がつきませんでした。その通り、和するという動詞がありますね。
長谷川
ええ。日本で作られた動詞です。でも「あえる」は、とくに日本文化の基層を表す言葉ではないでしょうか。 “A”と“B”を和えると一足す一が二以上のものになり、プラス“α”が生じるという風に。まさに「個々の姿を保ちながら調和の世界を築きあげる。」これを人間の社会・歴史で考えたら面白いでしょうね。
註1:『和の思想 異質のものを共存させる力』
長谷川櫂著。中公新書(2009年)。
2.古池や蛙飛びこむ水のおと

中村
仕事柄、毎日、生きものを見ていますが、よく機械との違いを考えます。例えば、私たちの細胞の中には生命現象の基本となるDNAが入っています。一個の細胞に入ったDNAの全体をゲノムと呼びますが、これが面白いのは、例えば、長谷川さんの細胞の中から取り出したゲノムは“A”,“T”,“G”,“C”の四種類のDNAが32億個並んだもので、その並びに固有の意味があるわけです。そして、これがすべてで、これ以上は長谷川さんから出てこない。
長谷川
ああ、そうなんですか。
中村
自然界に「これがすべて」と言えるものってなかなかありません。例えば虫を100万、200万どこまで探してもこれでお終いとはならない。まだどこかに何かが。
長谷川
新種がいるかもしれませんね。
中村
ええ。お星様もそう。ところがゲノムはこれがすべてと言える。これ、面白くありませんか?
長谷川
ちょっと寂しい感じもしますが。
中村
なるほど。でも私はこれを見て寂しいと思わないのは、全部をわかりながらここから無限の可能性を引き出せるから。全部と無限をいっぺんに考えられるなんて人間がなにかを考えるうえで幸せじゃありませんか。

長谷川
確かに日本語も五十音しかありませんが、そのうちの十七音の組み合わせだけでも膨大な数になり、しかも実際には、更にその限界を超える多様な俳句ができるのです。
中村
そこでは、切れ字や間も大事なのですね。
長谷川
ええ。例えば、松尾芭蕉(註2)の句、「古池や蛙飛こむ水のおと」は、「古池や」とつぶやいて、しばらく黙った後「蛙飛こむ水のおと」と読めば、この句の言わんとするところがわかる。
中村
古池「に」でなく「や」によって間が生まれる。間は、空間でも、時間でもありますね。
長谷川
私たちの文化は直感的に、調和させる空白を大事にしてきました。間は日本人にはすぐわかるのですが、外国人に説明するのは難しい。必要なものだけで埋め尽くして完成させたものは後に発展する余地がありません。俳句に限らず、一見不必要なものや、役に立たないと思われるものを残しておくところから後の展開が生まれるということはよくあることです。
中村
DNAは解読が始まった頃、タンパク質を作る命令を記した集まりだろうと思われていました。ところがそれは全体のわずか1.5パーセントという結果で皆驚きました。でも調べていくと、そこにこそ柔軟な対応のできる生きものの面白さがあるのです。間を感じることは、生きていることを感じることと重なります。
長谷川
合理性だけでものごとを突き詰めるとぎくしゃくしてくるもので、むだはとても大事です。
中村
私たちはそのことを知っているはずなのに、無用だけではいけないように思い、無用の用と言います。でも本当の無用もあってよいという気持ちを持てるのが生きもの研究の面白さの一つです。

長谷川
俳句には無用の季語がたくさんありますよ。昼寝は夏の季語で、昼寝する人は純粋に昼寝を楽しんでいるのです。
中村
明日の鋭気を養うために昼寝するなんて言ったら俳句にはなりませんね。
長谷川
寝正月という季語もお正月をぐうたら過ごすことですが、まさに無用の介であるところに面白さがあると思うんですね。
中村
俳句には無用がたくさん入っていますね。
長谷川
民話にもものぐさ太郎やわらしべ長者がいるけれど、出世したり長者にならず、ずっとものぐさのままでいる無用の介を、私たちの文化は一つの理想として思い描いてきましたね。中世の西行(註3)のような世捨て人は、出世やお金儲けの為でなく、なんの役にも立たぬ歌をただ作りたくて僧侶という姿を借りてのんびりした生活に入った、これが出家の実態でした。そんな果報者によってなりたっているのが日本の詩歌です。億万長者に出世してということでなく、ただ何も持たずに満ち足りる価値観ですね。
中村
俳句や詩歌に表れる理想を実現するような、ゆとりある社会でありたいですね。『方丈記』(註4)なんて、まさに方丈で、縁側があり琵琶を置く場所があれば足りるという感じで、すぐに引越せる。いいですね。
註2:松尾芭蕉【まつお・ばしょう】[1644-1694]
江戸前期の俳人。名は宗房。主な日記、紀行に『更科紀行』『奥の細道』『嵯峨日記』ほか。
註3:西行【さいぎょう】[1118-1190]
平安末・鎌倉初期の歌僧。俗名、佐藤義清。松尾芭蕉らに影響を与えた。『新古今和歌集』に94首がおさめられている。
註4:『方丈記』【ほうじょうき】
鎌倉時代初期の随筆。鴨長明著。
3.降る雪や明治は遠くなりにけり
中村
俳句の約束事と言えば、やはり季語ですね。
長谷川
俳句になぜ季語を入れるかと言えば、地球は軸が傾いたまま太陽の周りをグルグル回っていて、その微妙に傾いたところが大事だからです。
中村
突然、地球の傾きですか。上手に傾いていますよね。
長谷川
ええ。地球の無用のしぐさから春夏秋冬が生まれる。季語には、十七音に微妙に変化する宇宙の構造を刻み、俳句に宇宙的な広がりを反映するはたらきがあると思います。
中村
なるほど。季語は宇宙を捉えているということですね。
長谷川
ええ。例えば、中村草田男(註5)の句「降る雪や明治は遠くなりにけり」を見ると、明治でも昭和でもいい。ただ、「降る雪や」を持ってくることで、一面の降りしきる雪が宇宙的な広がりを物語る情景として句に刻まれます。
中村
確かに。最近気になるのは、旧来の季語と、今、温暖化で少し亜熱帯化している日々の感覚とのずれに困ることはありませんか。

長谷川
現代人は、春と聞けば、三月、四月、五月を思い浮かべますが、旧暦では二月、三月、四月が春です。もともと古代中国から伝わった二十四節気(註6)と日本の四季との間にずれがありました。
中村
むしろそのずれを楽しんでいるところがあるのですね。
長谷川
ずれを取り込んで豊かな季節感を持つようになったのだと思います。立秋は八月初めですが、例えば、『古今和歌集』(註7)にある「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」という歌で、作者の藤原敏行は暑いさかりに秋の気配を探ろうとしています。寒いさなかには春の気配を探り、初鰹や初物の空豆を喜ぶ習慣は季節を探る気持ちの表れですね。
中村
確かに先取りの感覚っていいですよね。俳句はダメの私もそれは持っています。例えば緑で言えば、二月から三月頃にかけて、本当に寒いのに電車の窓から見える土手の雑草たちがかすかに緑色になっている。あの感じが大好きです。

長谷川
春浅いころの緑ですね。それを俳句で下萌えと呼びます。冬のうちにそうなることもあり、それは冬萌えと呼びます。微妙な自然を捉える言葉は俳句にはたくさんあります。
中村
二月でまだ寒いのに、ああ、もうすぐ春だなあって感じるときの先取り感覚は、日本の風土で感じる独特の心の動きなのでしょうか。
註5:中村草田男【なかむら・くさたお】[1901-1983 ]
中国福建省生まれ。俳人。本名、清一郎。ホトトギス同人。『万緑』を創刊、主宰。句集に『火の島』『万緑』『銀河依然』ほか。
註6:二十四節気【にじゅうしせっき】
太陽年を太陽の黄経に従って二四等分して、季節を示すのに用いる語。
註7:『古今和歌集』【こきんわかしゅう】
醍醐天皇の下命により、紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑が撰し、905年または914年頃成る。勅撰和歌集の始まり。
4.間をわかる外国の人は増えている
中村
今、世界中で俳句が流行っていますね。どうしてですか。
長谷川
俳句は、既に19世紀からヨーロッパやアメリカに入っています。やはりその短かさが受け入れられた理由の一つだと思います。もともとキリスト教文化圏の詩人は、キリスト教の預言者が変形したものなのです。未来を予測するのではなく、神の言葉を聞き取れない人々に向けて、自分だけが預かった神の言葉を伝える人です。それで詩歌はダンテの『神曲』のように長大な言葉になる。

中村
確かに長いです。
長谷川
西洋では、誰もが詩を詠めるわけではなくて、神と対話できる能力を持った特別な人、即ち天才が作るものなのです。ところが俳句は、普通の人でも、しかも複数の人々が集まって作ることもある。俳句は、まるで言葉のかけらのように短いですから、西洋の人にはかなり新鮮に映るようです。それで、向こうでも広がりを見せ、今や世界中で詠まれるようになりました。日本語で作る人も、母国語で作る人もいて、外国の俳句は必ずしも季節の言葉はなくても成り立つことになっています。
中村
短く表現できればよい。
長谷川
ええ。面白いことに短い言葉で表現すると、英語で詠もうとフランス語で詠もうと、間が生じてくる。それまで言葉で埋め尽くしていたところに空白にゆだねなくてはならない部分が生じてくるのです。すると彼らも、間のはたらきというものに気づく。あることを言って、一行を空けて、別の何かを言うことで一つの世界が完成する。そんな優れた俳句が海外にもたくさんあります。句会では皆で持ち寄った中からよい句を選ぶ、自分とは異なる他人の良さを見つけることが俳句の面白さであるというところも共通です。
中村
自ずと間のわかる外国の人が増えるのはよいことですね。しかも理屈でなく、俳句を作っていくうちにわかるというところに意味を感じます。実はアメリカ人の好むディベートが嫌いなのです。言葉を、相手を倒すために使う。
長谷川
僕も嫌いです。俳句はそれと最も遠いところにあるものです。海外で生け花を教えている友人が、一つの枝を挿すことで全体をいかす生け花と、空間を花で埋めるフラワーアレンジメントとの違いをよく生徒に言うそうです。生け花は、全体の空間を生かし、和ませることが大事なのですね。

中村
一輪挿しも日本ではよく見かけますが、これも周りも含めてですね。和える、和む、和らぐ、と考えていくことはこれからの社会に向けてとても意味のあることだと思えてきました。それには、お説教していてもダメで、俳句や生け花という具体を通して間を世界に広めていけばよい。きっと平和にもつながる大事なお役目ですね。
長谷川
僕はそこまでの使命感を持てていませんが、日本人がそこに気づいていないということは問題ですね。「和」と言えば、調和を乱さずボスの意見に従うことと思う人が大多数でしょう。けれどもそれは違います。和えもののように、それぞれに意見があり、それが調和していくのが和の世界です。気づいて欲しいですね。
5.私たちの詩歌は櫂を漕ぐ舟唄から
中村
日本の歌は和歌が発祥で、それが連句へ移りその発句が俳句に分かれたと聞きますが、連句にしても、和歌にしても、一人で詠むのでなく皆で作るというところが面白いなあって思います。

長谷川
ええ。通説では、和歌から連歌が生まれて連句になり、発句が独立して俳句が生まれたと言われています。けれども起源はもっと古いのです。『古事記』(註8)に、イザナギノミコトとイザナミノミコトが出会う場面がありますね。「なんてすてきな方なのかしら」とイザナミが語りかけ、「なんてすてきな女性なんだ」とイザナギが答える。この対話が始まりで、もともと人と人とが掛け合わせる問答なのです。
和歌も連歌もこの問答が起こりです。連歌については、『古事記』の別の箇所を発祥とする考えもあります。征伐にやらされたヤマトタケルノミコトが、ため息交じりに「私は何日、旅をしているのだろう」と言うと、付き人のオホタキノオキナ、火を守る翁が、「もう九夜十日過ぎました」と答える場面です。筑波山での問答であったことに因み、連歌のことをツクバネノミチと呼んだ時代もあるくらいです。
いずれにしても、日本の詩歌は『古事記』の世界から続いており、もともと一人が詠むものでなく、複数人の問答として発祥したものと考えられており、自ずと何人かで歌仙や連句を巻いたりすることになる。問答ですから、相手が言うことに対して、プラス“α”で答えるという形がもう古代にある。そこから間が生まれたと考えたほうがよいですね。
中村
なんて面白いお話でしょう。ソクラテスも孔子も、問答が文化や学問の発祥にあって、ほかの国では、それが哲学や思想のような難しいものになっていきましたね。同じ問答に発祥しながら、そこにちょっと楽しみも入れて、文芸という形になってきたというところが面白いですね。難しいより楽しいが好きな者としては日本人いいなと思います。
長谷川
これは僕の考えですが、日本は島国ですから、昔、人々は舟で海を渡ってきたわけですね。きっと何年もかかったでしょう。誰かが艪や櫂を漕ぐと、別の誰かがそれに合いの手を打つ。長い旅のあいだに、たくさんの舟唄が生まれたでしょう。そこが僕らの詩歌の起源ではないかと思うのです。舟を漕ぐときのかけ声と唄との問答が、日本人の奥深くにずっと流れているんじゃないかと思うのです。
和歌も多くは男女のあいだの相聞歌という形で、これも問答として詠まれますね。

中村
『源氏物語』はまさにそうで、やりとりはみんな歌ですよね。
長谷川
ええ。誰か相手に問いかけ、向こうが答える。例えば、西行が詠んだ桜の歌のように単独で詠む場合でも、単にひとりで詠むのではなくて、桜の精霊に呼びかけているわけです。
中村
問答の世界は、神様に呼びかけるというところまで含めての広がりがあるわけですね。
註8:『古事記』【こじき】
現存する日本最古の歴史書。稗田阿礼が天武天皇の勅により誦習した帝紀および先代の旧辞を、太安万侶が元明天皇の勅により撰録して712年献上。
6.風鈴のような知恵を
長谷川
歌仙を、僕はオーケストラに喩えるのですが、その指揮者にあたる役割を捌き手と呼びます。歌仙は三十六句を何人で詠むとしても、発句に対して次の句をどう付けるか、三百六十度どの方角へどれだけ離すかを采配し、全体をとり仕切る捌き手には、間の専門家であることが求められます。その歌仙のすべてを担う中心人物で、実は、芭蕉は優れた捌き手でした。
中村
すると、芭蕉が捌いた歌仙は、誰が詠んだ句も、三十六句すべてが芭蕉の作品とも言えるわけですか。
長谷川
そうです。それぞれの楽器奏者にあたる人を連衆と呼びますが、連衆に詠ませた歌仙の全体は芭蕉がつくったものです。捌き手が変わればまったくの別ものになるでしょう。

中村
そういう面白さがあるのですね。一人ひとりが順番に詠んでいるように見えて、実は、常に皆で合奏しているようなものですね。合奏だけれど、ちょっとここは間を置いてなどと一人ひとりが自分らしさを出している。よその国でそういう文芸ってあまり聞きませんね。
長谷川
なんと言うか、日本は文芸もやはり共同作業なんです。お互いに添削し合ったりもしましたし、いわゆる所有権、著作権もはっきりしていませんでしたからね。ところが西欧の詩歌は、天才が一人で作るわけですから、例えば、リルケの詩を誰かが添削するなんてあり得ません。
中村
それはそうですね。今のお話は、21世紀を考える時とても大事ですね。今、グローバル化という言葉がよく使われますが、なぜか世界をアメリカ型社会に均一化するという意味で使われていませんか。多種多様な自然の中に多種多様な生きものがいて、その一つである人間が自然との関わりの中で文化をつくってきた。それがグローバルの意味だと思うのです。多種多様な生きものが地球上に38億年も続いてきたのは、それぞれが独自な存在でありながらもある調和があったからです。本来のグローバル化って「和える」につながるものだと思うんです。
長谷川
僕もそのとおりだと思います。地球上にいろいろな文化があって、民族が、多様な人々がいるというところを認めて、それぞれの人が生きやすい社会にすることですね。
中村
我田引水ですが、生きものの研究、そして日本文化から、世界に提案できることがたくさんあると思っているのです。日本はもっと上手にそれができるようになるといいのになあ。
長谷川
僕たちの中にある「和」の心、違う者同士が共存できる世界というメッセージは世界全体にプラスにはたらくはずですね。

中村
正倉院の収蔵品をデータベース化している方のご本がとても面白かったんです。私たちの祖先は、海外からなんでも取り入れて、しかもそれを工夫して洗練させたうえで、見事な日常品として使っていたわけです。しかもその千年も前の実物が、今も正倉院にあるということが素晴らしい。そういう知恵が私たち自身の中にあるということを、皆もっと意識して、自信を持っていいんじゃないかって思います。
長谷川
僕も機会があって正倉院展を拝見しました。ペルシャやインドや本当に多様な国のものがあって、奈良時代の日本があれほど国際的だったことに驚きました。
中村
ほんと。開かれていますよね。
長谷川
もともと日本という国はとても開かれていた、私たちは、もう一回、あの時代に学んだほうがいいですね。それを痛切に感じました。
中村
しかも、まねじゃないわけですよね。自分たちの風土に合うように洗練させて使っていくところがいいなと思って。
長谷川
東大寺など大きなお寺では、風鐸が屋根の四隅にぶら下がっていて、風が吹くとカランカランと鳴ります。これは仏敵を驚かす魔除けだそうですが日本に入ったのち、涼を楽しむ風鈴として日本中に広がっていった。
中村
庶民が楽しむわけですね。風鈴のような知恵を日常にもっと生かしていきたいですね。今日は「和する」という言葉を伺って、これを知っていたら今年はこれにしたかもしれないと思っているのです。「和える」「和む」「和らぐ」に比べて日常あまり使いませんが、和の本質を考えさせられます。
長谷川
それぞれの意見や立場の違いを認めながら、そこから新しいものを見いだしていくということが「和」の心です。「同じて和せず」ではなく、「和して同ぜず」ということです。調和を、お互いの意見を認めるけれども、安易には同化しない。どっしり構えているという感じです。
中村
「和して同ぜず」こそ、本来の「和」なのですね。

写真:大西成明
対談を終えて
中村 桂子
言葉への感性と時代認識がみごとに絡み合って生れた『和の思想』がきっかけでした。谷崎の『陰翳礼賛』に匹敵する戦後文献は日本国憲法とおっしゃるセンス。沖縄や東日本大震災にも向き合う俳句を核にして広がる世界に魅了されたすばらしい時間でした。異質なものを受容してより楽しいものにしていく「和」を、世界のものにしたいという気持がより強くなりました。「百合滅び白き百合根も滅びけり」(沖縄)を心に止めて。
長谷川 櫂
お互いに相手の話に触発されて、新しい視野が広がる。中村桂子さんとお会いするのははじめてだったが、1時間30分の対談はまさにそんな時間だった。自分のことを棚に上げていえば、やわらかな心の持ち主だからこそできることだろうと思った。今年の年間テーマは「和」とうかがった。しっかりした自分の世界があり、そのうえで自分と異なる考えの人も受け入れることができる。多難な地球を救えるのは、このやわらかな和の心しかないと思った。

長谷川 櫂(はせがわ かい)
1954年熊本県生まれ。東京大学法学部卒業。読 売新聞記者を経て、俳句に専念。「朝日俳壇」選者。俳句結社「古志」前主宰、東海大学特任教授。『俳句の宇宙』で第十二回サントリー学芸賞受賞。句集『虚 空』で第五十四回読売文学賞受賞。句集以外に『「奥の細道」をよむ』『和の思想』『文学部で読む日本国憲法』ほか著書多数。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)














