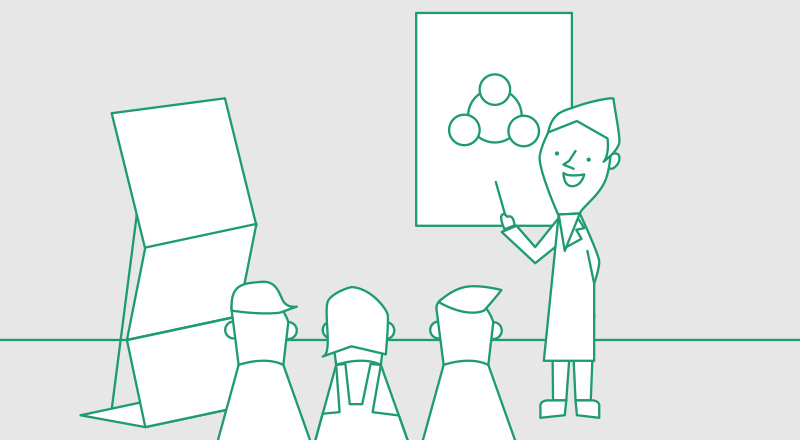RESEARCH
生きた膜を支える脂質の分子運動
細胞膜をつくっているのは、二層に集合した無数の脂質分子。その集団としての挙動に注目すると、細胞の増殖や死、さらに個体の行動まで、階層を貫く重要な役割が見えてきました。
1.細胞膜を動く脂質分子
1972年にシンガーとニコルソンが発表した生体膜の流動モザイクモデル(註1)は、それまでの細胞膜の静的なイメージを一新した。そのモデルは、細胞の内と外を隔てているだけと思われてきた膜が、実は脂質分子が集合した非常にやわらかい二分子膜構造であり、膜を構成する脂質分子は活発に動き回っているというものであった。そこで、脂質二分子膜内に浮かぶように存在しているタンパク質などの機能分子が、流動的な膜の中でどのようにはたらき、制御されているかを解明することが膜の理解につながるとして活発に進められてきた。
ところが、膜を構成する主要物質である脂質分子については、生体膜内を流動はするものの、特に生理機能は持たないという見方が続いていた。確かに脂質は、酵素などと異なり、分子一つで特定のはたらきを担うことはほとんどない。しかしこれだけの流動性が機能につながらないはずはないと考え、脂質分子の集団としての挙動に着目した。すると膜の流動性は巧みに制御されており、それが細胞分裂から個体の行動までの様々な階層での機能に関わっていることがわかってきた。
2.生体膜の非対称性
細胞膜の物理的な性質は膜を構成する脂質分子そのものに由来し、細胞から脂質を抽出して溶液に懸濁すると、生体膜と同じ脂質二分子膜構造が形成される。しかし、このようにして出来た人工膜は生きた細胞の膜と決定的に違う。生体膜では脂質分子の分布が非対称なのである。人工膜では脂質は二分子膜の内外でほぼ均一に分散しているのに対し、生体膜では内層と外層は種類の異なる脂質でできているのだ(図1)。このような非対称性はバクテリアから動植物に至るすべての細胞で普遍的に見られ、この構造を維持しているのが、脂質二分子膜の内外を脂質分子が横切って移動するとんぼ返り運動(フリップ・フロップ)なのである。生体膜中にはエネルギーを使ってフリップ・フロップを促進するタンパク質が存在し、特定の脂質を特定の方向に積極的に輸送している。このような脂質の非対称性は細胞が死ぬと解消する。細胞は、なぜわざわざエネルギーを使って脂質分子をとんぼ返りさせているのだろう。
生きた細胞で特定の脂質分子の動きや分布を検出することが難しいこともあって、細胞膜を構成する主要な脂質分子はこれまで厳密な観察の対象となってこなかった。我々はまず検出法を工夫した。ありふれた脂質の一つであるホスファチジルエタノールアミン(PE;註2)に特異的に結合する分子(プローブ;註3)を開発し、細胞膜上におけるPEの挙動を詳細に解析できるようにしたのである。その結果、PEのフリップ・フロップが、細胞の増殖や死に重要な役割を果たしているという思いがけない成果が得られた。

(図1) 細胞膜の構造と脂質の分布の非対称性
細胞膜を構成する主要な脂質であるホスファチジルエタノールアミン(PE)は、フリッパーゼのはたらきにより細胞質側に運ばれ、内層で拡散していく。このため、PEは外層にはほとんど見られず、内層に万遍なく存在する。
3.細胞活動を制御するフリップ・フロップ
細胞分裂は、あらゆる生物の増殖を支える最も基本的な生命現象である。細胞質が分裂する際には、アクチンとミオシンを主成分とするリング状の構造(収縮環;註4)が形成され、その収縮によって細胞膜のくびれ(分裂溝)が生じ、細胞が二分されるという様子が観察できる(図2左)。そこで、分裂の原動力は収縮環による細胞膜の収縮、あるいは娘細胞が反対方向に離される物理的な力によるものであって、細胞を包む膜系はその動きに従って受動的に動いていると考えられてきた。しかし我々の観察で、細胞膜に存在するPEの集団としての挙動が、分裂の進行に積極的に関与していることが見えてきた。

(図2) 分裂中の細胞に見られる脂質の局在と収縮環の関係
分裂期の細胞の分裂溝(左)。この時期の細胞膜外層の脂質分布をPE結合プローブ(緑)で観察すると、PEが分裂溝で特異的に存在していた(中)。また分裂溝付近の細胞質では、収縮環の主成分であるアクチン繊維(赤)が集積していた(右)。
通常の細胞膜では、PEはフリップ・フロップの結果、細胞膜の内側に多く細胞外層にはほとんど分布していない。ところが、PE結合プローブに蛍光物質で目印をつけ、細胞分裂終期におけるPEの分布の時間変化を観察したところ、PEが一過的に分裂溝の膜の表面(外層)に出ていることがわかった(図2中)。通常とは逆向きのフリップ・フロップが起きているのである。表面に出たPEはもう一度フリップ・フロップすることで内層に戻るのだが、細胞培養液にプローブを加えたままにしておいたところ、プローブが結合したPEは内側に戻れなくなった。この細胞は、2つの娘細胞がひも状の細胞間ブリッジで結ばれた状態で分裂が停止し、本来は役目を終えるはずの収縮環が消えずに残っていた(図3)。

(図3) プローブ添加によりPEの動きを止めた細胞
分裂中の細胞にプローブを添加したままにすると、娘細胞がブリッジされた状態(矢印)で分裂が異常に停止する。このときPEは2つの細胞をつなぐ膜の表面に出ており(緑)、収縮環の主成分であるアクチン繊維が分解されずに残っていた(赤)
この実験から、生理的機能がないと思われてきたPEのはたらきが見えてきた(図4)。分裂溝では活発なフリップ・フロップによってPEが表面に移行するのである。しかもこの時は、周辺の領域と脂質分子の往来は低下している。その結果分裂溝近くには、他と脂質組成の異なる特異な領域が生じることになる。このPEの分布の変化が適切に起きると、分裂溝にさまざまなタンパク質が集積し、収縮環のアクチン繊維の分解の合図となるのである。PEの分子集団としての動きの制御が、分裂という細胞の基本活動を進める役割をしているのである。これは予想外のことであり、新鮮な驚きであった。

(図4) 脂質の分子運動が関わる細胞分裂の制御
分裂溝では通常と異なるフリップ・フロップにより、PEが内層から外層へ動く。さらにここでは、周辺の領域との脂質分子の自由な往来が抑制されており、外層のPEは拡散せず、内層には膜タンパク質が集積し収縮環の分解を制御する。
なおPEの分布の変化は、分裂時以外にも細胞の運動や細胞死(アポトーシス)などで観察される。たとえばアポトーシスの過程で外層に現れるPEは、食細胞が死につつある細胞を食べる目印となっている(図5)。PEのフリップ・フロップを促進するタンパク質であるリン脂質フリッパーゼを同定することに成功したので、PEのフリップ・フロップの制御が細胞の分裂や運動にどのように関わっているかが明らかになりつつある。

(図5) アポトーシスを起こす細胞でのホスファチジルエタノールアミンの分布
ヒトの培養細胞でアポトーシスを誘導し、PEの分布を観察した。観察視野内には2個の細胞があるが(左)、アポトーシスの特徴である大きな小胞を持つ細胞(矢印)でのみ、細胞表層でのPEの分布が観察された。
4.脂質の分子運動の恒常性
フリッパーゼによって制御されるフリップ・フロップに対して、脂質分子の同一膜内での水平方向の動きは拡散によって速やかにおこり、例えば、直径約8.5μmの赤血球の端から端までを数秒で移動できる。このような流動性を規定する最大の要因は温度であり、生物は環境温の変動にかかわらず膜のダイナミズムを一定に保つ仕組みを進化させてきた。例えば多くの変温動物では、温度が変化すると脂質分子の化学構造を変えることが知られている。脂質分子の拡散のしやすさは「足」のように見える脂肪酸鎖(註5)の形状で決まるが、一般に脂質の分子運動が低下する低温環境下では、拡散しやすい脂質分子の割合を増やし、脂質の分子運動を一定に保とうとする。逆に高温環境下では、拡散しにくい脂質分子を増やして分子運動を抑制する。
このような温度に対する膜脂質の適応を恒流動性適応(註6)と呼ぶ。とはいえ、あまりにも急激な温度変化が起き膜脂質の構造変化が間に合わないこともあり、その場合には、動物、植物を問わず細胞機能に障害が生じ、個体の死に至る。環境温の変化が生物種の存亡を左右する要素の一つであるのはこのためだ。したがって大きな環境温の変化を生物が克服するには、恒流動性適応と合わせて、体温を一定に保つ仕組みも必要となる。体温と膜脂質のダイナミズムは、どちらが主でどちらが従という単純な関係ではなく、お互いが深く関わりあった現象であることが、この研究から見えてきた。
5.膜脂質と体温
生物は、環境温の変化を感知して、体内の温度環境を一定に保つ巧妙なシステムをもつ。平均体温は種によって異なり、あるいは同一種内でも個体差が見られることが多いが、そもそもある生物にとっての至適な体温はどのようなメカニズムで決まっているのだろうか。また、今の温度が自分に合っているかどうかをどうやって判断しているのだろう。体温には大きな謎がある。
一方、先述したように、低温環境に適応した生物では、膜を拡散しやすい脂質分子で構成する恒流動性適応が観察される。これは個体の至適体温を低温側にシフトし、同時に過度の流動性を防ぐため高温を避けるという性質をもたらす。そこで、膜脂質が温度受容に重要な役割を果たしている可能性が古くから指摘されてきた。もしこれが本当なら、膜脂質の組成を人工的に変化させることで、動物の体温調節に影響を与えることができるのではないだろうかと考え、検討を始めた。
実験材料としてショウジョウバエを選び、幼虫の温度選択行動を定量的に測定する装置を開発した(図6)。ショウジョウバエの幼虫は、自分が育った生育温度を好む温度選択性を示すことが知られており、実験室で通常用いられる25℃で育った幼虫は、低温から高温の温度勾配のある飼育器に移すと25℃付近の場所に移動する。そこで、生育温度は同じ25℃にしながら、特定の脂質を添加したエサを食べさせて細胞膜の成分を偏らせた個体をつくり、その選択温度を検討した。例えば低温での恒流動性適応に必要な脂質の原料であるリノール酸(註7)ばかりを与えた幼虫は、通常のエサで飼育した場合より選択温度が2℃ほど低温側にシフトした。細胞膜中のリノール酸成分が増えたことによって至適体温が変化し、暑がりのハエになったのである。

(図6) ショウジョウバエの温度選択行動の定量と変異体の同定
12℃から35℃までの温度勾配が設定できる培養器(上)。ここにショウジョウバエの3齢幼虫を置き、20分後の移動分布を観察する。この実験系を用いて温度選択行動の変異体を得ることに成功した。野生型のハエは25℃付近に移動するが(中)、膜タンパク質の変異により脂質の流動性が高まったatsugari 変異体は、18℃の選択性と低温耐性の2つを獲得していた(下)。
従来、変温動物は環境温の変動に応じて体温が大きく変化することから、哺乳動物のような精密な体温調節機構を備えていないと考えられてきた。今回の観察は、ショウジョウバエ幼虫は何らかのかたちで細胞膜の状態を感知して、それに相応しい環境温度を選ぶ緻密な体温のコントロールをしていることを示唆している。
6.脂質から見た生物の階層性
我々はさらに温度受容のメカニズムを明らかにするため、温度選択行動に異常を来したショウジョウバエ変異体を同定した。その一つatsugari変異体は、生育温度に関わらず18℃の低温域を選択し、エネルギー代謝率が標準個体の約2倍になっていた。これは変温動物においても代謝反応による熱が体温調節に関わる可能性を示す意味で非常に興味深い。一方この変異体の細胞膜に注目すると、原因遺伝子である膜タンパク質ジストログリカン(註8)の発現低下により膜の流動性が著しく亢進しており、結果的に低温での恒流動性適応が実現されていた。一つの遺伝子の変異によって体温調節行動と温度耐性という二つの異なる形質の変化が引き起こされたことは興味深い。生物進化の過程で、膜の性質を変えるというミクロな変化が、多様な温度環境下での生存や分布域の拡大というマクロな行動に影響を及ぼしてきたことが十分に予想される。
我々は、細胞膜という限られた場所をめぐっている脂質の分子運動に興味を持って研究を進めたところ、膜を構成する脂質分子の集団としての動きが、分子、細胞、個体、生態系という様々な階層で重要な役割を果たす可能性が浮かび上がってきた。博物学者の南方熊楠は、複雑な因果関係の中で、必然と偶然が最も多く通過する一つの点をマンダラの萃点(すいてん)と表現した。生物進化における萃点は脂質なのだろうか、あるいは脂質の分子運動を制御する他の分子なのだろうか? 萃点にたどりつく日を夢見ながら研究を続けている。
梅田真郷(うめだ・まさと)
1983年東京大学薬学系大学院博士課程修了。薬学博士。東京大学薬学部衛生裁判化学教室助手、東京都医学研究機構、東京都臨床医学総合研究所を経て、2003年より京都大学化学研究所複合基盤化学研究系超分子生物学教授。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)