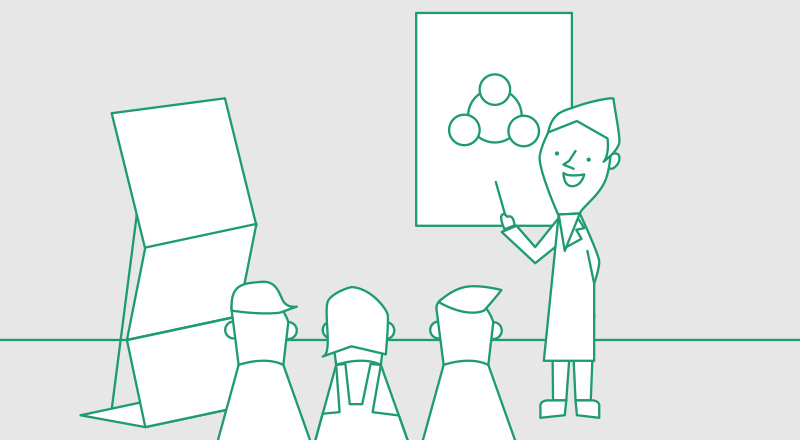風土に染まる蟲と言葉
ファーブル昆虫館館長奥本大三郎

JT生命誌研究館館長永田和宏
1. ウイルスを運ぶ文明
もう20年ぐらい前かな。奥本さんに僕が初めてお会いした時の印象が強すぎて。奥本さんの発言は、さらりと毒針が効いている(笑)。今日もよろしくお願いします。今は、まさに100年に1度のパンデミックといわれるコロナ禍で、この前はスペイン風邪でした。
第一次世界大戦でアメリカの兵隊が広めたという説もありますね。じっとしてりゃあいいものを……でも動かずにはいられない。動くから動物なんだ(笑)。
敵地へ送り出された船内で兵隊が感染し、着いた頃には戦闘できないほど弱っていたと。スペインは中立国だったので感染症の実態を発表した。しかしアメリカ側もドイツ側も…。
戦略上の理由からこれを隠していた。それで、スペイン風邪という名前が付いた。
スペインはえらい迷惑です。
まさに風評被害に近かった。そもそも人間は増えすぎ。なにしろ石を投げれば当たるほど個体数が増えた大型哺乳類で、これは異様な事態です。資源を食いつぶし他の動物に多大な迷惑を掛けている。人間が増えたことがパンデミックを招く主な要因だと思いますね。
人間は自然に対して遠慮なくずかずか入っていくところが、やはり一番の問題でしょうね。
人間は科学の発達の旗の下に突き進んできた。しかし、生物として、自分の天敵を滅ぼすのはルール違反です。例えば、草食獣のカモシカがライオンを滅ぼすようなことがもしあったとすれば、カモシカは増え、植物を食いつぶし、仲間同士で争うようになる。ギリシア神話にあるように、人間同士が争って敵を滅ぼしてしまうと、そこに呼び寄せられた戦の神様・軍神マルスの下、次は、異民族でなく内部分裂して戦は無限に続いていく。人間の敵は人間というわけです。

コロナウイルスは必ずしも生物とは言えないけれど、森林の生態系の中で他と共存していた。うまくバランスが取れていたところへ人間が入ってその調和を乱してしまったわけです。昔から、結界ってありますね。
このアクリル板も結界ですね(笑)。
結界とは、あるところから奥へは近づかないという、日本人がもっていた自然への畏れだと思うのです。
敬して遠ざける。
慎みです。
でも科学者というのは、その奥を知りたいのでしょう。
そう。そこが問題でね。
いろんな武器もできましたね。顕微鏡も電子顕微鏡になり…。
顕微鏡の進歩は劇的で、ここ10年ほどで科学論文の質が完全に変わりました。顕微鏡という道具は当初、生きものを見る、せいぜい細胞を見るものでした。それが今や直接分子を見ることができる。
目に見えないものが見えるようになり、それを言葉で説明するのが科学の務めでしょう。
今回のパンデミックでは、それが大きな役割を果たしています。コロナウイルスの表面に突き出たスパイクタンパク質が、私たちの細胞表面で血圧調節に関わるACE2という膜タンパク質に結合することがわかっています。それがいち早く中国の研究者の論文で、クライオ電子顕微鏡を使って、二つの分子の構造として見えてしまった。実はその二つのタンパク質が結合することに何の必然もありません。たまたまウイルスのタンパク質と私たちのタンパク質がうまく結合できたために感染が成立してパンデミックになる。ウイルスのほうで人間を殺そうと思っているわけではないのです。
パスカルの言う「宇宙」と同じで、そこに意思はないということですね。
そう。ただウイルスも自分の遺伝子を次につなごうとしている。以前、同じコロナウイルスでSARSが流行りましたが、あれは強すぎた。宿主が高確率で死んでしまい、それ以上は広がりませんでした。
寄生者は、宿主を生かさず殺さずというのが原則ですね。殺したら自滅。
ウイルスはどんどん変異します。しかし最終的には弱毒化していく。
でも今のコロナの変異株は、少し強くなっていませんか。
一時的にそれがあっても長続きはしません。ウイルスは宿主と共存する必要があるので、感染力をできるだけ強くして、しかし、相手を殺さない。進化的には共存する道を選ぶはずです。
お互いの幸福のために。
人間の歴史は感染症との戦いです。現代は世界中で人間が移動している。それがパンデミックを招いた。今、この瞬間、世界中の空を航空機が何機飛んでいるかをリアルタイムに見るソフトがあって、それ見ると、とんでもない数が飛び交っていて怖くなります。ですから驚いたことに、私たちが狩猟民族の時代には感染症はなかったらしい。農耕を始めてみんなで集まるようになってから。
定住して人口も増えますからね。
それで感染症が起こったらしい。それが伝播するのはやはり輸送だそうです。まず海上交通で。
陸上では伝播しないの。
なぜかというと旅の途中でみんな死んでしまうから。ところが船だと、感染した人を二、三日で次の町まで連れて行ける。交通手段という文明が感染症を運んでいるわけです。
なるほど。スペイン風邪がまさにそうだったわけですね。
2. 風土から逃れられない生きもの
いつも奥本さんの本は面白く拝見しています。この『虫から始まる文明論』を読ませていただくと、虫も鳥もその風土の色をしているということが最初に出てきますね。
生きものは風土から逃れられないと思うのです。例えば、南米とマダガスカルとでは、蝶も甲虫もまったく違う色彩をしています。しかし、同じ土地にいる蝶と鳥を比べると同じような色合いや模様をしている。アフリカの蝶は多くが赤い土の色をしていますし、同じアフリカでも森林地帯のオカピは、そこに棲む甲虫と同じ色や模様です。他にもシマウマと同所に棲むフタオチョウという蝶の裏翅が縞々柄だったりと。

なぜ、そうなったのか。これが、ファーブルとダーウィンの喧嘩のタネという気もしますね。風土への同化というのは、擬態の一種という風には考えられますね。一番見つかりにくい。
それが最も労力が掛からず経済的な方法かもしれません。無理がない生き方です。
蝶も、動物も、その風土の中で最も風土に溶け込むような色や形のものが最終的には生き残れた。そのように淘汰圧が掛かっている。
人間も、例えば、ハワイで日系2世の人に出会った時、やはり日本人との違いを感じるでしょう。服装の趣味や髪型、話の仕方等も含めて、その土地で日系アメリカ人として一番抵抗の少ない暮らし方がその人をつくっていくから。
奥本さんはご著書に、和歌や俳句は外国ではできないと書いておられましたね。僕はそのことを実感しました。アメリカに2年留学していて砂漠に驚いた。初めてネバダ砂漠へ行った時、何とかしてこれを詠みたいと思ったのです。でもついに1首もできませんでした。
わかります。渡米した日本人が、タコマの山を見ると富士山を思い出すというような形でしか歌にならないでしょう。
そう。斎藤茂吉のドイツ留学中の歌も、出てくる固有名詞は外国でも、全部日本の風景。われわれはそんな風にしか風景を捉えられなくなっている。見たものをいかに言葉で表現できるかはとても重要です。しかし、言葉では、どうしても表現できないもののほうが、自然界には圧倒的に多い。
言うべからざるが感動を覚えるという。
今日、お聞きしたかったのは、奥本さんは虫を見ておられて、更に、虫を扱った文学に強い関心を持っておられますが、虫の表現というものは日本人と外国人とでは違いますか。
全く違います。昔のフランス人にとって、虫は悪魔の作った生きものですね。それは、彼らの皮膚感覚でもあると思います。
人間が対象を観察する時、日本人の眼は接写レンズ。そして、欧米人の眼は広角レンズだとおっしゃっていますね。
欧米人はそもそも細かいものを見ていませんね。その目に虫は映らないのです。一方、日本人の接写レンズに風景はありません。だから、浮世絵に風景画はないと僕は思うのです。
その違いは、言葉の扱いにも影響しますか。
そう思います。
例えば、フランス語と日本語とで、色に対する言葉は違いますか。
日本の茶色い猫は、フランスでは黄色い猫です。虹もフランスは日本と同じ七色ではないと思います。虹は三色という民族文化もあります。それは色の名前がないからで、言葉がなかったらわからない。
なるほど。色の名前が三色しかなければ、虹は三色にしか見えない。言葉がないと認識できませんね。日本は色に対する言葉が豊かです。
とくに古代の色は、にび(鈍)色とか、つるばみ(橡)色とか。
はねず(朱華)色とかね。
ねずみ色が何種類もありますでしょう。利休鼠(りきゅうねず)なんて言ってね。今では忘れられてしまいました。
言葉ができることで、新しい認識ができていく。
段階の切り方が違ってくる。分類の仕方も同じでしょうね。
蝶は色覚が優れているそうですね。人間には見えない光の波長まで見える。
花や草の色がわからないと困りますからね。われわれが蝶を捕りに行く時も、例えば、ヒマラヤのテングアゲハを狙うなら青い捕虫網を持っていくし、ギフチョウも青い布を広げて置くと向こうから寄ってきますね。ふつうのアゲハは赤い網。
昼行性のチョウは色覚が優れ、翅の模様もいろいろと変えて、これは擬態だろうと思いますが。一方、夜行性のガは聴覚が優れているらしいですね。
ガは黄昏飛翔性で、チョウとガは、昼と夜の棲み分けですね。ハナムグリとコガネムシが同じことをやっています。ハナムグリは昼間に飛び回って花に来ます。コガネムシはクヌギの葉等を食べますが、夜行性で色覚は貧弱です。
夜はコウモリ等の捕食者に狙われる。コウモリは超音波で探索しますね。それをガのほうも聴覚でキャッチできるらしい。
なるほど。一緒に進化している。
しかも、ガのほうでも超音波を出して、コウモリはそれ感知すると、不味いガを避けるんですって。
お互いにやり合う。そういう進化の仕方って本当に信じられませんね。想像力。ファーブルは、ありとあらゆる可能性を想定して、それを一つずつ検証していくんです。例えば、オオクジャクヤママユというガは、雌が羽化すると、大量の雄が遠いところから帰ってくる。一体、何によって引き付けられているのかと考えて、彼はフェロモンを予言しましたが、その時、超音波のようなものまで想定していますね。
研究館では尾崎克久さんという研究員が、アゲハチョウの食草認識のしくみを探っていますが、母蝶はどこへでも飛んで行けますが、幼虫は卵から生まれた場所で育つしかない。だから母蝶がどこに卵を産むかが死活問題なのです。
母蝶は葉っぱを食べませんね。それなのに幼虫の好みの葉っぱを探り当てているわけでしょ。
そう。すごいですよね。
狩人蜂も。ハチはやはり花の蜜を吸いますが、肉食の幼虫のために獲物を狩り、そこに卵を産み付けますね。
母蝶は、葉っぱを叩いてある匂い物質を神経細胞で感知すると、そこに卵を産む。
幼虫の食べる葉は蝶によって柑橘の仲間などに限定されるとしても、同じ物質を含む葉であれば、系統的には縁の遠い植物でも、そこへ行きますね。
まさにその通りで、しかし、葉に忌避物質と呼ばれる成分が含まれていると、代謝できないのですが、その耐性を獲得すると…。
食べたものを無毒化するということですか。
そう。解毒する能力を獲得すれば、それを食草とすることができるわけです。食べることができて、かつ競争相手も少ないものが“美味しい”わけです。
アオスジアゲハは幼虫がクスノキの葉を食べますね。クスノキは樟脳の原料です。防虫剤ですから他の虫は食べません。アオスジアゲハはそれを独占している。そういう開拓の仕方もあるんですね。
3. 蟲愛づる姫君
生きもの研究の基本は観察ですね。よく観察し、何でやろうと疑問が湧く。現代の科学者は、それを分子生物学や細胞生物学として探っていく。
ファーブルの場合は、その観察している自分をまた別のところから観察していますね。
というと。
身体から抜け出した霊魂が空中に漂って自分を見ているような、そういう描写があります。『失われた時を求めて』のマルセル・プルーストが『昆虫記』をよく読んでいますが、きっとそういうところを面白がっていたのでしょうね。観察している自分をまた観察している。
面白いですね。幽体離脱そのものですね。ところで先ほどの続きでお聞きしたいのは、ファーブルはダーウィンの進化論を認めていなかった。

認めていませんね。
でも二人は仲が良かったそうですね。
ええ。文通しています。
ファーブルが、進化論を認めなかった理由は何だったのでしょうか。
例えば、狩人蜂の母親が獲物の幼虫・ヨトウムシを狩るとします。その時、正確に、神経節だけを刺していくのです。そうするとヨトウムシは生きたまま運動神経が麻痺して、生きたまま蜂の幼虫に食われる餌になるわけです。では、狩人蜂の母親は最初から、そのように洗練された方法で狩をしていたのだろうか。たまたま狩が成功して、それが獲得形質として遺伝するなんて、そんな偶然が重なることはあり得ないとファーブルは主張したのです。「最初のハチはどうやったのか」と言われてダーウィンも困ったらしいですね。
でも適応進化ということを、個体は犠牲になっても、種全体として存続すればよいと考えれば。
ええ。種の進化と、永い時間で捉えれば説明がつくと今の科学者は言いますね。しかし、ファーブルは、自分の眼で見たことしかわかりませんという立場でしたから。
なるほど。昆虫や植物との共進化というテーマは本当に面白いですね。研究館では、イチジクとイチジクコバチの共進化も探っています。
あれは、「壺中の天」ですね。壺の中に全世界がある『胡桃の中の世界』とかいうようなことでしょうね。やはりスケールが小さいことのメリットで、コバチにとってイチジクの内部は、この部屋よりも大きいでしょう。
しかも、食料もそろっていますし。
そこで食っちゃ寝、食っちゃ寝している。私も、です(笑)。
植物がそれを準備してあげているってのはすごいですね。
それがまた一方的に利用されてませんものね。花粉媒介に利用しており、したたかですよね。
更に、コバチを狙って、そこに卵を産む別の昆虫もいるとか。
ちょっとでも隙があると、そこを利用するやつがおりますからね。アリの巣の中に寄生する生きものの世界なんてもう本当に大変です。
奥本さんは、幼少の頃から虫に興味をもっておられますが。平安時代の『蟲愛づる姫君』についても書いておられますね。これは前館長の中村桂子さんが大好きで、生命誌研究館に来ていただくと蟲愛づる姫君の屏風があります。『堤中納言物語』の一編ですが、読み直してみると、まさに日本最初のサイエンティストです。
世界最初と言ってもいいでしょう。あんな風に素直に蝶の飼育日記を書いた人はないでしょう。
しかも最初の女性科学者です。
だから日本は女性が活躍してくれなければ国力が落ちますよ。
化粧もせず、きちんと自分の考えを述べるこの姫君は、現代のわれわれから見れば、とても魅力的な女性ですね。『蟲愛づる姫君』の一節に「本地たづねたるこそ、心ばへをかしけれ」とありますが、これはものごとの本質を見極めてこそ、意味があるんだということで。
それ、ファーブルの言っていることですよ。
なるほど。更に、「これが成らむさまを見むとて」と、つまり幼虫が蝶になる、その発生過程ですね。それをそのために「さまざまなる籠箱どもに入れさせ給ふ」。
螻蛄男(けらを)とか、蟲麿(むしまろ)とか男の子に名前つけて、それをやらせてね。
ええ。つまりここで、観察と実験ということを言っています。そして「いま新しきには、名をつけて、興じ給ふ」、楽しんでいたと。
新種に命名しているわけですね。
分類ということを意識している。最後は「よろづの事どもをたづねて、末を見ればこそ、事は故あれ」、つまりロジックですね。現象をつぶさに観察して、考察して、結果を見届けてこそ意味があるんだと。
科学は『蟲愛づる姫君』に尽きるんじゃないですか。
そう。この物語は作者未詳ですが、よう書いたなあと思って(笑)。科学の本質を、あますところなく語っていますよね。でも世界で初めてというのは、今日、初めて聞いた。
だってアリストテレスよりずっと科学的でしょう。アリストテレスは、キャベツに置いた露の玉が蝶の卵になるなんて非科学的なことを言っていたわけですから。しかもアリストテレスが書いたことが正しくて、自然を観察して、もし違うことがあれば、それは自然が間違っているというのが中世の学問の世界でしょう。
自然発生説も、19世紀にパスツールの実験で否定されるまで信じられていましたからね。
4. 日本の自然は優しい自然
日本におけるフランス文学って、一体何だったんだろう。全部、間違いだったんじゃないかと思う時があるんです。
ああ、翻訳のことを書いておられましたね。
ええ。ヴェルレーヌの「落葉」は上田敏の訳が素晴らしい名訳ですけども、大いなる誤解でもあるという。
同じ「落葉」でも奥本大三郎訳を見たらびっくり、ギョッとしますからね(笑)。
上田敏は「そこかしこ飛び散る落ち葉かな」って、ぴたっと、俳句になってます。一枚の落葉に収斂していく日本人特有の接写レンズの眼です。でもフランスの風景は広角レンズでないと。フランス文学者って自然音痴の人が多いから、何の葉っぱかも考えていません。日本で落葉と言えば紅葉。するとまた「流れもあへぬ紅葉なりけり」という風になってしまいますが、ヴェルレーヌの落葉は、パリの街路樹でマロニエとかプラタナスのガサガサした大きな葉っぱですから、むしろサルトルの『嘔吐』の世界なんですね。
いやあ、本当にその通りですね。ただ、必ずしも自然から文学が出てくるだけでもなくて、逆に、文学があって自然を見る眼が変わるということもありませんか。
でもその文学は、それ以前に、自然に育てられていますからね。
それはその通りですけど。藤原俊成が『古来風体抄』の中で、われわれは桜を見て美しいと思っているけれど、それは違うんだと。桜が美しいのでなく、われわれは桜を詠んだ名歌を知ってるから、桜を見た時に美しいと感ずるのだと。
「さまざまなこと思い出す桜かな」
「世の中は三日見ぬ間の桜かな」と(笑)。つまり、日本人がこれだけ桜を愛でてきて、歌にも、俳句にも詠んできたことで、桜に対する感受性が変わってきているのではないか。
それはそう思いますね。欧米人が喜ぶのは、ぼってりした八重桜でしょうね。そうでなければ実のなる桜。
桜桃ね。チェーホフの世界ですね。
実も成らない桜なんて。
しかも1週間で散ってしまう。
散ることが美しいなんて言ったら、ますますわからんと言われてしまう。
歴史的な蓄積ですね。
日本の自然は優しい自然で、それが日本人をつくり、日本独自の感性に基づく言葉もできてくるのでしょうね。
言葉ってデジタルです。デジタルだから隙間がある。だから僕は、歌人って〈隙間産業〉だと言っているんです(笑)。出来合いの言葉と出来合いの言葉の間にあるものをこそ表現したい。
先ほどの上田敏の訳で言えば、あれは日本人の感性に沿った、これだったら日本人に受けるだろうという訳で、そこには違和感というか、自分と違うものがない。それは、快くはあるけれど、驚きではない。やはり自分にはないものが示された時に、外国文学を読む喜びを感じます。
昔の「岩波語」のような、ぎこちない難しい訳文をありがたいと感じる。
岩波語ですか。
北杜夫さんは、それによく影響された作家じゃないでしょうか。トーマス・マンの『ブッテンブローク家の人々』などの翻訳で北杜夫ができたとも言えるし、三島由紀夫も、少年時代に『ドルジェル伯の舞踏会』等の堀口大学の日本語訳から影響を受けていると思いますね。

なるほどね。ものを読む時に、なるほどと納得しながら、既知を読むアルファ読みと、こんなことがあるのかと驚く、未知を読むベータ読みがあると外山滋比古さんが言っておられますね。
でんぷんと同じで熱を加えるとアルファからベータになったりします(笑)。外国文学という熱を加えられるとね。
その落差が外国文学読む喜びですね。
時々、徳川三百年間の漢詩というのは、何だったんだろうと思います。朝鮮の使いが来て、筆談で漢詩をやりとりして、発音もわからないのに、大変な努力で習得した漢詩をつくる能力でしょう。欧米人もラテン語で詩を散々書かされますが、あれも名作と言えるものは残っていませんね。やはり母国語でないと作品はつくれないような気がします。
でも、それは翻訳者としてはつらい言い方になりませんか。
翻訳者は、外国文学の刺激を受けて、そこから新しいものをつくって、チクチクと昆虫の針で刺されて虫こぶをつくっていけばよいわけです。
虫こぶですか。なるほどね。
5. 「虫の声にぞ驚かれぬる」
一度、伺いたかったのですが、虫がお好きな奥本さんにとって、標本というのは、やはり特別な位置を占めているのですか。

この2階に、標本が3000箱程あります。
ええ。以前も見せていただきました。でも、生きている虫を見る時と、標本を見る時とは、やはり違うものですか。
標本には骨董的な喜びがありますね。生きて飛んでいる蝶々と、形を整えて箱に並んでいる蝶々とでは、また魅力が違います。因果なものですね。
箱に並べられた標本は、絵画を見るような、ある種の美として見ておられる?
それと、やはり標本は多様性ですね。本当にこんな形や模様の可能性があったのかという驚きですね。自然界の可能性は限りないですからね。とくに昆虫の色と形の無限の組み合わせは、哺乳類や鳥類にはあり得ない多様性がありますね。やはり世代交代が早いからでしょうかね。
それが最も大きいでしょうね。
それに体が小さいので、少量の物質で成長できるし、ちょっとした隙間に棲み込んで、世代交代を重ねていろいろな遺伝型もできる。
生物の中では昆虫の種が一番多いですからね。しかし、虫の音を聞いて快いと感ずるのは日本人だけで、欧米人には雑音としか聞こえないと奥本さんはおっしゃっていますね。それも、ある種の美意識というか。
角田忠信博士の『日本語人の脳』という本がありますが、脳の使い方が違って、それが言葉とつながっているんだと。
聞きなしということにも関わりますね。
日本人は、何を聞いても、頭の中で片仮名や平仮名を当て嵌めて理解しているから、外国語が苦手なのはその裏返しです。片仮名で英語を表わそうとして、漏れた部分は耳に入らない。それは発音と聞き取り両方に関わると思います。
「虫の声にぞ驚かれぬる」という表現は、やはり文化の蓄積ですか。
中国にも蟲聲䗹䗹(ちゅうせいじじ)なんていう難しい言葉はありますが、擬音表現とは言えませんね。漢字で、コロコロ、リーリーというような微妙な表現はできないでしょう。
言葉にできれば認識できる。それができることで、虫の音に親しみが湧く。
鶏は、コケコッコーだし、汽車の音も「なんだ坂こんな坂」って言ったら、もう、そうとしか聞こえない。非科学的でしょうかね。
日本人の接写レンズ型の感性は、最初はどこから来ているんですかね。
狭い島に住み、デリケートな花の色を見。
短詩型をもったことも大きいかも。俳句なんてもう一瞬を切り取るだけで。
長詩は日本では育ちませんでしたね。いきなりですが、ランボーは長詩で訳すといいのがあります。富士山を詠んだ万葉の詩みたいに、ランボーの「精霊」という詩を訳すといいです。
そうですか。歌というものは、盛り込むのでなく、削り取るものです。いろんな属性をすべて剥ぎ取って、最後に一つだけ残ったものを歌にする。これも、接写レンズ型の文化の一つですね。
ここでも俳句の会をやっているんですよ。
えー、そうですか。
スカラベ句会と言って、虫のお題で。
なるほどね。名前がいかにもこの昆虫館にぴったりだ。僕も1回見学に来ようかな。
是非いらしてください。
そうですか。是非。
6. わからないということがわかる
季刊「生命誌」では、奥本先生の対談と一緒に、植物と昆虫の関係を特集しますが、その一つに、ファーブルも書いていますけれど、キャベツにモンシロチョウが卵を産んで、青虫がキャベツを食べていると、そこへ寄生蜂が来るという。
サムライコバチですね。
ええ。サムライコバチが来て、青虫が寄生されるという関係ですが、その蜂を呼び寄せる匂いをキャベツが放っていたという。
はい。植物が虫を呼びますね。もっとすごいのは、アブラムシがクサカゲロウを呼ぶ時、カイロモンという物質を出すそうですね。これは、ファーブルの時代にはまだわかっていなかったと思いますが、例えばバラがあると、そこにアブラムシが来て、単為生殖で爆発的に増えますね。すると、そこにテントウムシが来る、クサカゲロウが来る、それからヒラタアブが来る。それぞれがアブラムシをどんどん食べるんです。それでも食べきれないぐらいアブラムシが増えると、今度はアブラムシが自分から天敵を呼ぶ物質を出して、食草を食い尽くす前に間引いてもらうそうですよ。どこまでやるんですかという感じでしょ。
なんだかちょっと悲しくなってしまう習性ですね。
生物の世界って、考えようによっては、悲しいですよね。粛然とせざるを得ません。ファーブルの『昆虫記』には、そういう話の芽は大体網羅されていますね。現代は、分析技術も進んで、より細かく解明できるわけですが、でもどこまで調べても、「それでその先は?」って言われると同じです。やっぱりわからない。だから面白いんですね。終わらないですよ。
昨年、僕が館長に就任して、これから、どんな風に生命誌研究館を特徴づけようかと考えて、初めの挨拶の時に、「問いを発掘する場」というコンセプトで行こうと言ったのです。
問いを発する場。なるほど。
ええ。今のお話もそうですが、わかったと思ったら次にまたわからんことが出てくる。そこが面白いということですね。
わからなかったことがわかると、わからないということがわかるんですよ。
そうそう。まだここがわからないんだということを教え合うのが、本当の教育だと思います。
一番わからないのは、われわれがなんで生きているのかという。
本当にそうですね。

対談の後、ファーブル昆虫館の地下階にある「ファーブルの生家」を案内していただきました。
現地の採寸に基づき、南仏ルーエルグ地方の古民具や家具を集めて再現。ファーブル一家の当時の暮らしが慕ばれます。
写真:大西成明
対談を終えて
-

色と形の無限の組み合わせ
奥本さんに初めてお会いした時、男の子は幼少時、昆虫少年かラジオ少年かに分けられるとおっしゃったのが、今も記憶に残っています。残念ながら、私は典型的なラジオ少年でしたが、奥本さんは、昆虫への熱をそのままに、『完訳版ファーブル昆虫記』の翻訳を完成されました。虫と文学のお話を伺い、昆虫館地下に作られたファーブルの生家も見られるという、なんとも贅沢な対談になりました。
今回昆虫の色と形の無限の組み合わせからなる多様性の魅力を語られたのが印象的でした。次々と展開する話題転換の自在さは、まさに昆虫の多様性にも似た精神の自在さの反映かとも思ったことでした。 -

終わりのない「なぜ?」
久しぶりに永田館長とお会いして、新しい知見をというより、私が日頃考えていることを先生に確認して、「ああ、それでいいんだな」と安心しました。生物に対する見方は一致していると感じました。
「生命誌」に書かれたことは、多くの研究者による営々たる努力の、ほんの“ひとひら”でしょうが、やっぱり面白い。私が翻訳したファーブルの『昆虫記』には、この博物学者が一生かけて研究した虫達の生態が書かれています。そのテーマが、現代の技術によって精密に掘り下げられていることがよくわかります。それでも生命については、いつまでたっても、その奥があるんですね。

1944年、大阪生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。同大学院修了。埼玉大学名誉教授。フランス文学者。作家、翻訳家として幅広く活躍。『虫の宇宙誌』で読売文学賞、『楽しき熱帯』でサントリー学芸賞、ファーブル『昆虫記』完訳で菊池寛賞、一連の活動に対して第53回JXTG児童文化賞を受賞。著書多数。NPO日本アンリ・ファーブル会理事長。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)