生命誌ジャーナル
2011年遊ぶ
短歌と科学、定型の中に生まれる遊び
永田和宏 京都産業大学総合生命科学部教授・学部長 × 中村桂子 JT生命誌研究館館長
科学と歌それぞれに同じ情熱を注ぎながら、どこか余裕を感じさせるお話ぶりに、遊びの真髄を見ながらの楽しい時でした。歌は、自分の中に存在する得体の知れないものに最も端的な言葉を探す作業だというお話に、科学にもそれがあると思いました。今の仕事は「生命誌研究館」という言葉を見つけたことでそれまでのモヤモヤが消え、始まったものですから。「逝きし夫のバッグの中に残りいし二つ穴あくテレフォンカード」という見知らぬ方の歌に、「共有する時間」を感じとり、科学でもこの感覚を生かしたいと語り合ったこと、次につなげて行こうと思います。(中村桂子)

永田和宏(ながた・かずひろ)
1947年滋賀県生まれ。京都大学理学部物理学科卒業。後に結婚する河野裕子らと共に大学時代から本格的に短歌を始め、高安国世氏に師事。森永乳業に就職後、京都大学胸部疾患研究所で市川康夫氏に細胞生物学を師事。米国NIHに留学しコラーゲン特異的分子シャペロンを発見する。京都大学再生医科学研究所教授を経て、京都産業大学総合生命科学部教授・学部長。現在、宮中歌会始詠進歌選者を務める。

1. おもしろいという感覚を大切にする
| 中村 | 今年の生命誌のテーマを「遊ぶ」に決めようとしていた矢先に、3月11日の震災です。少し迷いましたが、こんなときだからこそ、広がりをもつことが求められるのではないかと、思い切って「遊ぶ」という言葉を選びました。永田先生はこの四月に出されたエッセイ『もうすぐ夏至だ』(註1)の後書きで、ハンドルの遊びのような「ある種の<遊び>の幅がエッセイの魅力だろう」と書いていらっしゃいましたね。ということは、細胞生物学と短歌は共に真剣勝負だということですね。
註1:『もうすぐ夏至だ』 永田和宏著。2011年白水社。 |
| 永田 | 遊ぶというテーマで僕がご指名を受けたのは、きっと遊んでいるように見えたからではないかと思って。(笑) |
| 中村 | 先生は新聞の選歌でもお忙しいのでしょうね。 |
| 永田 | 今、朝日新聞の選歌をしていますが、毎週四千通ほどの短歌が寄せられます。 |
| 中村 | それを全部ご覧になるのですか。 |
| 永田 | はい。今は震災に関する歌がとても多く、被災地以外の方は「頑張ろう日本」なんていうスタンスで歌おうとする。一方、被災地の方には、それはもういいよという歌が多い。同じ言葉でも、それを受け取る側の状況によって意味は全く違ってきますね。 被災地の状況をテレビで見るときにも、画面の中央ばかり見ていると、送る側が一番伝えたいメッセージしか受け取れない。それで、第三者が震災の歌を作ってもほとんど同じ新聞の見出し的な歌になる。その人独自の歌は、送り手が意図しないメッセージを画面の端で見つけたようなときに生まれるのかもしれませんね。 |
| 中村 | それは言葉を専門とする歌人としてのお話ですが、もう一つのお仕事である科学でも言葉の問題があるように思うのです。 科学者は本来、個々の興味を出発点にして仕事をするものですが、最近は「科学技術立国」という標語を掲げています。そこで皆で同じほうに向かって行くことになるわけです。 |
| 永田 |  皆が右を向いているときに、自分だけは左を向くんだという姿勢が私自身の科学にかける思いなんです。学生たちにも科学の基本は興味、インタレスト・オリエンテッドだといつも言っています。 皆が右を向いているときに、自分だけは左を向くんだという姿勢が私自身の科学にかける思いなんです。学生たちにも科学の基本は興味、インタレスト・オリエンテッドだといつも言っています。「科学技術立国」という言葉に象徴されるように、役に立つということが前面に出てきましたね。日本の科学界全体が短期間の成果だけで研究を評価する方向に動いているのは怖いですね。 |
| 中村 | 生命誌でいろいろな方にお話を伺ってつくづく思うのは、おもしろいという気持から仕事を始めた方は、他のおもしろい仕事とつながって必ず広がりが生まれているのです。例えば、病気の治療法の開発というところから仕事を始めるより、代謝や免疫の基本を研究していたら思いがけず病気につながったというお話の方が説得力があることが多いように思うのです。 |
| 永田 | 自分の仕事がおもしろいのはもちろんですが、人の仕事に自分の仕事と同じような興味と熱意を持てないと科学者にはなれない。いい仕事をしている人は、他のいい仕事をしている人に出会ったら相手そのものに興味をもつから、会話が弾み、話題は科学以外にまで広がります。「おもしろい人が必ずしもいい科学者とは限らないけれど、いい科学者は例外なくおもしろい」というのが、私のドグマなんです。 |
| 中村 | おっしゃる通りですね。 |
| 永田 | 広がりが生まれるかどうかは、興味の中心を少し外れたおもしろさに気がつくかどうかだと思います。例えば、図書館で本棚を眺めながら歩いていて、パッと目の端に留まった本をおもしろそう、と感じることってあるでしょう。 最近、自分の仕事は熱心に語れても、他人の仕事について議論できない人が増えているような気がします。学生もそう。僕は学生をあまり叱らないのですが、研究室の進捗報告会や論文抄読会で質問の出ないことがあると、年に一,二回ですが、そのときだけは我を忘れて「研究なんか、やめてしまえ」と激怒してしまう。 |
| 中村 | 柔和な先生が怒っていらっしゃる様子が眼に見えるようです。論文という形で仕事を知った方に実際お会いして初めて本当にそれが分かったという気持になることがあります。生命誌では研究の成果だけでなく、そこに至る過程での研究者の思いも伝えることが科学を語ることだとしています。 |
| 永田 | なぜその仕事をしたかなど、論文に書かれていない背景を知りたいときは、本人に会うほかないですね。 実は一流の歌人は歌以外にも幅広く興味をもっているし、科学者で詩や文学に興味をもっている人も大勢います。遊び心をもった人と語り合い、話題が活発に飛び回る時間はとても充実して楽しい。無駄を怖れていては、学問は成り立たないんじゃないかと思います。 |
| 中村 | 研究館は学問、即ち考えることがどれだけ自分を広げて色々なことを教えてくれるかを感じられる場にしたいと思っています。 |
| 永田 | 世の中にはいろいろな見方があるんだと知っていく「過程」が学問ですね。何かを考え始めると初めは次々と考えが湧いてきますが、自分の内から出てくる見方だけではなかなか広がりません。新しい見方を知ると、なぜか広がる。この過程にはある種の遊び心が必要です。遊びは無駄と考えがちですが、それは必須のものでしょう。 |
| 中村 | 世の中では一つの物の見方を徹底していくのが学問だと受けとめられているので、その遊びが難しい。 |
| 永田 | 日本には「この道一筋の美学」という風潮があって、私の場合などでも、短歌をやっているということで、いくらサイエンスに集中していても、本気じゃない、いい加減だと見なされることもありました。さらに困ったことには、自分の中にもそんな価値観がどこかに抜き難くあるんですね。 |
| 中村 | エッセイによると、科学よりも短歌に出会われた方が早いのですね。 |
| 永田 | 僕が初めて歌に出会ったのは高校時代です。受験勉強のさなかに国語の先生がガリ版で近代の歌を200首ぐらい刷って、読んでくれました。そのとき、いいなあと思った。受験勉強のさなかの、一種の陽だまりのような時間だったのです。それで自分でも歌をつくって新聞に投稿したら一回目は佳作で、二回目は特選になった。若者は傲慢ですから、すぐ特選になるようなものはつまらないと思ってやめてしまった。 |
| 中村 | 才能がおありになったんですね。 |
| 永田 | そういうわけじゃないんです。選者をやるようになってようやく分かったのですが、若いというだけで、ましてや10代の若者だったら、選者としては何としても入選させたいという気持が働くのです。高校生の頃、そんなことには全く思い至らなかった。 そして、大学で再び歌に出会ったのです。僕はスポーツが好きだったのでバスケットと合気道もやりましたが、こちらは続きませんでした。 |
| 中村 | 大学時代の会で奥様(註2)に出会っていらっしゃいますね。歌をずっと続けられたのはやはり奥様の力が大きかったのでしょうか。
註2:河野裕子 【かわの・ゆうこ】 |
| 永田 | 本業の方での科学がおもしろくなり、歌と科学を両方やるのがしんどくなって選択を迫られた時期がありました。彼女がいなかったら科学だけにしていたかもしれませんね。 |
 |
2. 得体の知れない気持を詠み込む
| 中村 | 宮中の歌会始(註3)で永田先生が詠われた「ゆつくりと風に光をまぜながら岬の端に風車はまはる」という歌を読んで、風と光がまざるという感覚が自分のものになってきました。岬の風車の風には、確かに光が混じっています。
註3:宮中歌会始 江戸時代から恒例行事となった、宮中でその年の初めに行う歌会のこと。明治期以降は一般の国民からの詠進も広く行われるようになり、天皇陛下の御製や一般の詠進歌が新聞などで発表されるようになった。 |
| 永田 | 次、風車を見たときに見方が変わるでしょう。歌を作る側の喜びはそんなふうに思っていただけるところです。歌にはものの見方の多様さに気づかせてくれる力があって、一首知っているだけでも日常をとても豊かに感じることができます。 歌は常識的な言葉のつながり方を嫌います。さらに、自分の感情を言わないということが鉄則です。 |
| 中村 | 永田先生の歌を拝読して、うれしい、悲しいという言葉がないことがとても印象的でした。 |
| 永田 | 悲しいという万人に共通の言葉では、その人だけがもつ悲しみを表現できません。 |
| 中村 | 読む側も、悲しいという言葉を聞いたからではなく、その人が悲しいんだと感じたときに初めて、悲しさを共感できますね。近頃は、メディアがよく感動を届けますなどと言いますが、私が見てどう感じるかが大事であって、そちらから押しつけないで欲しいと思うのです。 |
| 永田 | それが表現の基本ですね。 |
| 中村 | 先生が選ばれた歌に「逝きし夫のバッグの中に残りいし二つ穴あくテレフォンカード」という歌がありますでしょう。知らない方ですが、この悲しみを共有できます。 |
| 永田 | あの歌には市井のおばあさんが感じた原初の寂しさがある。読んでそう感じていただくのは本当にうれしい。 |
| 中村 | 病院の廊下には公衆電話があり、テレフォンカードを使って電話を掛けますね。穴二つまでお使いになったという事実からその向こうにさまざまな物語を感じます。悲しさだけでなく、共に暮らした時間のすべて。これが表現なのですね。 |
| 永田 | 感性が柔らかくなければ、こういう表現に感応できません。歌人なら、テレフォンカードに空いた二つの孔に旦那さんと共有した時間がある、までは読めますが、あと孔は四つか五つあくはずだったという痛恨の思いが背後にある。その孔でもっといろんなことを旦那さんと話したかったんでしょうね。感謝の言葉も伝えたかったかもしれない。そこまで読み込めるからこそ僕は歌というものに魅力を感じます。 |
| 中村 | 使いかけのテレフォンカードが思い浮かびます。この表現は歌の世界のものですが、科学こそ事実に語らせるもののはずなのにそれが難しい。 |
| 永田 | 歌は説明を嫌います。斯々然々で悲しいんだとは決して言いません。説明するとだれもが納得してくれるけど、その分感動の高さは下がります。 説明抜きで自分の感情の核が出てきたときには、日常的な感性との落差が大きく、それが驚きになるのです。 |
| 中村 | 表現のあり方として学ぶところ大ですね。 |
| 永田 |  月に一度の歌会では、一首ずつ皆が歌を披露して一巡りするのですが、感情は言わず、説明はせず、いかにして分かってもらえるように伝えるかですね。皆納得はしてくれたものの誰にも詠み手の思いが伝わらないとか、読んだとき一人しか分かってくれなかったけど、後から少しずつ皆が共感してくれたとか、歌を巡っていろいろな出来事があります。一人一人が全く違う読み方のできる歌に一番魅力があります。「歌の読みに正解はない」というのが、僕の信条であり、主張なんですね。 月に一度の歌会では、一首ずつ皆が歌を披露して一巡りするのですが、感情は言わず、説明はせず、いかにして分かってもらえるように伝えるかですね。皆納得はしてくれたものの誰にも詠み手の思いが伝わらないとか、読んだとき一人しか分かってくれなかったけど、後から少しずつ皆が共感してくれたとか、歌を巡っていろいろな出来事があります。一人一人が全く違う読み方のできる歌に一番魅力があります。「歌の読みに正解はない」というのが、僕の信条であり、主張なんですね。作者はその歌の持ち主ではありません。歌の解釈は作者が握っているものでもないと僕は言っています。作者も読者の一人に過ぎないと思っていた方が、読みの可能性が広がる。 |
| 中村 | 作者に決定権はなくて、皆で探っていくのは表現の基本ですね。 |
| 永田 | 河野裕子は昨年亡くなりましたが、彼女が検診から帰ってきたところを迎えた僕は、医師から癌と聞かされているのだけれどさりげなく迎えようとしました。彼女がそのときのことを詠んだのが、「何といふ顔をして我を見るものか私はここよ吊橋ぢやない」です。これはショックでしたね。これなんかどう受けとめたらいいのか。だから言葉に対して敏感にならざるを得ません。 |
3. ロジックを越える
| 中村 | 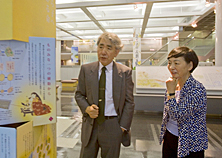 研究館の「表現を通して生きものを考える」グループでも表現の基本は言葉なので、科学でも言葉への敏感な気持がなければいけないと思っています。 研究館の「表現を通して生きものを考える」グループでも表現の基本は言葉なので、科学でも言葉への敏感な気持がなければいけないと思っています。そこで毎年のテーマを動詞にしています。例えば、生きものを考えるときに名詞で「生命」と言わずに、「生きている」と動詞で考えると、蟻や鮭という個々の生きものがどのように生きているかについてのイメージが広がり日常性や動きが出てきます。 |
| 永田 | 歌でも名詞ばかりでは窮屈になり、動詞が多いと歌としてのまとまりが無くなるので動詞の数は一首平均3.5か3.3になるという研究報告があります。 生命誌でも同じだと思いますが、でき合いの言葉を使っていると自分の考えは話せませんね。人と同じ感じ方は表現しない。大事なのはわずか31文字で相手が感じるきっかけをつくることで、その先は読者に任せるわけです。歌も俳句も短詩系統の表現は非常につつましく、逆にそこに意味があります。 |
| 中村 | 河野さんも永田先生も日常を語る歌が多いのに、思いがけない驚きがある。言葉の選び方なのだと思うのです。 |
| 永田 | 日常生活では手垢のついた言葉を使っているので、歌を作る前には、日常の埃を洗い落とす必要があります。歌の言葉のプールまでたどり着くのにずいぶん時間がかかります。一晩考えても日常の埃を被った表現になって歌がつくれないということもよくありました。 歌を詠むときには、これだという言葉を一瞬で掴む。それはロジックで出てくる言葉ではありません。 |
| 中村 | 科学は論理の世界ですが、表現するときには今おっしゃったことと同じで何かをつかまなければなりません。生命誌では科学的な事実を歪めないぎりぎりの表現を追求したいと思いながらそれはとても難しいと思っています。やはり歌には定型があるから、そこまで言葉を錬ることができるのでしょうか。 |
| 永田 | 詩人に「現代詩ってどこで終わるんだい」と聞くと、風邪が自然に治るように終わるという人もあれば、どうしても次に言葉が出てこなくなったときが終わりだという人もある。歌には五七五七七という定型があります。その中でああでもない、こうでもない、と推敲する手順があります。何か違うなと思いながら言葉をやり繰りしていると、全く違う言葉が突然浮かび、こういうことだったんだと気づく。定型の恩寵だと思います。 |
| 中村 | 約束事は私たちを縛りつけるものと思いがちですが、むしろ約束事があるがゆえに遊びや広がりが生まれるとも考えられますね。 |
| 永田 |  人間は誰だって、あと何十年かすれば死の瞬間がくるという約束の中で生きています。死の瞬間があるからこそ、今が充実すると言ったのはハイデガーですが、確かに意識が充実しているときでないと遊べない。漫然と時間を過ごしているのは遊んでいるとは言えません。 人間は誰だって、あと何十年かすれば死の瞬間がくるという約束の中で生きています。死の瞬間があるからこそ、今が充実すると言ったのはハイデガーですが、確かに意識が充実しているときでないと遊べない。漫然と時間を過ごしているのは遊んでいるとは言えません。 |
| 中村 | 日本語は普段の話し言葉でも五七調だと調子がいいですね。 |
| 永田 | なぜ五七調になったのかについては、もともとは4拍子であり、それは農耕作業のリズムが変化したなど色々な説がありますが、まだよく分かっていません。欧米のソネットなども定型詩ですが、定型をもった詩が1300年も続いている国は日本の他にありません。 |
| 中村 | 千年以上の歴史がある上に、新聞一紙だけでも毎週4000首の投稿があるのですから、歌の裾野はとても広いですね。 |
| 永田 | 全国の地方新聞を含めて、短歌、俳句の欄のない新聞はありません。職業詩人でない人が日常的に詩を作って、全ての新聞が毎週一面を使ってそれを掲載するという国は、世界中探しても日本だけです。外国人の知り合いに話すとびっくりしますね。 |
| 中村 | ラジオやテレビにも短歌、俳句のコーナーがありますでしょう。その割に、日常の言葉が寂しくなってしまい残念ですね。皆さんすぐに「感動しました」とおっしゃるけれど、それを言ってはおしまいではと言いたくなります。(笑) |
| 永田 | 皆と同じ言葉を使えば安心だと思ってしまったら、表現はできません。 |
| 中村 | 最近は旧仮名で歌を詠まれていると伺いましたが、やはり表現をなさる上で仮名遣いの違いは影響がありますか。 |
| 永田 | 定型があるから自由になれると言いましたが、旧仮名を使うようになり、自由になりました。文章を文語で書くのと同じですね。石につまずいて、痛し、とは思わないのに、痛し、と表現する。詩はこのギャップの中に生まれてくる。日常で用いる新仮名と書き言葉としての旧仮名の間にできた距離の分だけ言葉が自由に遊んでくれるというのが実感です。しかし、あまり遊びすぎるのは良くない。そこに旧仮名のデーモンが潜んでいると思っています。 僕は今でこそこうして歌の話ができるようになりましたが、振り返ると中途半端な時期が長かった。先ほど言いましたように、この道一筋の美学が自分をも縛っていた時期ですね。歌と科学の二股という後ろめたさから、二つのものの共通項を見つけて無理矢理、自分で納得しようとしていました。「先生は、科学と文学をどうやって両立されているのですか」などと聞かれると「科学も歌も同じ、どちらも誰もやってないことを見つけるんだ」なんて答えていたものです。 歌と科学は全然違うんだと素直に言えるようになったのは、50代後半です。それまでは二つのことを同時にやっているという後ろめたさからどうしても逃れることが出来なかった。自分で自分を納得させるために人一倍仕事しようと、労働時間だけは研究所の誰にも負けない自信がありました。 |
| 中村 | 科学に没頭しているんだ、ということをご自分に納得させて。 |
| 永田 | 今ではその時間があってよかったと思います。科学と歌の両方の分野の優れた方々に出会い、人様の二倍人生時間を楽しんで生きていると思えるようになりましたから。 |
| 中村 | 歌と科学のどちらかが遊びということではなくて、両方を本気でなさった末に両方に遊び心というか、ゆとりが生まれたということでしょうか。 |
| 永田 | 一方を遊びと意識したらもうだめだと思いますね。歌と科学は全然違うと割り切ったのですが、このごろは、やっぱり同じだなと思いかけています。 |
| 中村 | 行ったり来たりですね。 |
| 永田 | 実はこれまでの30年間、研究室で歌の話は一切御法度にしていました。 短歌の専門誌に作品が載っていただけの頃は研究室の学生の誰一人、僕が歌を詠んでいるとは知らなかった。ところが、ペンネームを使っていませんでしたから、新聞などに歌が載るようになると、否応なく学生たちの目にも触れる。「ここに詠われているのは誰だ」なんて噂していたようです。最近は学生に歌を読まれることも仕方がないと思いはじめていますが、学生たちがそれを真似できることでは決してない。私がなんとか二つのことを同時にやることに折り合いを付けられたのは、相当に厳しい時期を経たからだと思っています。 |
 |
4. アナログの世界からデジタルを引き出す
| 永田 | 学生に接するようになって感じるのですが、今の若い人は、現実の世界から何かを引き出すという訓練を全く受けていませんね。小学校から高校までの教育は、全て、既に分かっている情報を与える。つまり、デジタルからデジテルへ情報を変換することしか教えていないのです。数学や算数はもちろん、国語もそう。文章を見せて意味を問うのは、言葉で表現されたデジタル情報をもう一回デジタルに変換しているだけでしょう。 |
| 中村 | 教育や学問では一人一人の状況に応じて対象から引き出すものが違ってくるところが大事なのに、どんな子供も同じことから同じものを引き出すように仕向けている風潮がありますね。 |
| 永田 | 我々がデジタル情報として認識できるものは最初から世の中に存在するものではありません。現実に生えている木はアナログの存在です。我々が、立木を見て、それを一本と認識したとき初めて"1"という情報にデジタル化され、大きいと認識して初めて大きさの情報になる。 |
| 中村 |  コップに入ったお茶を見て、色を見るか、量を見るか、いろいろな見方はあるけれど、喉が渇いていたらやっぱり飲みたいと思う。こちらの状況でまったく違うところが面白さですね。 コップに入ったお茶を見て、色を見るか、量を見るか、いろいろな見方はあるけれど、喉が渇いていたらやっぱり飲みたいと思う。こちらの状況でまったく違うところが面白さですね。 |
| 永田 | 科学の本質は、実験や観察を通してアナログの世界からいかにデジタル情報を引き出すかに尽きます。他人の研究成果を理解するときにはデジタルな思考が必要ですが、科学でもおもしろいと思うところはアナログ世界です。 |
| 中村 | 今、アナログ世界がどんどん失われていますね。 |
| 永田 | 子供が成長していく過程でデジタルなものにしか触れることができず、アナログ世界を理解できなくなっていくのは怖いことです。 だから学生には、アナログからデジタルをいかに引き出すか、そのおもしろさを伝えようとしているのですが、それでも「先生、正解は何ですか」と聞かれます(笑)。しかし、中には、自分で何かを引き出そうとする学生はいて、やはり伸びていきます。 分かっていることは教科書に書いてあるのでそれを読めばいい。講義で一番大事なことは、「今まだこんなことも分かっていないんだ」と教えることです。分からないことは教科書に書けないから、世界の最前線でしのぎを削っている人にしか講義で教えることができない。だから昨年、京都産業大学で総合生命科学部を立ち上げたときにもいい研究をしている人を採るという方針で人選を行いました。 教科書の中でも、中村先生が訳された『細胞の分子生物学』(ザ・セル)(註4)には教科書を越えるおもしろさがありますね。 註4:『細胞の分子生物学』 【MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL】 |
| 中村 | 原著の『Molecular Biology of the Cell』をはじめて英文で読んだとき、本当に感激しました。それまで分子生物学の教科書と言えばワトソンの書いた『Molecular Biology of the Gene(邦訳:遺伝子の分子生物学)』(註5)しかありませんでした。でも、生きものを考えるときには、どうしても細胞レベルまで行く必要があると思っていたところに、『Molecular Biology of the Cell』が出た。今なぜ細胞を見ることが大事かが述べてあり、しかも、これから見えてくるかもしれないことが向こう側に見えるように書いてあり、教科書で感激したなんて初めてです。
註5:『遺伝子の分子生物学』 【MOLECULAR BIOLOGY OF THE GENE】 |
| 永田 | それはやはり本当の研究者が書いているからでしょうね。 |
| 中村 | 本当は日本の研究者が日本の学生に向けて書いた教科書が一番いいのだけれど、これを超えるものは書けないと思い、翻訳することに決めたのです。 |
| 永田 | 中村先生が感激されたのと同じように、もう亡くなられた僕の恩師の市川康夫先生(註6)もザ・セルに恋をしておられました。
註6:市川康夫 【いちかわ・やすお】 |
| 中村 | 市川先生はボロボロになるまでお読みになられたとか。 |
| 永田 | 市川先生の本は今、僕が受け継いでいます。背表紙も取れて、間にいっぱい挟んだメモで2倍ほどの厚さになったのを譲ってもらいました。 |
| 中村 | 最近では分子生物学の教科書が色々と出ていますが、あの教科書の第一版の意義は大きかったですね。本物が登場したと思いました。 |
| 永田 |  学生たちには、世界一流の研究と我々の研究の日常が地続きだと感じてほしいと思っています。偉い人は自分とは全然別の世界の人だと思ったら興味が湧きませんよ。僕の研究室でも修士の学生の論文が「サイエンス」に載ったことがあって、あいつに書けるなら、と他の学生に活気が出てきたんです。 学生たちには、世界一流の研究と我々の研究の日常が地続きだと感じてほしいと思っています。偉い人は自分とは全然別の世界の人だと思ったら興味が湧きませんよ。僕の研究室でも修士の学生の論文が「サイエンス」に載ったことがあって、あいつに書けるなら、と他の学生に活気が出てきたんです。もう一つ、我々が科学を志した頃って、誰かスーパースターへの憧れがありましたでしょう。そこで、偉人伝をテーマに新入生5〜6人のセミナーをやっていて、自分が感激した科学者を調べて、その人のどこに興味をもったか発表させているのです。 |
| 中村 | 私たちの学生時代はモノーとジャコブの遺伝子の調節の研究が出て皆憧れていました。 |
| 永田 | 僕も湯川先生への憧れから物理に進みました。途中で落ち零れてしまいましたが、夢が破れるにしても本気でだれかに憧れるということが大事でしょう。偉人伝が流行らない世の中になってきたことには、大きな問題があると個人的には思っています。 |
| 中村 | その気持を少し広げて考えたとき、先生が歌の世界をもっていらっしゃることが、研究室で科学を志す若者たちにある種の憧れを抱かせ、影響を与えているとお思いになりますか。 |
| 永田 | 僕は自国の文化を足場としない科学はあり得ないと思っています。論文を読むことはおもしろいけれど、それだけでは興味が他に向かない。だから言葉を横に読んでいるだけでなく、言葉を縦に読む時間も大切にしなければだめだと学生たちには言っていますが、これはもう一方の一生懸命に仕事をしろという要求との両立が難しい。 |
| 中村 | 一日は二四時間しかないのに。(笑) |
| 永田 | 今でも、僕のほうがどの学生より睡眠時間は短いし、よく仕事している自信はあるので、そんなことで文句は言わせません。(笑) ところで、大学には大学の歌、学歌というものがありますね。京都産業大の学歌は初代学長の荒木俊馬さん(註7)という物理学者が作詞されたもので、言葉が万葉集辺りから取られていて、難しいのですが、初めて読んだときいいなあと感激しました。ヒキガエルを谷蟆(たにぐく)というような表現が平気で出てきます。 註7:荒木俊馬 【あらき・としま】 |
| 中村 | これ読めませんね。 |
| 永田 | 文語だから、漢字が読めても意味が分からないですよね。 大学でも高校でも生徒が理解できないから教えない、と生徒のレベルに合わせた教育をやり過ぎているとお感じになりませんか。湯川秀樹先生が五,六歳の頃に祖父から四書五経の素読をさせられたとおっしゃっていますが、理解できなくても必要なときに与えることが大事です。 苫屋、という言葉が小学生には分からないという理由で「われは海の子」が小学唱歌から外されたと聞きました。すると、子どもたちは、藤原定家の「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ」を読んだ時、初めて苫屋に出会うわけです。でも、それ以前に「われは海の子」を歌っていれば、秋の夕暮れを読んだときに、これだったのか、と思う。そのとき初めて本当に出会ったことになるのです。 |
| 中村 | 私も「箱根八里」なんてまさにそれでした。意味も分からずに言葉としては入っているから、大人になって、ああ、そういう意味だったのかと知ったときとても楽しい。 |
| 永田 | ものを知っていく喜びはそこにあると思いますね。最初に知るときは憶えることに一生懸命で感動する余地がない。二度目に出会って、なるほどと思ったときに初めて本当に学んだことになるのです。その過程を飛ばした学びはありません。 |
5. 品質管理に至るまで
| 中村 | 研究の方のお話を伺わせて下さい。大学で物理を学ばれて、一度企業に就職なさってから、生物学に移られたのですね。 |
| 永田 | 僕は京大理学部の物理学科で落ちこぼれたあと、森永乳業の中央研究所に就職して、そこで初めてバイオをやりました。何も分からない状態から吉倉廣さん(註8)に細胞培養を教えて頂きました。最初は顕微鏡の使い方も怪しくて、培養しているはずの動物細胞が一向に増えないので、吉倉さんに見てもらったら「これはごみだよ」と言われたこともあった。(笑)
註8:吉倉廣 【よしくら・ひろし】 |
| 中村 | ごみが増えては困る。(笑) |
| 永田 |  ところが、やり始めたらおもしろくなりました。自治医大に3カ月通って、三浦恭定さん(註9)の研究室にお世話になって、白血病細胞の分化の研究をしました。いま慶応大学の教授をしておられる須田年生さん(註10)が大学院生として入ってきて、彼としばらく一緒に仕事をしました。お互いに血を取り合ったりしましたね。一旦は研究に見切りをつけたはずなのに、自分で手を動かしているうちにその世界に戻りたくなってしまった。このとき、僕は人生で初めて研究者をやろうと自分なりに決心しました。 ところが、やり始めたらおもしろくなりました。自治医大に3カ月通って、三浦恭定さん(註9)の研究室にお世話になって、白血病細胞の分化の研究をしました。いま慶応大学の教授をしておられる須田年生さん(註10)が大学院生として入ってきて、彼としばらく一緒に仕事をしました。お互いに血を取り合ったりしましたね。一旦は研究に見切りをつけたはずなのに、自分で手を動かしているうちにその世界に戻りたくなってしまった。このとき、僕は人生で初めて研究者をやろうと自分なりに決心しました。すでに子供が二人いたのに、無給で京大の胸部疾患研究所の市川康夫さんの研究室に転がりこんだのです。そして、3年ほどで生物物理の論文博士を取りました。論文博士の口頭審問に岡田節人先生や柳田充弘先生(註11)がおられて質疑を受け、全く答えられませんでしたが(笑)。森永時代に論文を二つ出していましたが、どんな場に居ようと論文だけはきちんと書いておかなければと、その時痛切に思いました。 その後、ファイブロネクチン(註12)を発見したNIH(アメリカ国立衛生研究所)のケネス・ヤマダ先生(註13)の誘いで彼の研究室へ移りました。そこのメンバーは皆ファイブロネクチンレセプターを探していました。インテグリン(註14)が発見される直前でした。僕は当時から人と同じことをやるのが嫌な性質だったので、一人だけコラーゲンレセプターを探すと宣言してコラーゲン(註15)に結合するタンパク質を探りました。すると、思いがけずコラーゲン特異的なシャペロン(註16)が見つかったのです。シャペロンは、他のタンパク質の折り畳みを補助して、正常な立体構造と機能をもたせるように働くタンパク質の総称ですけれど、特定のタンパク質の折り畳みに働くシャペロンとしては最初の発見だったので、あちこちのシンポジウムなどに呼んでくれましたが、世界的にはなかなかそんな概念を信じてもらうことができませんでしたね。これは、僕の研究室で全ての解析系を立ち上げて、20年余りかけて仕事を完成させました。 そこから、タンパク質の品質管理という現象への興味が強くなって研究テーマが広がります。特に小胞体というタンパク質合成の主要な場における品質管理の概念が認知され始めたのは90年代半ば頃で、それまで研究者は皆、小胞体で折り畳みに失敗したタンパク質は小胞体の中で処分されると信じていました。だから、タンパク質が小胞体から細胞質へ引き抜かれた後に分解されるという報告は大きなショックを与えました。僕たちはそれに比較的初期の頃から関わることができました。しかも人の見つけたタンパク質で仕事するのは嫌なので、自分たちが見つけたタンパク質から仕事を始めるという姿勢を貫いています。その分進みは遅いですが、自分たちが見つけたタンパク質から仕事が広がっていくと、とても楽しいですね。 僕は研究室の学生たちには、できるだけ大股で歩こうと言ってるんです。人のやったことを跡付ける仕事ももちろん大事ですが、できれば、新しい概念を提出できるような仕事をしたいですね。 註9:三浦恭定 【みうら・やすさだ】 註10:須田年生 【すだ・としお】 註11:柳田充弘 【やなぎだ・みつひろ】 註12:ファイブロネクチン 【fibronectin】 註13:ケネス・ヤマダ 【Kenneth M.Yamada】 註14:インテグリン 【integrin】 註15:コラーゲン 【collagen】 註16:分子シャペロン 【molecular chaperone】 |
| 中村 |  大股で歩こうという言葉の遣い方、やはり永田先生だなと思います。シャペロンから品質管理へ広がっていくお仕事、まさに大股ですね。 大股で歩こうという言葉の遣い方、やはり永田先生だなと思います。シャペロンから品質管理へ広がっていくお仕事、まさに大股ですね。 |
| 永田 | タンパク質はいずれ必ず変性するので、それを分解処理しなければいけません。最近は核のなかで変性したタンパク質はどう処理されるのだろうというところに興味を持っています。細胞生物学者の大多数は、核の中できちんと畳めなかったタンパク質は核の中で分解されるだろうと信じていますが、その様子をまだ誰も証明できていないのです。そこで、細胞が核内タンパク質をどうやって分解するのかを今探っています。 学生たちに言わせると、僕が「それ、おもろいやないか」と言うところから、仕事が始まると言っていますが、いま本当におもしろい状態になっていて、我々が新しく見つけた2つのタンパク質が核から変性したタンパク質を引き抜いて、細胞質で分解しそうだという証拠を得ています。この新しい分解の仕方に「引き抜き分解」という名前を付けて、これから論文を出そうとしていますが、通すのは無茶苦茶難しいと覚悟しています。 新しい言葉を提示するときはかなり気を使いますね。言葉は一人歩きしますし、最初に定着した言葉が残りますから、うまく付けないといけない。 |
| 中村 | 日本人にはそこが難しいですね。 |
6. 細胞のもつあいまいさ
| 永田 | 細胞内の品質管理という概念は、残念ながら日本が最初に言い出したものではなくて、英語圏で出てきたクオリティコントロールという言葉の翻訳なのです。 |
| 中村 | タンパク質合成はアミノ酸配列に従って勝手に正しい構造に折り畳まれるという考えが常識でしたが、このごろまったく変わってきましたね。 |
| 永田 | いろいろなシャペロンが順番に働かなければいけません。 |
| 中村 | あいまいさが見えていますね。今まではアミノ酸配列と立体構造の関係も、タンパク質同士の関係も、一対一で対応させて理解してきましたが、近頃では一対一で対応しているところのほうが少ないと分かってきて、どうしてうまくいくのかますます不思議になってきました。 |
| 永田 |  一昔前まで分子生物学や生化学は、一次構造が決まれば、三次構造は自動的に決まり、それに従って機能も決まってくるという形でタンパク質を理解してきました。タンパク質の機能は、他の分子との相互作用に完全に依存しますから、他の分子との相互作用、あるいは認識の厳密さがタンパク質機能の本質であるわけです。そこには当然一対一の認識が想定されていました。 一昔前まで分子生物学や生化学は、一次構造が決まれば、三次構造は自動的に決まり、それに従って機能も決まってくるという形でタンパク質を理解してきました。タンパク質の機能は、他の分子との相互作用に完全に依存しますから、他の分子との相互作用、あるいは認識の厳密さがタンパク質機能の本質であるわけです。そこには当然一対一の認識が想定されていました。しかし、構造と認識にはどちらもかなりのあいまいさが残されており、むしろそのあいまいさに意味があると思っています。シャペロンを含め大部分のタンパク質間の認識はあいまいです。ヒトゲノムには三万種以上のタンパク質がコードされていますし、作られたポリペプチドがタンパクとして完成するまでに二次構造、三次構造といろいろな中間体を遷移していきますから、その構造を全て一対一の対応で認識していたらシャペロンがいくらあっても足りないでしょう。認識のあいまいさは、生物学でまだ余り皆が注目していないけれど、重要な問題ですね。 |
| 中村 | 先ほど、おっしゃったアナログですね。ディジタルではない。 それこそ、今までの方法論を深めていくのではなく、興味を広げていくという方法でしか理解できないものが出てきていると感じます。工場で採用されている機械を用いた管理では、あいまいな品質管理をすると品質が落ちるわけですが、生物の場合あいまいさに意味があるのですから。 |
| 永田 | 細胞は、コンピュータによる品質管理とは全く違って、偶然や認識のあいまいさが細胞のホメオスタシスを維持しているわけですよね。あるところまで変性したら分解に回す、それ以前なら再生に回す、という分水嶺のような基準は恐らくありません。このあいまいさを科学することはかなり難しくて、まだ誰にもできていないというのが正しいでしょう。生命のもっとも大切な性質は、恒常性の維持にあると私は考えていますが、恒常性とはたった一つの状態を言うのではなく、いろいろに振れていながら、それを摂動的に修正して、結果としてある一定の状態を維持しているということです。ここでもあいまいさの概念を外しては、恒常性を考えることができません。 |
| 中村 | これまでの科学はあいまいさを排除してきましたから。 |
| 永田 | 活発な細胞だと1個の細胞が1秒間に数万個という単位でタンパクを作っているはずで、厳密に時間をかけて作ると追いつかないから、作るときは結構いい加減なんです。しかし、何段階もバックアップのシステムをつくりながらダメだったものを非常に厳密に壊している。 |
| 中村 | 機械の社会とは違いますね、今まで教育されてきた頭には大転換が必要ですね。 |
| 永田 | 生命誌では生物の進化という時間軸を考えておられますが、時間の概念を生物学にどう取り入れるかは大事ですね。生物学者は細胞の中で起こる反応を取りだして、個々別々には理解しているけれども、細胞の中ではそれが全て一連の出来事としてつながっている。 |
| 中村 | 生きものが時間と切り離せない存在だということは、日常的な感覚では誰もが分かっているはずですが、時間を切り離さないと科学の世界にもってこられないために、日常を離れてしまいます。 |
| 永田 | 僕もタンパク質の品質管理を研究する中で、同じところにぶつかりました。今の方法論では時間を含めた観察ができないのです。細胞も工場の品質管理と同じで、変なものができたら、まず合成を止める。次に再生を試みて、再生ができなければ分解をして、分解できなければ細胞自体がアポトーシスによって処理される。再生より前に分解は起きません。 再生の前に分解したらもったいないから遅らせるのだというのは人間社会での合理性で、生物の品質管理にそのアナロジーを持ち込んでよいものかと考えています。 ただ、この再生と分解という2つの現象が逆転しないという事も含め、品質管理の仕組みは何にも考えない細胞にしてはちょっとできすぎているなと思う。とはいえ神の力が働いているわけではなく、進化の産物だと言わざるを得ないのですが、進化だけで説明できるとはとても信じられない。この感覚を自分で感じられるかどうかが、科学を続けていけるかどうかの分岐点だと思います。感情のない科学はおもしろくないですね。 |
7. 歌人・河野裕子の思い出
| 中村 | 研究館の展示にもあります『堤中納言物語』の一編、「蟲愛づる姫君」からは、現代にも通じる日本独自の自然と向き合う姿勢を読み解くことができます。私たち日本人は、万葉に始まり平安時代に作られた歌が今も私たちの生活の中に生きているのはすばらしいと思うのです。 |
| 永田 | 文字として残っている歌を通して、我々が1300年前の感情に同調できるのはすごいことだと思います。いくら科学が発展しても、人の感情のあり様はずっと変わらないということですね。 今残っている一番古い物語は竹取物語ですが、竹取物語でも源氏物語でも地の文は状況説明に徹しており、そのときそこに描かれた登場人物がどう思ったかという心の動きは地の文に挿入された歌の中で詠われています。感情は歌に込めて詠うという世界だったのですね。 |
| 中村 | なるほど、地の文は叙事で、気持は相聞歌でというわけですね。 |
| 永田 | 今、文芸春秋から僕と河野の相聞歌集を出版したいと言う話が来ていて、改めて数えてみると性懲りもなく河野が500首余り、僕のが450首ぐらいありました。 |
| 中村 | 普通の夫婦に、それはちょっとできませんけれど(笑)。歌だから本当の気持を表現できるということもおありなのですか。 |
| 永田 |  『たとへば君―四十年の恋歌』(註17)という本になる予定なのですが、日常生活で気恥ずかしくて言えないことでも、歌でなら言えてしまう。だから、結婚して40年も経って、恥ずかしげもなく恋の歌ができてしまうのかもしれません。河野がいたことが二つの世界を続けられた一番大きな理由だったと思います。 『たとへば君―四十年の恋歌』(註17)という本になる予定なのですが、日常生活で気恥ずかしくて言えないことでも、歌でなら言えてしまう。だから、結婚して40年も経って、恥ずかしげもなく恋の歌ができてしまうのかもしれません。河野がいたことが二つの世界を続けられた一番大きな理由だったと思います。女房には、僕は蒸留水みたいだとか、夢みたいなことを考えている、と何遍も言われました。人生一回しかないのだから、自分のおもしろいことやらないと損ですよね。だれかのためにやってる訳でもないですから。 註17:『たとへば君―四十年の恋歌』 河野裕子、永田和宏著。2011年文藝春秋。 |
| 中村 | 河野さんは、先に亡くなりたくないと思ってらしたことが分かります。 |
| 永田 | 僕が女房にかなり依存していたので、彼女は最後まで僕のことを心配していました。僕のほうは、歌という形で彼女の感情が残っているから自分でも意外に元気なのですが、女房を亡くしてからは何をつくっても挽歌にしかなりませんね。 最期になっても女房は日常生活でよかったとか、ありがとうとか、一切言わなかった。けれど、最後まで歌をつくり続けた。本当に死ぬ前の日まで歌をつくって、それを僕が口述筆記した。改めて読み直すと、これだけは言っておきたいという必死さを感じます。 今、非常に心残りなのは、そのとき彼女が発している歌をこれは作品としていいか悪いかとか、これは採れる歌かどうかとか、文学として見ていたことです。彼女にとっては文学的ないい悪いなんてどうでもよくて、本当にもう最期の言葉で自分の一番の思いを伝えて形に残す手段が歌だった。そのときは「切ないよ」とか「これはいいよ」「よく分かるよ」と言ったんだけど、もっとぎりぎりの感情があったことを女房が生きているときに感じ取ってやれなかった。歌という形をとっているけれども、僕への最期の言葉だった、僕にとって何よりも一番大きな財産だった。このことをもっとリアルに感じ取ってやらんといかんかったと思います。 |
| 中村 | 最後まで歌人で歌として見てしまったということ、よく分かると同時に、私たちのもっている問題点を教えられている気もします。 |
| 永田 | そうです、本当に中村先生がおっしゃるとおり、プロの歌詠みが歌を見るときの目で見てしまった。それが、歌を長くやってきた自分のだめなところだったと思いますね。 |
| 中村 | 「遊び」という言葉の中でお話合いをしてきて、河野裕子さんの最後の思いという先生にとってはお辛い体験まで伺いましたが、失礼を省みず、本当に伝えたいことを歌という形で語ることができるのは幸せでいらっしゃるといわせていただきたいのです。こじつけでなく大きな世界に遊ぶみごとさを感じました。自分らしく生きるところにある広がりです。ありがとうございました。 |
 |
柔らかさのある知に遊ぶ
研究者はそれぞれ専門分野の言葉で語ろうとする。いきおい言葉は多義性を排した正確さの中で用いられることになるが、一方で、それらに議論や連想、新たな発想を導き出すような柔らかさ、ナイーブさが欠けているのではないかと感じることも往々にしてある。
中村先生から対談のお話をいただいた時、これまでの著作に接してきたものとしては、どのようにしなやかな言葉でサイエンスが語られるのかに興味があった。そして対談の中で、実に言葉を大切にされていることを痛感した。サイエンスは、もと「知の営み」という意である。その中には語り合うことの楽しみが当然入っていよう。私自身は、サイエンスの楽しみは語り合うことにありと端的に思っている人間であるが、今回の対談は、まさに「知に遊ぶ」という喜びを感じさせていただけるものでもあった。(永田和宏)