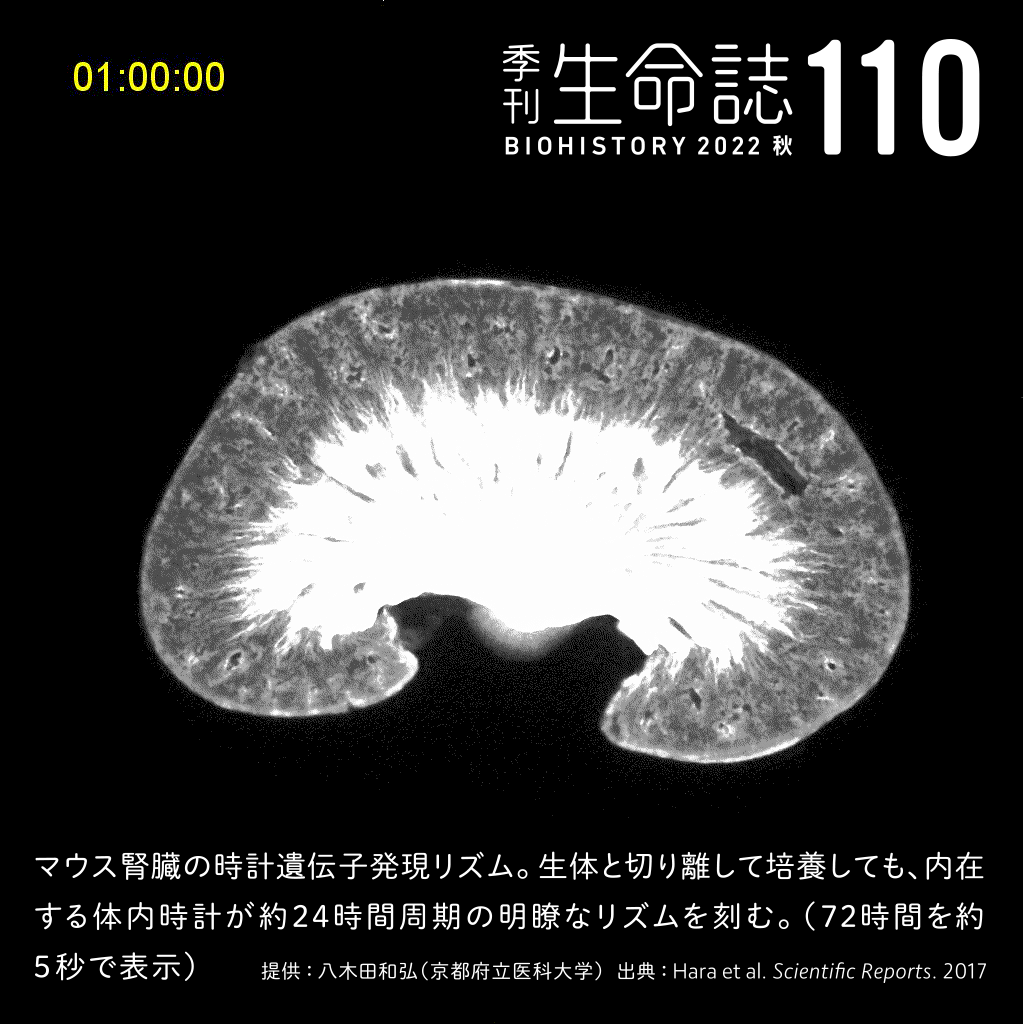RESEARCH
水中のクロロフィルはどこへ?
水圏生態系を支えるミクロな食物連鎖
地球生物圏は光合成によって支えられています。クロロフィルが適度な光を受けると、栄養を作る光合成反応が進みます。しかし、光が過剰になると、強い毒性をもつ活性酸素も発生させてしまいます(クロロフィルの光毒性)。そのため、植物細胞の内部では活性酸素を無毒化するしくみが発達し、陸上植物などはクロロフィルをわざわざ分解するしくみを持つことが知られています。光合成の約半分を行う水中の微細藻類のクロロフィルはどう処理されているのか。柏山祐一郎さんは、クロロフィルの分解物シクロエノール色素の分析法を開発し、シクロエノールがあらゆる水圏に存在することを明らかにしました。ここからクロロフィルの行方を追います。
1.光合成の立役者クロロフィル
地球生物圏はおよそ30億年前に誕生した光合成というしくみに支えられて今日に至る。光合成は太陽から放射される光のエネルギーを利用して、二酸化炭素と水から有機物を合成する過程である。この過程で、光合成生物自身は生きるために必須のエネルギー物質ATPや還元物質NADPHなどを合成し,それらを基に糖質や脂質などの有機物を手に入れている。地球上の多くの生きものは光合成生物を食べ、光合成によって発生した酸素を利用して暮らしている。
私たちに最も身近な光合成生物は樹木や草本などの陸上植物だが、水中の藻類もその能力をもつ植物のなかまである。植物の細胞内には、光合成を行なう器官である色素体(葉緑体)が存在する。陸上植物の葉の緑色は、色素体に含まれる光合成器官(タンパク質複合体)の色である。光合成器官に含まれる色素はいく種類かあり、酸素発生型の光合成を行なう生物のほとんどでクロロフィルaが必須かつ最も大量に存在する光合成色素である。光合成色素は降り注ぐ光エネルギーを吸収し、それを光合成の初期反応を担う光化学系タンパク質複合体の反応中心に受け渡す重要な役割を担う。ところでクロロフィルには、一定の割合で分子酸素(O2ガス)にエネルギーを渡す性質がある。エネルギーを受け取った分子酸素は、一重項酸素(活性酸素の一種)といわれる非常に強力な酸化剤となり、細胞に致命的なダメージを与える。クロロフィルの光毒性という困った性質である(図1)。

(図1)クロロフィルがもたらす光合成と光毒性
2.水中のクロロフィルはどこへ?
実際は、光合成生物は光毒性をもつクロロフィルをうまく利用して活動している。彼らは何重にも張り巡らせた対クロロフィル毒性戦略をもっているのだ。まずひとつの例として、クロロフィルの光合成タンパク複合体内部での配置が、効率よく光合成のためのエネルギー移動を起こし、一重項酸素の発生を抑制するようになっている。また、発生してしまった一重項酸素に対しては、複合体内のキサントフィル類が一重項酸素分子の分子エネルギーを吸い取り、通常の分子酸素に戻すというしくみも存在する。植物細胞内でのクロロフィルの生合成は精密に制御され、不必要に中間物質や分解物(これらにも同様の光毒性がある)が蓄積されないようになっている。しかし、それでもすべてを押さえ込むことはできず、光合成器官は常に一重項酸素の脅威にさらされているのである。
では、細胞内で不要になったクロロフィルはどのように処理されるのか。その様子がよくわかるのが紅葉だ。秋が近づき気温が下がると、クロロフィルの分解が進み、葉の緑色の割合が減る。その少し前から赤色のアントシアニン色素がつくられており、葉は緑色から紅色へと変わるのだ。地球全体では春から秋にかけて年間10億トンものクロロフィルが無色で光毒性のない物質に分解されている。このとき、植物はある程度のエネルギーを消費してまでクロロフィルを分解する理由はなぜだろうか(クロロフィルの分解物は再利用されずに棄てられる)。実は紅葉の際、植物は落とす葉の栄養分(特に光合成器官などのタンパク質)を自身の酵素によってアミノ酸にまで分解し、回収する。この際クロロフィルが遊離すると、光毒性によって分解酵素が破壊され回収ができなくなる。そこで、落葉前にまずクロロフィルを分解して無毒にするのではないかと考えられている(図2)。

(図2) 被子植物におけるクロロフィル分解のメカニズムの概念図と代謝経路
被子植物においては、クロロフィルは数段階の反応を経て無色・無蛍光の化合物に変化する。
ところで、現在の地球上の光合成の約半分は、海洋や湖沼などの水圏環境で行なわれており、主に微細藻類が基礎生産を担っている。酸素を発生させる光合成生物のうち陸上植物(コケ・シダ・種子植物)を除いたものを藻類と呼び、これにはワカメやコンブの他、色素体をもつプロティスト(原生生物)(図3)や原核生物のシアノバクテリアも含まれる。藻類の中でも体サイズが小さい微細藻類は単細胞体制で、寿命も比較的短いので、落葉植物のように養分を回収する必要がなく、クロロフィル分解も必要ないと考えられてきた。しかし、水底の堆積物の中からは水中の藻類のバイオマスに相当するだけの大量のクロロフィルは検出されない。藻類の持つクロロフィルはいったいどこにいったのか。この地球上の半分のクロロフィルの消滅過程はどうなっているのだろう。それを知りたいと考えた。

(図3) さまざまなプロティスト
単細胞の真核生物。ここで話題になっている微細藻類もプロティストのなかまであるが、多くのプロティストは色素体を持たないため、外部から餌を取り込む必要がある。(左:微細藻類を飲み込むプロティスト 中央:ミドリムシ 右:ゾウリムシ )
3.シクロエノールに変えるプロティスト
私たちは、水圏環境中のクロロフィル分解過程を理解するため、水試料や海洋・湖沼の底泥に含まれる色素分解物を調べ、シクロエノール(132,173-シクロフェオフォルバイドaエノール)色素が大量に存在することを発見した。この色素は以前から知られていたが、分解されやすく分析が困難であるため、自然界における実態やその存在理由はわかっていなかった。そこで、分析法を改良したところ、シクロエノールはあらゆる水圏から見つかることがわかったのだ(図4)。過去の研究に、節足動物の排出物からシクロエノールのような化合物が検出されたという報告があったので、まず、ミジンコに微細藻類を与え排出物を分析したがシクロエノールは確認できなかった。過去の実験から見つかったシクロエノールは節足動物の餌となる生きものに含まれていたのではないかと予想した。

(図4) さまざまな場所で見つかるシクロエノール
そこで、単細胞生物で微細藻類を食べるプロティスト(原生生物)に注目した。プロティストに微細藻類を与えその排出物を分析したところ、餌の微細藻類が持つクロロフィルはほぼ消失し、代わりにシクロエノールが蓄積していることがわかった。同じ実験をバクテリアにも行なったがシクロエノールは全く検出されなかった。さまざまな系統距離にあるプロティストを用いて実験を続けると、多様な分類群(しかしすべてではない)でシクロエノールをつくり出していることがわかった(図5)。次に、プロティストが鎖状の微細藻類を食べる様子を、蛍光顕微鏡を用いて追いかけたところ、完全に飲み込んで10分ほど経つと、色素体のクロロフィル蛍光がひとつずつ消えていった(図6)。周囲の「生きた」微細藻類の蛍光には何も変化がなかったので、この消失がプロティストによる捕食と関連していることは明らかだった。また、観察の際、微細藻類の蛍光の消失が、プロティストの核に近いものから始まることに気づいた。プロティストはリソソームによって核膜付近の小胞体から運ばれる酵素によってクロロフィルを分解していると想像できる。
クロロフィル蛍光の消失とシクロエノール合成の関係を見ようと、私たちは純粋なシクロエノールを有機合成し性質を調べた。蛍光は、「酸素にエネルギー移動を起こして一重項酸素を発生させる色素の性質」と密接に関わる現象である。クロロフィルやその誘導体である様々な色素は基本的に赤い蛍光を示すのに対して、シクロエノールが全く蛍光を発しないというのは、エネルギー移動がおこらず、一重項酸素が発生していない可能性を示す。私たちは、微量の一重項酸素を検出できる特殊な蛍光指示薬で調べたところ、クロロフィルやほかのクロロフィル分解物では一重項酸素の発生が有意に検出されたが、シクロエノールでは全く検出できなかった。こうして、水圏のクロロフィル分解の正体を捉えることができた。

(図5)真核生物の全体に渡って存在するプロティスト
様々なプロティストの中から多細胞生物が進化したため、プロティストは特定の系統群を指す用語ではなく、真核生物の全体に渡って存在する。

(図6) 蛍光顕微鏡下での観察
珪藻が完全に飲み込まれた直後から、クロロフィルの蛍光が、ひとつ、またひとつとパタパタと消えていったのだ。
4.生物が光とどう付き合ってきたかを理解する
生命の歴史を考えると、シクロエノール代謝の発明は画期的な出来事だったと言って良い。シクロエノールをつくり出すプロティスト(原生生物)の仲間は水圏環境には大量に存在するが、彼らの細胞は透明なものが多い。そのため、透明なプロティストが微細藻類を体の内に取り込むときは、光が当たりクロロフィルから一重項酸素が発生すれば致命的であるはずだ。しかし、プロティストが問題なく暮らしている一つの理由は、シクロエノール代謝にあると考えられる。この発明によって、プロティストによる藻類捕食が可能となったことで、光の当たる海の中で微生物たちがミクロの食物網を発達させて、多様な生態系をつくり上げることができたのだ。また、藻類の進化にも重要な意味があっただろう。シアノバクテリアを自らの細胞内に取り込んで色素体にしたプロティストの子孫は一次植物と呼ばれ、緑藻(陸上植物につながる系統)、紅藻、灰色植物がある。一方、一次植物を共生させた生きものは二次植物と呼ばれ、真核生物の様々な系統群に散らばって存在している。興味深いことに、すべての二次植物に近縁のプロティストがシクロエノール代謝を行なうのだ。それは、かつて微細藻類を補食していたプロティストが色素体を維持するようになり、二次植物に進化したことを意味するのではないだろうか。藻類の進化とシクロエノール代謝の関係は非常に興味深い。
光合成というしくみが地球生命体の中で進化して以来の地球上の生きもののほとんどは、太陽から届く光が欠かせない存在と言ってよい。水圏生態系で生み出された酸素が大気上層に到達することでオゾン層が形成され、危険な紫外線を遮蔽して地球生命圏は陸上に向かって本格的に発展できるようになった。しかしそれは、クロロフィルが捕捉した光のエネルギーによって水を酸化して分子酸素を発生させ、かつその酸素からクロロフィルが生み出す一重項酸素にさらされるリスクを抱えての光合成生物の営みの継続の結果なのである。シクロエノールの発見は、生命の歴史の紆余曲折の一つを考える突破口になったと思っている。

(図7)酸素発生型光合成生物と従属栄養生物の変遷
シクロエノールを起源とする分子化石が過去の水圏の堆積岩から見つかり、網羅的に研究されたわけではないが最古の記録はジュラ紀(1億9900万~1億4500万年前、図のピンク色実線の部分)まで遡る。プロティスト(単細胞真核生物)は約20億年前に誕生し、ジュラ紀頃かそれより前にシクロエノール代謝を発明したのだろう。シクロエノール代謝によって、水中での物質循環やエネルギー循環が飛躍的に向上したと考えられ、地球環境に大きな影響を与えたことは間違いない。
参考
Johnston et al. (2009)
Falkowsky et al. (2004)
『地球と生命の進化学―新・自然史科学1』北海道大学出版(2008)

柏山祐一郎(かしやま・ゆういちろう)
2007年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了。博士(理学)。海洋研究開発機構JSPS特別研究員、筑波大学JSPS特別研究員、立命館大学グローバル・イノベーション研究機構のポスドク研究員、JSTさきがけ研究者(専任)を経て2013年より福井工業大学工学部環境生命化学科講師およびJSTさきがけ研究者(兼任)。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)