
TALK
動きと関わりが生命を続かせる
1.小さなジャンプ
中村
今年の動詞で考えるテーマは「続く」です。一生懸命続こうとしているのが生きものだと言えますが、最近の風潮では遺伝子を渡すことが続くことだという見方が主流です。私も分子生物学の出身ですから、まずは遺伝子を基本に考えてきましたが、生命誌に取り組む中で、遺伝子に還元してしまうと本質が見えなくなると思うようになりました。生きものは個体発生を経て生まれ、代謝によって活動し、その結果として次の世代に続いていく。その過程を見なければいけません。そこでは確かに親から子へとDNAが渡されて、そこで起きた変化が進化となるわけで、DNAに注目する必要はありますが、DNAを渡すことを中心に置くのは適切ではないように思えるのです。そこで、個体が生まれる創出を支えるオートポイエーシスというシステムで生きものを捉えていらっしゃる河本さんと「続く」を考えていくための切り口を話し合いたいと思ったのです。
河本
「続く」というとどのくらいの範囲で考えればよいのかな。色々な話が入るテーマですよね。
中村
始めから規定せずに考えていることをどんどん話して下さい。それについて質問したり、疑問を呈したりしていきたいと思いますので。
河本
 まずは「区切る」ということがイメージされますね。時間軸はアナログで続いているわけですが、自然界ではアナログに流れることは稀で、すべてデジタルでどこかに区切りが入っています。リズムの問題です。もう一つ、区切るというと普通は空間、内外の区切りを思い浮かべますが、自然界にはまた、内と外を区切らなければ自己展開ができない系があるのです。
まずは「区切る」ということがイメージされますね。時間軸はアナログで続いているわけですが、自然界ではアナログに流れることは稀で、すべてデジタルでどこかに区切りが入っています。リズムの問題です。もう一つ、区切るというと普通は空間、内外の区切りを思い浮かべますが、自然界にはまた、内と外を区切らなければ自己展開ができない系があるのです。
中村
生きものがまさにそうですよね。リズムも内外の区切りも。
河本
一つの系が内と外に領域化されると、閉じこめられたことによって系がもともと持っていた運動の状態が変化します。細胞膜がそうですね。二重膜をうまく閉じて、内側の塩濃度を上げていくと、内と外の塩濃度に落差が生じて、外とは違う状態ができあがる。開いたままでは生命は生まれなかったでしょう。
中村
領域に生まれた特有の運動が続いているということが生きているということだと言えばいいのかな。
河本
運動能力と同時に生まれたもう一つの重要な能力が認知能力、つまり内と外を感じとる能力でしょう。感覚は触覚が基本で、触覚は最初は衝突作用のような形で現れたのでしょうね。
中村
外との関わりの始まりは接触、相互作用ですね。触覚と言うと、主体的に対象に触れるイメージになりますが、接触と考えると関係の始まりをイメージできます。その場合、接触を感じとるしくみが内にあることが大事だと思うのですが。
河本
ええ、閉じた系の中に外を感じとるしくみがなければいけません。物性のレベルの「続く」は、力学的な相互作用によって与えられた運動量を別の運動量に変換していくだけですが、生きものの場合はその個体に特有の何かがあると思うのです。
中村
生きものという具体が続いていくのであって、単に運動量が継続しているわけではありませんから。
河本
運動量保存の法則としては何も変化していなくても、閉じた系の中では接触の度に変化が起こり、それは記憶として蓄えられていきます。接触における感触のような記憶です。神経細胞を用いた記憶とは別に、金属疲労のようなしくみの、物としての記憶があると思うのです。
中村
なるほど。今、生物学ではDNAやタンパク質を扱いますが、それぞれをバラバラに観察しても、物質の連なりが延々と見えるだけで、生きものの「続く」を支えるしくみはなかなか見えてこないんです。生きものを分解しても物質しか出てきませんが、物質が集まって生きものになるには、ちょっとした変化でその後を大きく変える「小さなジャンプ」があるはずです。内と外を区切ることはまさに1つ目のジャンプです。領域化によって運動を閉じこめ、閉じこめられた運動が変化しながら続いていくわけですから。さらに接触が起きて記憶が蓄えられていくことが2つ目のジャンプかなと思いました。「続く」を考えてきた時に出てきたこの2つのキーワードから生命の基本を定義できるとお考えですか。
河本
うーん、難しいですね。46億年前の初期条件の結果、たまたま現在のような地球があり、そこに生命体があるわけですが、当然それとは違う条件で暮らす生命もありえますね。「区切る」と「接触」は地球外の生命にも当てはまる条件です。生きものがなぜDNAやRNAのような高分子を活用したのか、これは偶然でしょう。
中村
DNAやRNAでなくてもよいでしょうが、私たちはそれを持ち、それを基本に生きているので、そのはたらきとして見ていくほかないわけです。ですから、そこから離れて、生きものが続くというダイナミズムは「区切る」ことで生まれたという捉え方には、なるほどと思いました。
河本
区切るというはたらき自体はそう難しいことではなく、ちょっとしたきっかけで起こると、またたく間にあちこちで区切りが生まれ、それらが衝突することで接触が始まる。区分と接触という2つの条件さえおさえておけば、事実を整理するのに非常に見晴らしが良くなると思います。内外を区切ることは、オパーリン(註1)の化学進化説につながります。
中村
地球に限定して考えても、海という環境下では内と外を区切る状況が化学的に起こりやすいことは確かめられています。私の先生である江上不二夫先生(註2)はマリグラヌールという膜で包まれたものを作り出されたんです(註3)。もっともこれは続く能力はもっていませんが。内と外を区切り、運動の状態を差異化して、それを繰り返し続けることが私たちが生命と呼んでいるものの基盤だとすれば、それをどうゲノムDNAに繋げて理解していくのかはこれからですが、生命の誕生を特別なものとは考えずに、よく起こりえる状況の中でたまたま起こった結果と考えることはできますね。
(註1) オパーリン【Aleksandr Ivanovich Oparin】
(1894-1980)
ロシアの生化学者。化学進化の一段階であるコアセルベート説を提唱。
(註2) 江上不二夫
(1910~1982)
生化学者。核酸構造研究から日本における分子生物学の基礎を築いた。
(註3) マリグラヌール【marigranule】
1976年、柳川弘志・江上不二夫が発見した原始細胞モデルの一つ。アミノ酸からなる混合物を高濃度の金属原子を含む人工海水中で4週間105℃に保ち反応させると直径0.3~2.5μmの球状の構造体を生成する。
2.非可逆世界への戦略
河本
「続く」という現象に対して、記憶は決定的な役割を担っています。プリゴジン(註4)が『混沌からの秩序』で解き明かそうとしたのは、なぜ自然界には非可逆性があるのかという問題でした。力学的な可逆世界は続いているように見えても、常に元に戻る可能性を含んでいます。
中村
物理学では可逆の時間を教えられるけれど、自然界の時間の流れ、日常の時間の流れは非可逆ですからね。
河本
自然界は非可逆であることを前提に考えれば、あらゆる現象はエントロピーとして計量できますが、ではなぜエネルギー保存則が満たされているにもかかわらずエントロピーが増大していくのか。物質の性質を粒子のレベルで統計的に計算しようとすれば力学になり、力学的なものが非可逆になる理由はありません。プリゴジンはそこが解けなくて、ついには粒子の一つひとつが過去と未来を見分けていると言い始めたんですよ。苦し紛れのようですが、個々の粒子に認知能力がなければ、自然界に非可逆性は出現しないと仮定するところから内部観測(註5)が出てきたのです。
粒子の認知能力を人間の高次の認知能力と混同するとオカルトになってしまいますが、物性の認知能力は人間の意識で捉えられる能力と関係なく考えることができ、記憶とは、それによって未来と過去を区分できる能力と言えるわけでしょう。
中村
 物性の一つを記憶と呼んだのですね。生物学者としてその気持ちはわかります。認知という言葉は本来の定義を外れて様々な分野で使われていますが、ずいぶん昔、分子生物学の人が分子の世界、大腸菌の世界で環境を認知すると言って、脳研究の人に怒られたことがあるんです。“recognition”という英語なんですね。それは分子にも使われていたのに日本語で認知と言うと特別のものとされて。日本語での科学用語の難しさです。粒子も、細胞も、バクテリアも、それぞれに記憶があると考えるのは、大事な切り口だと思います。
物性の一つを記憶と呼んだのですね。生物学者としてその気持ちはわかります。認知という言葉は本来の定義を外れて様々な分野で使われていますが、ずいぶん昔、分子生物学の人が分子の世界、大腸菌の世界で環境を認知すると言って、脳研究の人に怒られたことがあるんです。“recognition”という英語なんですね。それは分子にも使われていたのに日本語で認知と言うと特別のものとされて。日本語での科学用語の難しさです。粒子も、細胞も、バクテリアも、それぞれに記憶があると考えるのは、大事な切り口だと思います。
河本
日常の動作をほとんど無意識のうちに行えるのは、触覚的な認知能力によるものです。頭で考えなくても、身体の記憶によって自ずと足を動かして歩くことができる。記憶から始まったある種の認知能力の領域もまた、「続く」を支えているのではないでしょうか。
非可逆の世界では運動の継続に限界がある。やがては止まるという条件下に置かれた時に、最初に出す戦略が反復の活用です。区切りを入れて、一つを終わらせることで次を作っていく。反復は遺伝や複製よりずっと手前で起きたことだと思います。
中村
生きものにとって、反復はとても基本的なキーワードです。塩基配列を調べると繰り返し配列が本当に多い。ヒトの場合、ゲノムの半分はそれです。意味があるとかないとかいう以前に、とにかく反復することへのこだわりを感じます。反復は生きていることの「くせ」のようなものと思っていたのですが、区切って反復することが私たちの「続く」を支えていると考えれば整理ができます。
河本
 反復に周期性が出ると、それはリズムになるわけです。リズムは運動を伴い、自分自身をリズムに乗せると同時に特定の状態に変化させます。雨上がりのブヨの群れを想像してください。個々の動きはバラバラでも、ひとかたまりの集団を形成していて、手で振り払うとパッと乱れますが、間もなく元の集団に戻るでしょう。ブヨは自らを領域化しながら他と同期するしくみを持ち、少々の撹乱に対しても連動を回復することができる。視覚的な認知とはまったく違って、リズムによって動きながら他と同期しているわけですよね。
反復に周期性が出ると、それはリズムになるわけです。リズムは運動を伴い、自分自身をリズムに乗せると同時に特定の状態に変化させます。雨上がりのブヨの群れを想像してください。個々の動きはバラバラでも、ひとかたまりの集団を形成していて、手で振り払うとパッと乱れますが、間もなく元の集団に戻るでしょう。ブヨは自らを領域化しながら他と同期するしくみを持ち、少々の撹乱に対しても連動を回復することができる。視覚的な認知とはまったく違って、リズムによって動きながら他と同期しているわけですよね。
生きものって、偶然の暴力に対しては非常に弱くて、あっという間に絶滅しますね。そこで、生き延びるために選んだ手段の一つが多重性だと思うんですよ。集団を大きくして孤立しないようにするとか。
中村
誰かが生き残ればいいだろうという考えですね。
河本
これ大きいですよ。20万年前にアフリカで誕生した人類(ホモ・サピエンス)も、相当な個体群となって世界中に移動していかなければ、幾度も訪れた絶滅の危機を乗り越えることはできなかったでしょう。進化とは生き延びると言うことです。生き延びるためには、大量に飲み食いすること、逃げ足が速いこと、生殖能が高いこと、この3つの要素さえ満たせば何とかなります。ブヨは個体の機能だけでは対応できない外的な危機を、リズムによって集団を作ることで解消しているわけで、生きものの知恵ですね。
中村
続くという言葉は平らな連続性を思わせますが、生きものの場合、区切りとリズムというめりはりをつけることが、続くことを支えたのだという考え方は確認しました。
河本
アナログに続く物理量の時間軸にデジタルな区切りを入れ、生きていくための単位を作ったわけですね。例えば竹の節やヒトの脊椎を見ても、自らを区切って単位化し、それを足場に反復を繰り返すことで、形を作っていますよね。物理学者からはフラクタル(註6)の繰り返しに過ぎないと片付けられてしまうかもしれませんが、当事者にとっては運動を続けているわけです。運動には始まりと移行期と終わりがあって、自分自身を単位化するためには、常に自分の終わりを作っていかなければいけない。
中村
終わりがあることは重要ですね。区切ることは、終わりを作ることですが、それによって次に続きます。日常的には世代交代がイメージされます。自分が死に、次の世代が続くという風に。
河本
単位化は非可逆世界への適応形態なのでしょう。
中村
非可逆にこそ、生きものの面白さが出てくると受け止めることですね。
(註4) プリゴジン【Ilya Prigogine】
(1917-2003)
ベルギーの化学者・物理学者。散逸構造理論の研究によって1977年にノーベル化学賞受賞。自己組織化の枠組みを再編し、複雑系科学へ大きな影響を与えた。著書に『混沌からの秩序』(1987年、みすず書房)等がある。
(註5) 内部観測
複雑系科学の概念で、システムの一要素がシステムの現象を観測すること。観測者はシステム内にいるため、観測行為がシステム内の現象を変える可能性がある。
(註6) フラクタル
部分と全体とが同じ形となる自己相似性を示す図形。
3.次元をひらく形づくり
河本
現存の生きものを手掛かりにどこまでが生命なのかを定義しようとすると、今の生きものの特徴を中心にして、例えば原核生物は下等であるというような序列化をしてしまいがちですが、それは大きなところでの可能性を狭めてしまうと思うのです。今、人間が地球上で見ている生きものが生命の典型かどうかわかりませんが、もっと自由度のある変数を入れて生命をイメージした方がいいと思っています。
物理学では形態を三次元で表記しなければいけませんが、生命体は絶対に三次元には書き込めません。整数次元で無理矢理に生命体を捉えようとすると、記述の限界が対象の理解に制約をかけてしまう。
中村
難しい問題ですね。17世紀に西洋に誕生した自然科学はこれまで物理学を基本にしていましたが、生命を基本に自らを変えていく時期にいるのかなとは思い、科学の見方や定義はどんどん変わっていくものだと思っています。さてそこで、「整数次元では生命体は考えられない」ということの意味を具体的に説明してください。
河本
 単純な例として、人間は一応三次元の立体です。その表面を求積法(註7)によって円や四角といった面で埋めようとした時、人間くらい複雑な立体だと埋まらない部分が出てきて、埋まらない部分をさらに円や四角で埋めていくと無限になってしまう。二次元の求積法で複雑な立体を把握しようとすると、三次元に達する手前に無限の量が出てきて解は求められないことから、二次元と三次元の間には別の次元があると推測できるのです。
単純な例として、人間は一応三次元の立体です。その表面を求積法(註7)によって円や四角といった面で埋めようとした時、人間くらい複雑な立体だと埋まらない部分が出てきて、埋まらない部分をさらに円や四角で埋めていくと無限になってしまう。二次元の求積法で複雑な立体を把握しようとすると、三次元に達する手前に無限の量が出てきて解は求められないことから、二次元と三次元の間には別の次元があると推測できるのです。
中村
二次元から三次元へと連続的に次元が続いているということ?
河本
変換をかけると2.6 次元とか2.85次元と言った、幾つかの決まった次元が出てくるはずです。
中村
何でもありでベタッと続くわけではないのですね。
河本
そうです。求積法で割り出すことのできない無限量が、可付番無限(註8)なのか非可付番無限なのかによって次元が異なると考えられます。同様に生命を考える場合も、整数次元以外の次元が設定可能なことを念頭に置いてアプローチすべきです。
中村
そうした次元は生命体に特有なのですか。
河本
少しでも複雑な物体には必ず出てきますよ。ここにある湯飲み茶碗程度なら微分幾何で計算できますが、内外の区分を持ち、自ら内側に陥没するような有機的な形態に微分幾何は適用できないので、整数次元になりません。
中村
整数次元ならば、日常でも時間を入れた四次元までは思い描けますが…難しいですね。
河本
生命は三次元と四次元の間に多くの次元を作ります。中村先生ぐらい複雑な形を作ろうとすると、その過程で非常にたくさんの次元が出てくると思いますよ。
中村
たくさんの次元を作るのが生命。めんどうくさいこと言うなあ(笑)。
河本
観点が増えたからそう聞こえるだけで、生命であることには変わりありません。三次元や四次元に留まらず、細かな次元数を追っていかなければいけません。
中村
生きものの形づくりにもそうした見方が入るのでしょうか。
河本
個体発生は自らの内と外を区切り、体を折りたたんで次元の多重化を行っています。次々に次元を張り出すことで自分自身の領域化を行っているのです。
中村
先回対談をした倉谷さん(註9)が、発生生物学は形づくりであるとして研究をしているのですが、それは次元を作っているという言い方ができるわけですね。とすると、例えば人間ならばみな同じ次元を作っているのかしら?
河本
ええ、人間ならホモ・サピエンスの次元を作る仲間ですね。より細かい次元が計算できるようになれば、例えばよく似た形のオウムガイを比較して、三次元の端数が異なっていればそれは種が違うということがわかるようになると思います。種の違いは次元の違いであり、種の分岐は世界の接点がポンと欠けてしまうような出来事です。
中村
できあがっていく過程を次元の変化と考えるのはおもしろいですね。
河本
形づくりの過程で新しい構造が生まれる可能性もあって、今日はそれを体験できるものを用意しています。
中村
 きれいですけれど、次元を教えてくれるものなの?
きれいですけれど、次元を教えてくれるものなの?
河本
触ってみてください。
中村
あっ、小さな球が大きな球に変わった。なるほど。
河本
パズル作家の柳瀬順一が考案した「ジュノ・スピナー」という作品で、12面体に変換をかけると20面体の像が現れるんです。これによって、12面体の中に20面体が埋め込まれていることがわかったんです。
中村
えっ、12面体の中に20面体が埋め込まれている?
河本
多面体は互いに内包関係にあって、ケプラーの多面体の場合、一番内側に正四面体を含み、外側に向かってどんどん面数が増えていきます。僕も詳しくは説明できないのですが、多面体に変換をかけると、軸の張り出し方が変化して、それまで見えなかった像が次々に現れてくるのです。
中村
ケプラーの多面体が面数を増やしていくと球形になるという変化はわかるけれど、12面体の中に20面体があるというのは何だか不思議。
河本
そうした自己組織化が自然界に本性的に備わっているとすれば、自然界には発見の場所がたくさんありますよね。
(註7) 求積法
面積、体積を求める方法。不定積分を有限回行うことによって微分方程式の解を求める。
(註8) 可付番無限
1.2.3…という自然数の番号を対応することができる数字の無限。
(註9) 倉谷滋
1958年生まれ。理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター創造的研究推進プログラム形態進化グループディレクター。
生命誌トーク57号「形づくりが語る進化の物語り」参照。
4.進化は選択の繰り返し
河本
 生きものを非可逆に持続しながら分岐を繰り返す系と考えると、常に運動を続けると同時に、自分自身にとっての選択肢を生み出すという2重のはたらきを行っている可能性があります。これがオートポイエーシスの基本の部分です。細胞は38億年前から続いてきましたが、単に自己複製を繰り返しているだけならば、自然界はこれほど多様な生物で満ちているはずがありません。多様化の分岐点では必ず選択に直面してきたはずです。簡単に言えば、目の前にあるものを食うか食わないか。この状況に対する選択からある種の知恵が生まれたのだと思います。
生きものを非可逆に持続しながら分岐を繰り返す系と考えると、常に運動を続けると同時に、自分自身にとっての選択肢を生み出すという2重のはたらきを行っている可能性があります。これがオートポイエーシスの基本の部分です。細胞は38億年前から続いてきましたが、単に自己複製を繰り返しているだけならば、自然界はこれほど多様な生物で満ちているはずがありません。多様化の分岐点では必ず選択に直面してきたはずです。簡単に言えば、目の前にあるものを食うか食わないか。この状況に対する選択からある種の知恵が生まれたのだと思います。
中村
「さあ、どうしよう」という選択に迫られて知恵が出る。生きものは常に選択に直面して多様化したからこそ38億年続いてきたと言えるわけで、生きものの歴史を考える切り口はいつも多様化にありますね。
河本
特に重要なジャンプは、真核生物において分裂した細胞が接着し、機能分化が起きたことでしょう。複製する機能は一方に譲り、もう一方は多様性を作り出す。単細胞生物の自己複製とは別の回路を持った、いわゆる幹細胞の基本型の出現が面白いですね。
中村
そうですね。細胞と言っても最初に登場した原核細胞と20億年前に誕生した真核生物では階層が異なるわけで、おそらく真核細胞が生まれたことが最大のイベントだったと言えるのだと思います。「続く」という切り口で見ても、新しい方法が生まれてきたわけですから。
河本
では、なぜ多能化した細胞は組織としてのまとまりを保つことができたのでしょうか。機能分化した後に、ひたすら巨大化するという選択肢もあったはずです。今は生きていないだけで、4~5mの大きさの細胞もありえたかもしれない。
中村
現存の生物から言えることは、生物はそこで分化した細胞が集合し形をつくる方法を持っているということで、そこから逆に歴史を見ていくわけです。
河本
なぜ幹細胞性の細胞が出現したのか、そして形の設計にどのくらい制約があったのかを明らかにしなければいけない。
中村
それは私たち生物研究者が一番解きたい問題です。発生生物学や進化学を合わせた進化発生学という分野が出てきましたが、これはまさに生命誌が基本として考えてきたことで、その2点を解こうとして研究しています。いつ何が起きたのかという事実関係はある程度わかってきましたから、今はその基本にある構造を明らかにしなければいけません。生きものが続いていくことを本気で考えると、その構造が最も重要だと思うのです。
河本
原則的なものはさほど多くなく単純に定式化できますが、ある時一挙にあらゆる形態が誕生し、事実が多様化したのでしょう。そうしたアンバランスな爆発の起きた段階がいくつかあるはずです。
中村
生物の歴史では、カンブリアの大爆発などがあり、その場合のゲノムでの変化はどのように起き、形の変化はどのように起きたのかを解いているわけです。この2つの変化は独立に起きていることがわかってきたのが面白い。
河本
爆発が起きるということは、原則の部分から変化しているはずじゃありませんか。変化が生きものの「続く」に欠かせないものだとして、すぐに想起されるのはDNAの変異ですが、爆発で起きた変化は塩基配列の変化とは根本的に違うしくみだろうという感覚があるんです。もう一歩先の変化を考えるためには何をイメージすればいいのか、いつも考えています。
中村
 まさにそこが問題です。分子生物学の研究は、新たな形質の獲得を遺伝子の変異として説明することができるようになり、カンブリア紀よりもかなり前に多様化するための遺伝子を獲得していたことを突き止めました。ところが、遺伝子の獲得と形の多様化には数億年の開きがあるので、その時の環境との関わり、ゲノム全体としての構造変化という、単に塩基の変化ではない変化を考えることが重要です。これが生命誌の生物学的側面の最大のテーマですね。
まさにそこが問題です。分子生物学の研究は、新たな形質の獲得を遺伝子の変異として説明することができるようになり、カンブリア紀よりもかなり前に多様化するための遺伝子を獲得していたことを突き止めました。ところが、遺伝子の獲得と形の多様化には数億年の開きがあるので、その時の環境との関わり、ゲノム全体としての構造変化という、単に塩基の変化ではない変化を考えることが重要です。これが生命誌の生物学的側面の最大のテーマですね。
河本
人間が生きられるのは100年程度ですから、億という単位を物理的にイメージできる人はいないでしょう。年表に区切りを入れて億という単位を示すことができても、それはただ知っているだけで、数億年続くということに経験的な現実感を持つことは難しい。
中村
DNAから生きものを見るという作業を続け、進化を見ていると、数億年という時間が具体的にイメージできる感じはあるのです。ただ、同じ経験をしていない人にそれをどう伝えるのか、そこの表現が難しく、生命誌でもいつも考えています。
研究の結果を数字にして客観的に伝えることは大切ですが、研究者の持つイメージは数字では伝わらない。「語る」という言葉を使っているのはそこなのです。単に事実を述べるだけでなく、感覚の共有を必要とするわけで。
河本
大学は基礎的なデータを集めることと、それに基づいてどういう経験をするかを分けていますが、本当に講義で聞きたいのは、そうした実感の部分でしょう。
中村
著作では伝わらないことを伝える場ですね。だから、顔を合わせて話をするわけですが、話す側がデータや事実を投げるだけでなく、語る必要があるわけです。
5.はたらきかけ合い、続く
中村
ここまで非常にユニークな「続く」の切り口が出てきましたが、どれも受け身ではなく、自ら生み出していくイメージがあります。オートポイエーシスを研究されている河本さんらしい「続く」です。
河本
 オートポイエーシスは、幹細胞を基本モデルに考えると理解しやすい。現実の生命体の中では幹細胞が単独で存在することはないのですが、ある種の理念として単独で存在する幹細胞を設定してみるのです。
オートポイエーシスは、幹細胞を基本モデルに考えると理解しやすい。現実の生命体の中では幹細胞が単独で存在することはないのですが、ある種の理念として単独で存在する幹細胞を設定してみるのです。
幹細胞は様々に変化していきますが、そこで重要なことはこれまで話してきたことと同じく、領域化をして内外の区分をするということです。オートポイエーシスについては多くの人が多様な意見を出しましたが、僕は触覚的なはたらきの延長上ではたらいているものと解釈しています。言語的な定式化で表現しようとすると、自己言及的にならざるを得なくて、ひどく煩雑な説明が必要になるんですよ。でも考えてみれば、自己言及性は自分が自分に関わることでしょう。関わりの基本は触れることなんです。触れるというメカニズムが動きながら生じているものが触覚だということに気づき、それを基本とした信念からこれまで仕事を続けてきたんです。正直に言うと、最近になってようやくオートポイエーシスの理論がなんとかわかってきたという気がしているんです。と言っても、今の理解度は40%くらい、死ぬまでに50%を越えるくらいは行けるかなと思っています。
中村
生命誌の始まりは自己創出。それまでは自己複製こそが生命の基本であると言われ、それで「続く」が説明されていたのに対し、常に創出があり、創出をくりかえすことで続いていくという考え方を出しました。ですから、オートポイエーシス理論は勉強せざるを得なかったのですが、面倒なところがあって…。触覚的なはたらきと言われると、ちょっとわかりそう。面白いですね。
河本
空間的な接触もあるんですよ。僕が「すうっ」と息を吸い吐くと、肺から体内に取り込まれなかった空気は再び空間に吐き戻され、その幾分かを中村先生は吸って体内に入れているわけで、これは唇を使わないディープキスをしているのと同じです。
中村
なるほど、すごいことおっしゃいますね(笑)。
河本
こう言われると疎ましいほどリアリティがあるでしょう。空間的な広がりの中に人間が配置されているような視覚で捉えた世界では、配置したもの同士の接点にそうしたリアリティは感じられないでしょ。ところが実際は、互いにはたらきかけ合っているわけですよ。例えば言葉には、何かを説明するだけでなく、互いを誘惑し合うというはたらきが必ず含まれている。誘惑と言ってトゲが立つなら挑発と言い換えてもいい。言葉は何かを伝えると同時に、その中に挑発を含まざるを得ない。そうした見えないところで続いているはたらきもまた、「続く」を支えていると思いますよ。
中村
なるほど。触覚的な解釈をしていくとやけにリアリティが出るわけね。
河本
情報伝達と言うと情報がつながっているように思いがちですが、伝えるというはたらきの結果情報が残るのであって、続いているのははたらきなんですよ。
中村
それは生きものだからこそですね。機械では情報しか伝わらないけれど、生きものは伝えるというはたらき自体を繰り返して情報を生み出している。
河本
そうです。すべての生きものが持っているものとして遺伝情報は確かに重要ですが、もう一つ重要なのがはたらきそのものが継承されているということです。他に人間の場合は文化情報、いわゆるミームも継承している。人間は建物を建てて、その中で寝起きしますよね。生まれた時から平らな床に寝かされた結果、本人の意思とは無関係に平面とは何かの定義を身体的に獲得してしまう。それは幾何学的な平面の定義とはまったく異なり、寝るという営みを通して継承されるものです。僕たちからは見えにくいだけで、あらゆる生きものがそれぞれの暮らしに即したはたらきを継承していると思います。
中村
 そうね。自然界には平面なんてないわけだから、他の生きものは平面は使っていないわけだ。人間以外の生きものは言語を持たないから、はたらきそのものが見えますね。遺伝情報、文化情報の他にはたらきの継承があるという考え方は確かにおもしろいです。オートポイエーシスの河本さんと思っていたのに、なんだかこの頃身体の動きに入り込んでいるのはなぜだろうと思っていたんです。そこでつながっているんだ。
そうね。自然界には平面なんてないわけだから、他の生きものは平面は使っていないわけだ。人間以外の生きものは言語を持たないから、はたらきそのものが見えますね。遺伝情報、文化情報の他にはたらきの継承があるという考え方は確かにおもしろいです。オートポイエーシスの河本さんと思っていたのに、なんだかこの頃身体の動きに入り込んでいるのはなぜだろうと思っていたんです。そこでつながっているんだ。
河本
遺伝情報とも文化情報とも違う、はたらきこそが、本当は生命に特有なものだと思います。
6.生きるために
中村
はたらきということで言うなら荒川修作さん(註10)。河本さんも著作の翻訳などで深く関わっていらっしゃるけれど、私も荒川さんからはたらきかけがあり、どこかに接点ありと思いながら言葉ではなかなか共通のものを見つけられなくて、お互いにちょっともどかしいのです。そこで作られたものに接するのがよいと思って、先日、三鷹の天命反転住宅に行ってきました。赤や黄色に塗られた壁は曲がりくねって、床はでこぼこで、天井にはさまざまなものが吊されている。写真で見る限りはよほど変なところだと身構えて行ったのですが、実際は気を衒っているところもなく、私にとっては非常に居心地のよい場所でした。
河本
居心地のよさの中には何がありましたか。例えば新鮮さなど。
中村
それが、あれだけ普通の家と違っているのに、新鮮さは感じなくて、自分の部屋にいるのと同じように違和感なくぴたっとはまったんです。部屋の使用法もあれこれ説明されましたが、そんなことはどうでも良くなって、ただ居ることが心地良かったのです。河本さんが最初訪れた時はどうでした?
河本
僕は三鷹の住宅の構想段階から荒川さんとさんざん話し合って、施工中も何度も通いました。実現はできなかったけど、廊下を歩くと前方から足音がやってくる装置も考えましたよ。あの頃の荒川さんは奇妙奇天烈な人と思われていましたが、今は時代の中心人物ですね。先日、日本病跡学会の講演に来てくれた時、医者に向かって「君たちは病人を治していると思っているだろうが、病人とは君たちのことだ」と言うのです。すると医者が「ああ、やっぱりそうなのか」とうなずく(笑)。
中村
荒川さんは変わっていませんから、時代が変わったのでしょう。住宅の屋上の花壇に水をまくには梯子のような垂直の階段を登らなければいけないでしょう。私は高所恐怖症なので遠慮しましたが、でも花の命がかかっているわけで、こちらも命がけにならなければいけないのかもしれない。
河本
3階建てのマンションでは労力を省くためにエレベーターが設置されていますが、荒川式住宅は、労力に見合うだけの面白さを提供すれば3階まで登れるという発想で作られています。省エネや環境保護のように抑える発想ではなく、面白さを運動エネルギーに変換させるのです。
中村
確かにあの住宅は身体に働きかけるところがありますね。座っていても動きたくなる呼びかけを感じます。
河本
建築は三次元の座標軸を張り出し、柱や天井でそれを区切ることで設計しますが、あの住宅は生命体のようにユニットをつないでいくだけ。柱を持たない球や箱の形をしたユニットの継ぎ足しはゲーテの原型を思わせます。
中村
構造自体が生きもの的ですね。
河本
住宅には何時間くらいおられました?
中村
 何時間くらいでしょう。とても居心地がよくて、招いてくれた友人たちと何時間もおしゃべりしていました。私は片付け魔ですっきりした所で暮らすのが好きなので、すべてのはたらきが形として表に出ているあの場所での住み方はできるかな、と思います。建物のあらゆる部分に荒川さんの生きもの的な気持ちが出てきていて、慣れた場所にいるように感じました。電気のスイッチも場所によって色々な高さにあるでしょ。でも、「なるほど、ここか」と思わせる場所にあるから不思議じゃないんですよ。
何時間くらいでしょう。とても居心地がよくて、招いてくれた友人たちと何時間もおしゃべりしていました。私は片付け魔ですっきりした所で暮らすのが好きなので、すべてのはたらきが形として表に出ているあの場所での住み方はできるかな、と思います。建物のあらゆる部分に荒川さんの生きもの的な気持ちが出てきていて、慣れた場所にいるように感じました。電気のスイッチも場所によって色々な高さにあるでしょ。でも、「なるほど、ここか」と思わせる場所にあるから不思議じゃないんですよ。
河本
構想では多くの認知科学者が一緒になって工夫を重ねましたから、あれ以外の形にはならなかったと思います。荒川さんがあの住宅を建てたのは「死なないために」という思いからです。非可逆の世界には必ず区切りがあって、誰もが個体としては始まりと終わりがあることを知っています。ところが、終わりにベクトルを置いた文化がある。死生学は「豊かな死」を雄弁に語りますが、死の間際に最善の努力をするくらいなら、若いうちからそうすればいい。努力の力点を変えるべきです。
中村
その通りですね。荒川さんに「死ぬのは犯罪です」と言われた時はドキッとしたけれど、生きることに努めるべきというのは同感です。今、世の中では死を語る学問が流行して、死を語る方が重要みたいに言われますし、わりあい軽く「メメント・モリ」などと言いますでしょ。あまり好きじゃないんです。個体の死は不可逆の時間を持った生きものが続いていくための戦略ですから。個体としては死にながら、生命としては38億年続いてきたわけで。大事なのは生き続けることです。ですから、荒川さんの「死なないことに決めました」という宣言に賛成です。
河本
人間は長い時間をかけて埋葬儀礼のような宗教文化を形成してきました。死を埋め込んだ文化の堆積から、時代ごとに時々死生学のようなものがポッと出てくるのは、時代の要請もありますが、荒川さんのように正面を切って生きることを主張する人が非常に少ないからでしょう。死を違った形に特権化するのはまずいですね。死なないと決めて手にする選択肢は、死を配慮した生き方よりも、もっと人間の能力を発揮できると思います。
中村
本当にそう。生きることにきちんと向き合う方がよいですね。三鷹の住宅は「続く」を考えるために非常に意味のあるメッセージを持っていますね。


(註10) 荒川修作
美術家。1936年生まれ。パートナーのマドリッド・ギンズと共に、身体感覚を呼び起こす作品を制作する。作品に〈遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体〉〈三鷹天命反転住宅〉、著書に『意味のメカニズム』『死なないために』など。
photo(C) 中野正貴 協力:ギャラリー・アートアンリミテッド
7.総力戦の認知運動療法
中村
ハーバード大学の脳解剖学者のジル・テイラーという女性が記した『My Stroke of Insight』という本を紹介してくださった方があって読んでいるんです。彼女は37歳の時に脳梗塞を起こし、左脳が完全にはたらかなくなるのですが、回復するまでの一週間、高度な神経系が抑制された体験を事細かに分析して記述しているのです。
まず、最初の発作で記憶をなくします。そして、感覚に区切りがなくなり、音は聞こえても人の声と雑音の区別がつかず、見えるものすべては印象派の点描のように均等な色点になってしまう。もちろん話はできませんし、助けを呼ぶための救急車の電話番号もわからない。電話機の側にたまたま知人の名刺があって、そこに印された電話番号と同じ数字のボタンを一つひとつ、どこまでかけたかわからなくならないように数字に×印をつけながら押していって、なんとか電話をかけることができたのです。彼女の体験記は、視覚や聴覚のはたらきが失われても、触覚だけは確かに残ることを正確に分析していてとても面白いのです。
河本
触覚系の感覚は脳研究では体性感覚“Somatic Sense”と言い、皮膚を介した接触の感覚と、尿意や便意のような内感的な感覚の2種類が確かめられています。触覚は視覚や聴覚と同じ五感の一つに数えられていますけれど、これは外部を知るというはたらきに限定された時のことです。実際は身体を動かすと同時に感じとるわけで、例えば腕を伸ばす時の運動感や、指先で押す圧覚のように、非常に多様な力覚のモードがあるのです。
中村
なるほど。動きとの関わり、まさにはたらきですね。
河本
触覚性の力覚は脳梗塞の麻痺からの回復に重要な役割を果たしているんです。喉が動けば色々な音を作って発話したり、手を使って体を移動させたり、自分自身の動きを感じとる能力を活用して環境に応じた身体の動きを作り出すんです。脳のしくみはあまりに複雑で、力覚の研究はまだ全くなされていないんですけど。
中村
力覚は根本的な感覚なんでしょうね。複雑な脳を持つ以前から、続いてきた能力ですよね。ところで河本さんが最近取り組んでいらっしゃる認知運動療法はまさに触覚性力覚の活用でしょ。
河本
 視覚と触覚のギャップの具体的体験を見せますね。目盛りを書いたホワイトボードの前に黒板消しを持って立ち、目を閉じた状態で腕の位置を少しずつ移動します。はい、そこで止めて、目を開けて。今、どの位置で止めたかわかりますか?
視覚と触覚のギャップの具体的体験を見せますね。目盛りを書いたホワイトボードの前に黒板消しを持って立ち、目を閉じた状態で腕の位置を少しずつ移動します。はい、そこで止めて、目を開けて。今、どの位置で止めたかわかりますか?
これは体性感覚、つまり自分の腕がだいたいここにあるという感覚と、視覚で捉えた空間的な配置を一致させる認知運動療法の訓練です。私たちは通常、視覚と体性感覚とによる位置を調整して、釣り合いのとれた状態で体を動かしているんです。足を持ち上げたつもりでも段差につまづくので、思いきり蹴り上げないと階段を登れない人がいるんです。視覚と体勢感覚で捉えた位置にズレが生じているんです。今やった訓練は、知能が高い人ほど間違える傾向にあって、黒板消しを持つのはハンディキャップをつけてるんですが、その重みを計算することで、さらにズレが大きくなってしまうんです。うまくいかなくなって、しまいには怒り出してしまう人もいますよ。
順序と配置の組織化は右脳と左脳が分担しています。脳機能が損傷を受けても、視覚のような高次の認知能力は無事であることが多い。先ほど紹介された脳梗塞を起こした女性の場合も、数字の形を見分けることはできるのだけれど、順序を組織化して配置を組み直すことができないわけでしょ。
中村
一つひとつ何があるかはわかっても、そのように体が動かないんですね。
河本
そうした患者さんに、このホワイトボードの上から3段目はどこかわかりますかと聞くと、わかると答えます。では、そこに手を置いてくださいと言うと、まったく的外れなところを指してしまう。視覚情報を組織化できないんです。
中村
そこで認知運動療法という手法が登場するわけですね。
河本
今、脳卒中で障害を負った人が130万人ほどいます。障害者はそれ相応に行為するのだと見なすのは人間を機械的に見ている。障害を負った人だってよりよく生きたいんです。よりよく生きるというのは、体の動かし方を改善したり、基本的な動作を自分でできるようになったり、さまざまな能力を維持して生きていくことです。
脳に障害を負うと、回復をあきらめてすぐに隠居暮らしを始める傾向がありますが、それはこれまでそうした人が多かったというだけで、治らないと決めつける根拠はない。たとえ脳機能の半分が損傷しても、絶対に治る。治せないのは治療した人が悪いのだ、という固い決意を持って、どう治すかということを真剣に考えなくてはいけないというのがわれわれの立場なんです。
通常のリハビリテーションは命令に従って体を動かす運動訓練ですが、それでは筋肉が少し硬くならない程度の効果しか望めません。障害は脳にあるのですから、脳にはたらきかけるための課題設定をしなければいけません。こうした訓練の基本形は数十個あるんですが、どれも視覚と体性感覚を調和するもので、セラピストの支えを受けながら、世界との関わりを作っていく作業です。
中村
 とてもよくわかります。脳の柔軟さを生かしていけるはずですよね。残っている部分を活用して。
とてもよくわかります。脳の柔軟さを生かしていけるはずですよね。残っている部分を活用して。
河本
認知運動療法の一番の特性は、患者を課題に直面させて、課題に対して患者自らが自分の能力を変化させていくことです。間違えることで本気になり、本気で繰り返すことで脳の神経ネットワークが再生するのです。
中村
やる気になればいいんですね。そうして別の回路をつなげていく。
河本
ええ、学習プロセスが大切です。先ほどの例では、ホワイトボードに書かれた複数の線から自分の体性感覚と一致する位置を選ばなければいけませんでした。複数の選択肢に直面して、自分で考えて答えを出すことが学習の基本です。
中村
そうした課題を考えたのはどなたですか。
河本
イタリアのペルフェッティ(註11)が数十種類の課題を考えたのが始まりです。彼は認知運動療法を最大限に活用して行為能力を形成するために、身体そのものの感覚を作ろうとした。例えば物理的に足があっても、脳の障害によって足の感覚がなくなった場合、硬さの違うスポンジを足に押し当てて、スポンジの硬さを感じ取ることで、そこに足があるという感覚を作るのです。脳に受けた障害は一人ひとり違いますから、その人に最適な課題を考えなくてはいけません。難しすぎても簡単すぎてもよくない、成功率は半分くらいがいいんです。
中村
まさにオーダーメイド医療ですね。ところで、オートポイエーシス研究の河本さんがなぜ認知運動療法に関心があるのか。両方の関係が知りたいんですが。
河本
 なぜ僕が認知運動療法をやっているかというと、これは脳神経科学や身体運動学、現象学のような分野を総動員した学問の総力戦だからなんです。中村先生も50年も総力戦を続けていらっしゃいますが、総力戦って、負担も大きいけれどすごく面白いですよね。少し勉強すると新しい問題がたくさん見えてきて、さらに勉強するとその先にまた問題が見えてくる。これは自分に向いているなと思って、携わっているわけです。
なぜ僕が認知運動療法をやっているかというと、これは脳神経科学や身体運動学、現象学のような分野を総動員した学問の総力戦だからなんです。中村先生も50年も総力戦を続けていらっしゃいますが、総力戦って、負担も大きいけれどすごく面白いですよね。少し勉強すると新しい問題がたくさん見えてきて、さらに勉強するとその先にまた問題が見えてくる。これは自分に向いているなと思って、携わっているわけです。
実は、2001年にイタリアで始まった認知運動療法の研究プロジェクトが治療法にオートポイエーシスを導入したのです。そこで即刻イタリアの研究本部に呼び出され、それ以来、学会の度に声をかけられて、内外の研究者の橋渡しを頼まれています。よくいえば出会い、まあ事故にあったようなものですが、これからも続けていきますよ。
中村
総力戦という言い方いいですね。学問の総力戦であると同時に現場とつながる。事故とおっしゃるけれど幸運な出会いだったと思いますね。生命誌も総力戦。生きものとは何か、どう生きていくかを色々な人と一緒に考えて、楽しみたいと思っています。今日はありがとうございました。
(註11) カルロ・ペルフェッティ【Carlo Perfetti】
イタリアの神経内科医。1970年代に、当時主流であった運動療法に対して学習を重視した独自の認知運動療法を編み出した。
写真:大西成明
対談を終えて
河本英夫
生命が持続するとき、物理的な運動と異なり、そのつど区切りを入れることを基本だと考えてきた。もっとも眼につく区切りは細胞分裂のような世代交代である。だが生命体の造りそのものも、区切りが基本になっている。竹の節や動物の脊椎のように単位を形成しながら、その単位を繰り返し作って成長するような仕組みを、ゲーテは原型とその反復だと考えていた。原型そのものがかたちを変える場面が、メタモルフォーゼである。
生命の最大の区切りは、内外の区分であり、これが最初の区分である。というのもまさにそれによって生命そのものが誕生したと考えてよいからである。その内部が生命の自己である。内外区分によって内と区分されたものに、さらに内外区分が反復的に進行する。内外区分を行うような運動は、三次元空間内の運動とは異なり、むしろ固有空間を形成するような運動である。この区分する運動は、認知的には触覚的感度を必要とする。中村桂子先生との対談は、触覚的感度に溢れ、興味深さを超えて、魅惑的でさえあった。
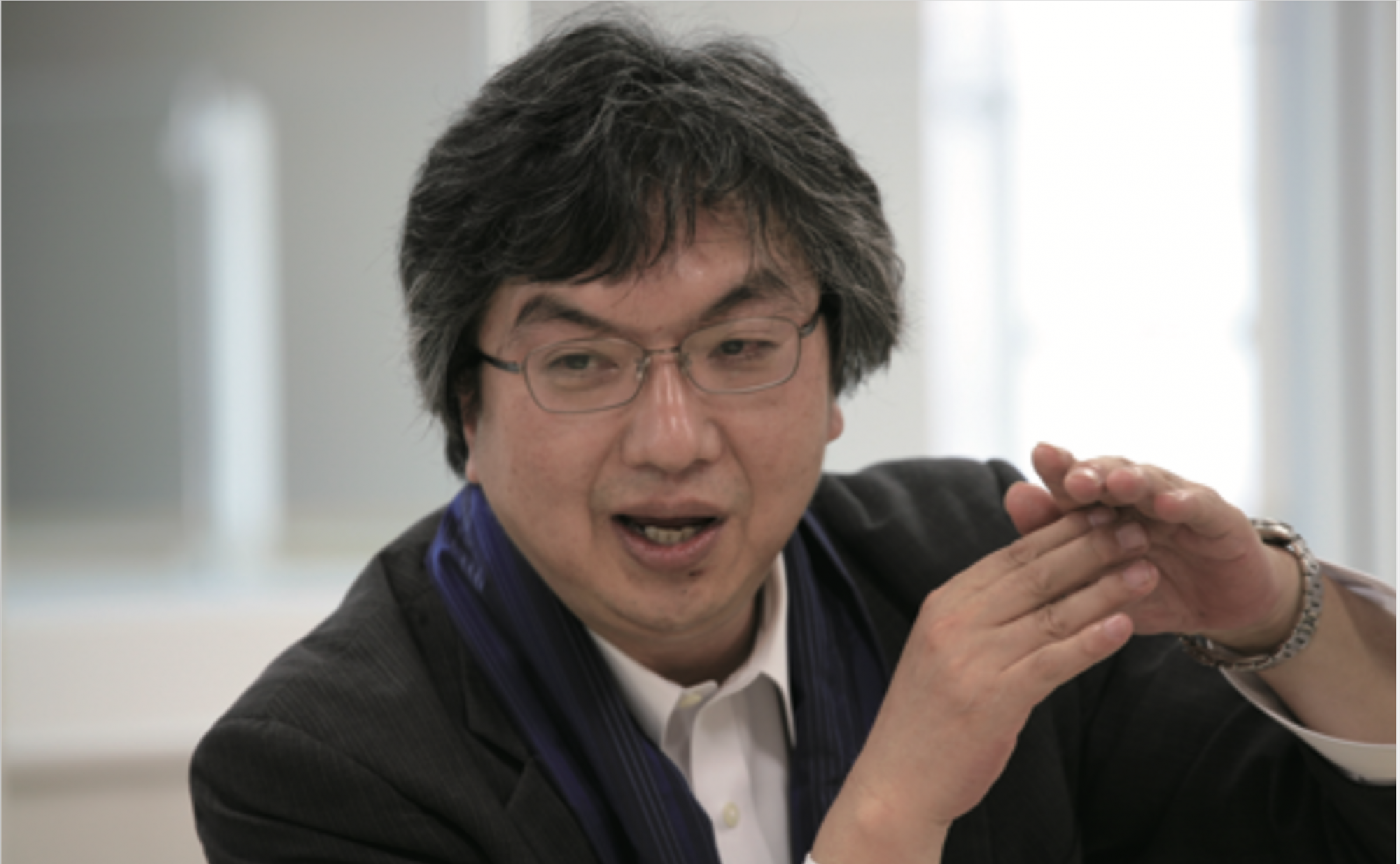
河本英夫(かわもと ひでお)
1953年鳥取県生まれ。東京大学教養学部卒業、同大学大学院理学研究科博士課程修了。東洋大学助教授を経て1996年より同教授。著書に『システム現象学 オートポイエーシスの第四領域』など多数。日本におけるオートポイエーシス研究の第一人者であり、近年は認知運動療法にも携わる。
![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)














