マウスとの出会い
中学生時代の私は、鉱石ラジオを組み立てたり、軍艦の模型を作ったり。ものの仕組みが面白かったのです。東京大学での専攻決定のとき、一度は工学部に願書を出したのに締め切り最終日になって動物学に変更したのも、生き物の仕組みに引かれたのでしょう。生物学者の父親に「食えねえぞ」と言われましたが。
大学院では新進の石田寿老先生の発生生理化学講座に進学しました。1950年代、生化学が盛んになり、先生の講義には先端の知識がどんどん出てきました。丸山工作(前千葉大学学長)、毛利秀雄(基礎生物学研究所所長)、山上健次郎(元上智大学生命研究所所長)、安増郁夫(元発生生物学会会長)など元気な仲間が狭い部屋にひしめいて、実験もし、飯も食い、論文も書くという活気のある研究室でした。
与えられたテーマは、発生過程やさまざまな生物機能とともに、ATP(生物のエネルギーはほとんどこの物質を通して動く)がどう変化するかを調べること。春はヒキガエル、夏はメダカ、秋はウニを材料にしました。自分で採集するので、季節まかせの力仕事でしたが、ATPという当時の先端的なデータから自然集団の挙動を見るのが面白くて、それが後を引いて野生を追いかけるようになったのかなと今になって思います。冬は野生の材料がないので、マウス(ハツカネズミ)の横隔膜を取り出して、細胞膜を通しての水の移動とATPがどう関係しているかを調べました。これがマウスとの初めての出会いです。
ヒキガエルを採って調べているうちに、分類学的には同じヒキガエルなのに、地域ごとに代謝阻害剤に対する反応に違いがあることに気づきました。これは遺伝的変異なのではないかと研究発表会で口にしたところ、「変異を乗り越えて成り立つ現象が大事なので、遺伝的変異などに囚われないように」という講評がありました。DNAの二重らせん構造が発見されてまもないころで、発生学・生理学を標榜する動物学教室では、遺伝が語られることは少なかったのです。
しかし、博士課程を終えるころ、国立遺伝学研究所に行くようにという教授の一言で、その後遺伝学の道に進むことが決まったのです。

78年インドでの学術調査では旗を作った。中央が吉田博士。その左が森脇博士。

マイソール近郊。孤児の援助をしている日本人平和部隊の協力を得て、ネズミを集めた。

中国西寧で。王成懐(蘭州の生物製品研究所所長)と。

93年、浜松。国際マウスゲノムコンファランスを主催した。マウスの遺伝子は6000ほどわかっている。DNAと生き物を結ぶ研究が大事だと森脇博士は考えてきた。
遺伝研へ
59年4月、三島駅から満開の桜並木の坂道を上っていくと、遺伝研の古い木造の建物がありました。戦争中に飛行機を造っていた工場を仕切って顕微鏡を持ち込んだだけで、本当に何もない。暖房はおろか少し前まで水も出なかったという。やめて帰ろうかと思ったほどです。
私を採用したのは、ネズミの染色体の専門家で、細胞遺伝部門の吉田俊秀先生です。マウスやクマネズミの遺伝的な変異を生化学的な方法で探究してくれと言われて、びっくりしました。東大とは逆に、今度は変異のあるほうですから。ともあれ、ここでのネズミとの付き合いが私の研究人生をつくりました。
当時の遺伝研は、木原均先生、酒井寛一先生、若かった木村資生先生などユニークな遺伝学者がいて、自由に議論する雰囲気でした。遺伝学は、メンデルの法則を中心に生物学の中で唯一法則をもっている学問ですから、論理的な議論が盛んで、ここならメカニズムの研究ができると期待が膨らみました。東大では生物の複雑性に悩まされていましたから。
まず、遺伝的に脱毛するマウスの、毛が抜ける時の生化学的な変化を調べました。いくつかの酵素が変動することはわかりましたが、結局、何が先に変化するのかがわからず平行現象です。もっと遺伝子に近い発現機構を研究したいと模索していました。
そうこうするうちに、アメリカの国立癌研究所に行っていた吉田先生が、マウス・ミエローマという癌細胞を持ち帰ってこられました。ミエローマは、γグロブリンというタンパク質を大量につくるので、そのメッセンジャーRNAも大量に出していることになります。このメッセンジャーRNAを取り出し、γグロブリンをつくらない培養細胞に入れたら、その細胞もγグロブリンをつくるようになるのではないか…。この実験が成功すれば、遺伝子の発現とタンパク質の対応がつけられるわけですから、メカニズムを明らかにしたいと思っていた私は、ミエローマに飛びつきました。
しかし、実験は非常に難しく、当時遺伝研にはメッセンジャーRNAを採った人などいませんし、器材もありません。外国の論文を読みながら手探りで実験するしかありません。それでも2~3年の間にデータは出るようになりましたが、再現性が低く、泥沼に入り込んだ感がありました。

日本産野生マウスから樹立した系統。他の実験用マウスに比べて、活発な行動を示す。

北海道手稲山周辺で採取した野生マウス。南方系カスタネウス亜種のミトコンドリアDNAをもつのは、縄文人に付いてきたためかもしれない。

京都市郊外桃山で採取した野生マウス。耳が大きい。
ミシガンへ
64年、マウスの遺伝学で有名なミシガン大学にポスドクとして行くことになりました。マウスの遺伝学をきちんと勉強したいし、アメリカのほうがはるかに施設がよく、能率が上がると思ったのです。
当時はアメリカの黄金時代で、自由な雰囲気。留学生にも親切でした。私の先生はモリス・フォスターというマウスの毛色の遺伝の専門家でしたが、「朝から晩まで仕事ができる時は、もう一生ないだろうから、好きなことをやりなさい」とまったくの自由を与えてくれたのです。日本より格段に整った実験系をつくって、再びミエローマのメッセンジャーRNAを別の細胞に取り込ませる実験を続けました。
2年半のアメリカ生活は、楽しかったけれど、一方では苦しかったですね。自由ということは、全部自分でやるということです。実験だけでなく、ネズミを飼うこと、薬の購入、伝票書きまで。研究室から離れた実験棟に、マイナス20度の中を歩いて行った。そして結局、再現性の高い成果は得られませんでした。今では、ある遺伝子を他の細胞に移すことなど、誰でも簡単にできるんですけどね。私の力不足でしたが、時代も早すぎました。生物は複雑だという意識をもって遺伝研に行ったら、論理的に攻めていけそうな雰囲気だったので飛びついた。それが、生物は単純ではないということにもう一度戻ってしまいました。
アメリカに滞在している間に、この国のもつ科学の奥深い実力を思い知らされました。その後、75年にはアメリカのジャクソン研究所哺乳動物遺伝学コースに参加しました。この研究所はノーベル賞学者を輩出するような高度な研究機関であり、マウス遺伝学の総本山です。一方では多数のマウス系統を開発・維持し、世界中の研究者に分譲する事業を行っています。このコースに、M・ライオン、D・ベネット、G・スネル、O・ミュールボッホなど一流のマウス遺伝学者が講師として招かれていて、私は欧米の学問の蓄積と進歩に感銘を受けました。と同時に、日本で自分にできる研究は何だろうという不安に襲われました。
A : 南からきたカスタネウス亜種群は人と一緒に日本全国に広がった。
B : 北から朝鮮半島を通ってイネとともに渡来した人に付いてムスルクス亜種群が入ってきた。
C : ムスルクスは人の移動とともに中央部を占拠し、カスタネウスは北に押しやられた。
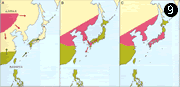
野生マウスに着目
日本で何ができるか?帰国後もずいぶん考えた末、アジア産野生マウスの遺伝学をやってみようと決心しました。ミエローマの仕事で回り道をしてしまったので、もう40歳近くなっていました。
当時、実験用マウスはジャクソン研究所の努力によって、世界の医学生物学研究に盛んに使われており、ヒトの免疫遺伝学もマウスの研究を土台にして発展したといえます。このような重要な実験素材であるにもかかわらず、その遺伝的な起源についてはあまり研究されていませんでした。実験用マウスの起源を調べ、もしそれがアジア産とは遺伝的に大きく離れているのであれば、アジア産野生マウスからは、実験用マウスにはない独自の遺伝子が見つかり、それを使って日本独自の研究ができると考えました。
幸い米川博通さん(現東京都臨床研)という共同研究者に恵まれ、ミトコンドリアDNAを使った亜種分化の分析を進めることができました。その他にも多くの共同研究者の遺伝学的研究のおかげで、現在東アジアに生息するムスクルス亜種群、東南アジアのカスタネウス亜種群、ヨーロッパのドメスティカス亜種群は、それぞれおよそ100万年前に分岐したらしいことがわかり、これらの遺伝的分化を基に、実験用マウスが主としてドメスティカス亜種群に由来することも明らかになりました。
アルビノのネズミが描かれている。
これらの絵から、江戸時代にアルビノのネズミがいたことがわかる。

野生マウスを使った独自の研究
日本産を含む東アジア産野生マウスが、実験用マウスとは遺伝的に大きく異なることがわかりました。ねらい通り、このマウスを使って独自の研究ができる糸口ができたのです。そこで、生化学、細胞遺伝学、免疫学、腫瘍学など、いろいろな視点から探索研究を進めた結果、取り上げた遺伝的特性のすべてに東アジア産マウス特有のものが見つかるといってもよいくらい、新しい遺伝子(対立遺伝子)が見つかりました。
なかでも、東北大学の大学院生の城石俊彦君(現遺伝研助教授)は、減数分裂時に非常に高い頻度で遺伝的組み換えを示すマウスを発見して、その分子機構を解明し、さらにその系統育成をするという大きな業績を上げました。
宮下信泉(現香川医科大学助教授)は、アジア産野生マウスから肺腫瘍に対する強い抵抗性遺伝子を見つけました。実験用マウスが失ってしまった遺伝子が野生マウスから見つかり、その中から生命機能の研究に役立つものが出てくる可能性はまだまだありそうです。
アジア全域の野生マウスのミトコンドリアDNAを調べていた米川さんは、ムスクルス亜種群とカスタネウス亜種群の分布に非常に面白い傾向を見つけました。大陸では中国の長江を境に、北のマウスはムスクルス型、南はカスタネウス型のDNAをもっています。ところが日本ではこれが逆転して、盛岡あたりから北にカスタネウス型、南にムスクルス型DNAをもったマウスが分布している。先に南から入ったマウスを後から来たマウスが北に押しやったという説明ができます。マウスが我々の祖先に付いて移動したと考えれば、日本人は2度にわたって渡来したという埴原和郎先生(元東京大学人類学教授)の説と話が合うのです。意外なことから人類学の研究に役立つこととなり、分野の違う方々とおつき合いすることができて、よい経験となりました。停年後、私は総合研究大学院大学の副学長になるのですが、そこの目指している「総合性」に、この時少しは貢献できたのかもしれません。
野生マウスに関するたくさんの人々との研究は、64年“The Genetics of Wild Mouse”として出版されました。
研究の基盤としての支援
マウスの研究をしているうちに、遺伝研の系統保存事業に深入りすることになり、ついには実験動物学の分野にまで浅くない縁ができてきてしまいました。そのことで苦しかったのは、研究室の実績も上げながら、大学共同利用研としての系統保存事業を進めなければならないことでした。研究者が系統保存の実務に忙殺されるようでは、研究どころではなくなります。しかし、その生物の研究をしている研究者がそばにいなければ、系統保存事業を高いレベルに保つことは難しい。高度の研究支援を受け持つ人たちを優遇し、その社会を確立することが、奥行きの深い独創的な生物学を生み、科学全体を発展させるのに重要だというのが、系統保存事業に関わった私の実感です。
ユニークな生物学研究を進めるには、独自の系統生物から見出した新しい知見をもとにしなければなりません。日本もこのあたりで、この基盤をつくることに本腰を入れないと、いつまでも西欧のオリジナリティーの後を追うことになると思うのです。






