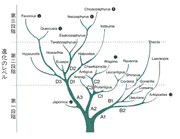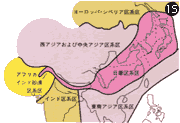15歳未満
精神年齢は15歳未満・・・。折々にそう思ってきたし、今もそれは変わらない。子供時代の虫捕りをいまだにやっているのだから。
大学の研究室での四十余年、その後も含めると60年間、チョウに打ち込んできた。まずは、日本とその周辺地域にどんな種のチョウが産するか、その形態と識別、各種の生活史、幼虫の食性、地理的分布状況などを明らかにしようとした。日本の大学で、本格的にチョウをテーマにしたのは、私が初めてだと思う。昆虫学者は多い。だがチョウでは「食え」ない。大発見も大論文も、チョウでは直接人間の生活に役立たない。食うためには、害虫の研究など、実利的分野に転向せざるを得ない状況がある。事実、「チョウの研究などばかげている」という疑問をぶつけられたりもした。
しかし私は、「文化」とはそういうものだと考えている。生活に役立つかどうかという次元とは別ものだ。さまざまなことに情熱を傾けることが許されるのも、社会の豊かさの一つである。チョウと縁を切り、実利的な研究に転向することなど、考えもしなかった。研究生活を振り返って、幸いだったと思いこそすれ、悔いはない。
尋常小学校時代。上から2列目の左から3人目が白水博士。
運命の出会い―本と人と
1917年、福岡市一番の繁華街の商家に生まれた。小学校入学前に亡くなった父は動物好きで、その血を引いたのだろうか。とにかく虫が好きだった。虫がめったにいない環境だったために、郊外や農村育ちの子供たちより、かえって虫に強い興味を覚えたのかもしれない。
小学校3年の頃、隣家の1年上の子に誘われて、昆虫採集を始め、標本も作れるようになって、いっぱしの虫屋が誕生した。その頃、『虫の絵物語』(横山桐郎著)を繰り返し読み、台湾のチョウや国蝶のオオムラサキの美しさに、ため息をついた。
中学へ入学直後、本屋で『原色蝶類図鑑』(山川黙著)と出会った。チョウの原色写真と名前。世の中にこんな本が存在するのか。手はふるえ、心臓は高鳴った。この本をむさぼりながめて暮らしたものだ。私の一生を決める、「運命の本」だった。
この年、「福岡虫の会」に顔を出し、終生の師、江崎悌三先生に出会う。江崎先生の思い出はふきこぼれるほどあるが、とにかくその影響で、虫好きの少年が研究者の道を進むことになった。先生は、東大を卒業してヨーロッパに留学、帰国直後に九州大学教授に迎えられた少壮の昆虫学者だった。専門の半翅類(カメムシやアメンボ)以上にチョウを好んで、チョウの専門誌『ゼフィルス』(西風の精の意=ミドリシジミ類のこと)を発行、全国からの記録や論文を掲載した。戦前のチョウ研究の黄金時代だった。
虫好きな諸先輩とも知り合いになった。面白いもので、虫が好きというだけで職業や地位など関係なく、誰とでも話がはずむ。自然史では、各地からの記録や報告がいわば「測候所」の役目を果たし、生活史や分布状況などの把握には不可欠だ。最近は研究者と一般社会が離れているということが問題になっているが、チョウの研究はアマチュアなしでは存在しない。近年、ナガサキアゲハなどいくつかの種の北進現象が見られるが、それもアマチュアの観察報告でわかったことだ。
さて、虫を追い回して勉強をおろそかにした天罰テキメンで、福岡高校受験に失敗。幸い宮崎高等農林専門学校(宮崎大学農学部の前身)にパスしたので、南国の昆虫に会える期待もあって、入学した。さっそく、初めて見る虫たちに夢中になった。専攻した林学科より、農学科の動物学教室に足しげく出入りし、昆虫好きの助手や学生と虫談義に興じた。卒論には「宮崎地方のコガネ虫の生態」をまとめ、論文賞をもらった。

玉山(台湾)の頂上にて(1967)。この時は九州大学山岳部台湾遠征登山隊員として訪れた。

高良山(九州)へ昆虫採集に出かけた時のスナップ(1954)。
チョウ研究の道へ
宮崎高農を卒業した1938年は、人生の岐路だった。江崎先生の下で虫の研究をやりたかった。家業を切り回していた母は就職を希望した。その時、長兄が母を説得してくれて、虫への道が開けた。人生とは不思議、江崎先生と兄がいなかったら―。こうして1年の受験勉強。その間、九大の昆虫学教室に出入りさせてもらった。興味は採集だけでなく、虫の生活史、とくに食性(幼生期に何を食べるか)にあり、文献で食草を調べてみると、チョウの研究は盛んなのに、食草の記録は極めて貧弱と、わかった。後年(43年)発表した『チョウの生活史』が大きな反響を呼び、アマチュアの生態研究熱に火をつけたが、この浪人時代の調査が大いに役立ったのである。
翌年、九大に入学。江崎先生が、研究室に私専用の机を与えてくれ、破格の待遇にファイトがわいた。虫なら何でも好きだったが、その中でチョウを専攻テーマにしたのは、江崎先生の影響があった。「もうチョウでは大した発見はないよ」と先輩から忠告されたが、これは大間違い。浪人時代に引き続き、チョウの生態、生活史解明に熱中した。幼虫の採集、産卵の観察、食草の発見など・・・。クロセセリの幼虫を見つけ、食草を初めて明らかにしたのも、この頃。当時はこんな普通種の生活史さえわかっていなかったのである。
時は太平洋戦争前夜。学内でも話題は専ら戦争だったが、私はひたすら虫に打ち込んだ。野外研究とともに、大学の膨大な標本類を調べることも、楽しく勉強になった。忘れ難いのは、江崎先生が台湾で採集したチョウの中から、新種を見つけて専門誌に発表したことだ。その後の研究生活で20種のチョウの新種記載をしたが、初めてチョウの名付け親となったこの時の思い出は格別である。
九大を卒業したのが、1941年12月。チョウの研究を続ける決意を固めていたので、そのまま研究室に残り、翌年2月に副手、6月に助手となった。私の研究生活は、太平洋戦争と同時にスタートしたわけである。生活は苦しかったが、プロとしての第一歩を踏み出し「さあやるぞ」と張り切っており、江崎先生と共同で、台湾産のチョウの新種を次々に発表した。
戦局は傾き、1944年春、召集令状がきた。鹿児島県の志布志に配属され、研究は中断する。幸い理科系の研究者への配慮で、1年で除隊になり、研究室に戻った。しかし、時代は切迫し、専門誌は休・廃刊され、研究発表もままならない。45年6月には、空襲で博多の中心街は火の海となり、自宅も焼け、標本類や文献などを失った。終戦後も含めて3年間は、研究らしい研究もできなかった。

勲二等瑞鳳章受章を祝って。右隣は山本英穂博士。後列中央は、三枝豊平現九州大学教授

九州大学農学部にて(1956)。江崎悌三先生と。その右が白水博士。
ミドリシジミの分類
戦後の混乱が一段落して研究再開。
黒沢良彦さん(現国立科学博物館動物部長)が知人から託されたと持ち込んできたチョウ5頭の標本を見るなり興奮した。新種らしい。さっそく交尾器を調べた。チョウの種の判定には、腹部を解剖して交尾器を比較検討するのが有力な方法なのだ。外国文献も当たって新種と確認。クロミドリシジミと名付け、47年に発表した。それまでは日本国内でチョウの新種発見は無理と思われていたのである。
ミドリシジミ族は、シジミチョウ科、ミドリシジミ亜科に含まれ、当時、世界で28属108種が知られていた。そのうち日本に13属24種(現在の知見では25種)が生息しており、色彩、斑紋の美しさ、変化の多様性、なかんずく採集の困難さによって、日本の蝶類同好者に特別の関心をもたれている。1942年に、柴谷篤弘(当時京大)・伊藤修四郎(当時九大)両博士によって、日本産ミドリシジミの属の分類に先鞭がつけられていた。
私は、かねてから世界のミドリシジミの分類を研究したかったので、ぜひ虫の研究がしたいと私の研究室に飛び込んできた山本英穂君をパートナーに、51年これに着手した。彼は交尾器の解剖が得意だったので、解剖や形態の解析を担当してもらった。しかし、肝心のアジア大陸の標本が入手できず、大英博物館に手紙で依頼したところ、快く送ってくれるという一幕もあった。研究とは競争でもあるが協力が重要であり、さすが大人の国英国だ。以後、成虫の形態を細部にわたって入念にチェックした。前脚の形態、複眼の大小、雌雄の翅形、翅表における金属鱗の発達程度、雌雄斑紋の差、雌雄の外部生殖器の徴細な構造などの比較は、時間と根気と注意力を要する仕事で、5年の歳月をかけてやっと完成した。比較形態学的に詳細に調べることで、今までにない、属レベルの分類を再整理し、日本のメスアカミドリシジミを含むChrysozephyrus属など4種を新設すると共に、世界の属の系統発生的関係を示した。この仕事は、国内だけでなく、欧米からも注目され、日本のチョウ研究も世界に通用することを示したものと自負している。
分類学の最終目標は、系統を明らかにし、系統に由来する秩序を解明することであると考えているので、各属の形態上の特徴を総合して、それぞれの属がどの程度の進化レベルにあるかを示す進化系統樹を作成した。後に(63年)「ミドリシジミ類幼虫の食性進化について」という論文を発表し、さらに進化について考察を深めた。
白水博士は、比較形態学的に詳細に調べることで、今までにない、世界のミドリシジミの分類をした。図は、各属の形態上の特徴からそれぞれの属がどの程度の進化レベルにあるかを三段階で示している。







写真(6)~(12)=栗田貞多男
西部支那系を提唱
日本のチョウを分類するには、いつ、どこから来たか、地質時代まで遡って、その歴史を類推しなければならない。従来の生物地理学では、地球上を、旧北区・新北区・東洋区・エチオピア区・オーストラリア区・新熱帯区などと区分けし、ヨーロッパで作られたこの区割に、日本をどう当てはめるかが論争となっていた。ところが、日本のチョウを個々に見ていくと、実際の区割に当てはまらない種が少なくない。これらは中国西南部(西部支那)を中心として西はヒマラヤから東は日本に至る帯状分布をなしていることがわかったので、1947年、「系統的生物地理学」の重要性を唱え、「西部支那系要素」を提唱した。植物地理学でも、中国西南部の植物相と日本のそれとの類似性、関連性が指摘され、「日華区系」と名付けられるようになったが、これは、私の出した西部支那系にほぼ等しいものである。今でこそ、これが日本の生物相の基本的な構成要素であることは、さまざまな方面から証明されているが、昆虫の分野で指摘したのは私が初めてだった。
「系統的生物地理学」を主張したのは、現存の種を区分けするだけでなく、日本の蝶相の形成過程を考えることの重要性を指摘したかったからだ。温暖だった第三紀に北極地方にあった生物相は、第四紀の気温の低下・上昇の繰り返しの中で、数回にわたり南下・北上を繰り返した。この間に、ヨーロッパでは東西に連なるアルプス山脈、アジア中部では広大な乾燥地に移動を阻まれて消滅する種が多かったが、東アジアでは山脈が幸い南北に走っていたので多くが生き残れた。西部支那系の種は、その時の残存種とその子孫だと捉えている。
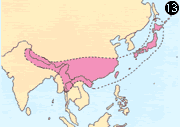
中国南西部を中心として西はヒマラヤ、東は日本に至る帯状に分布をする種を一括して、「西部支那系」とした。この図は西部支那系種の代表的分布を示すと考えられるNeope(キマダラヒカゲ属)の分布概念図。
動物の分布を区系的に理解し、地図上に線引きしていた。
「西部支那系」は植物地理学上でいわれる「日華区系」にほぼ等しいことがわかった。チョウの進化は食草と密接に結びついていると考えた博士は、たとえば、温帯性ミドリシジミ類の大部分は、第三紀周北極要素と呼ばれる植物相に伴って日本に南下してきたものの日本の温帯林における生き残りだと考えている。
資料収集狂
58年出版の『日本産蝶類分布表』は大変に思い出深い。数年かけて、迷チョウも含めて、217種のチョウの都道府県別の記録の一覧表を作成。裏付けとなる資料、出典などを巻末に明示したものだ。
報告や記録の収集・整理がいかに大切か、学生時代からその重要性に気づき、手に入るものは全部集めていたので、数万点にもなる。私の資料収集狂ぶりが知れわたり、今では毎年、昆虫の記事を満載した印刷物が数百冊も郵送されてくる。丹念に目を通し、記録をとり、整理するのが日課だ。手間はかかるし手柄にもならない。半ば義務感で作業を続けている。遠くから、資料を見に尋ねてくる研究者も少なくないのである。
小さい頃からの台湾への憧れにもかかわらず、訪れる機会もないままに1960年、研究室の優秀な後継者である三枝豊平君らと共に、ようやく『原色台湾蝶類大図鑑』の刊行にこぎつけた。文献、資料、標本の詳細な検討の成果である。すべてに解剖図、分布図をつけており、画期的なものと評価された。台湾はチョウの宝庫で、九州くらいの面積だが、チョウの種は3倍の360種もいる。翌年、台湾のチョウをテーマに学位を取得し、初めての訪台にも恵まれた。長年頭の中にあった台湾のチョウの生きた姿を見た新鮮な感動は忘れられない。新種も見つかった。

白水博士の著した図鑑の数々。
チョウ研究家のバイブルとなった。
『日本産蝶類分布表』(1958)
『原色昆虫大図鑑――蝶蛾編』(1959)
『原色図鑑日本の蝶』(1965)
『原色台湾蝶類大図鑑』(1960)
『原色日本蝶類幼虫大図鑑1』(1960)
『原色日本蝶類幼虫大図鑑2』(1962)など。
種は存在しない
本格的にチョウの研究を始めて、長い歳月が流れた。しかし、まだやりたいことは山ほどある。むしろ新たな疑問が後から後から追いかけてくる。
私は、「種」とは何だろう、と考え続けてきた。一般的に、種は形態で判別される。分類学の基本だが、同じ種でも雌雄や季節型で外見が極端に違う例は無数にある。一方、種は生殖集団だとする遺伝学や生態学の見地からの定義がある。子孫を残しうる集団なら同種、残せないなら別種とする。きわめて的を射た定義であろう。だが、厄介なのは、地理的に隔離された近似グループの関係である。それが別種なのか、同一種の別亜種なのかを形態的に判定することは難しい。
結局、種とは、絶対的な区別ではないのではないか。種は現実に存在するが、すべての種のルーツは元をたどれば同じはずだから、本質的なものではない。長い地質時代を経て、生物はさまざまな方向に進化し、現在私たちが目にすることのできる種が形づくられてきた。なかには進化の途上で絶滅した集団もあろうし、現生の種につながる過去の集団は当然絶滅している。その欠落がなければ、あらゆる種が連続した状態が想定できる。それゆえ、種はあくまで相対的な存在であるといえる。長年の研究生活で到達した一つの結論だ。
現在、日本のチョウ研究は世界最高水準に達し、ファンは数万人といわれる。優れた研究者も少なくないが、大半は余技で研究している。その中で私は公費でチョウの研究をさせてもらった。じつにありがたいことだ。
少年時代の一冊の本、そして人との出会いを、運命と思わざるを得ない。多数の虫屋、虫友との交わりも含めて幸せな生活ができた。どんなに新しいタイプの研究が生まれようとも、自然を見つめる科学が基礎にあるのだということを、次の世代に伝えていきたい。見果てぬ夢をなお追いつつ、心楽しい日々なのである。
図は白水博士が60年代に発表に用いてた掛図の写真(図中の番号はその時のもの)。当時学会発表などでは誰もが掛図を使っていた。
斑紋パターンの相同性を探っていた白水博士は、1957年、ウラナミアカシジミの異常型を見て、現生種の斑紋パターンが1筋おきに消えていることに気づいた。