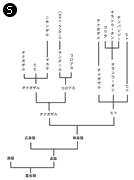生物の研究を志す――京都大学へ
満州から引き揚げて住み着いた東京の阿佐ヶ谷は、周辺に田園風景が広がっており、メダカやドジョウ、トンボやセミ採りは当たり前のことでした。これといった特徴のない、普通の子供でしたが、意識せずとも植物や動物は、身近で親しい存在でした。学校の教師になれば生物を観察しながら一生を送れると思って、東京教育大学に入りました。卒業研究として選んだのが浦安海岸に棲息していたスナガニです。遠浅の砂浜に掘った穴から出てきてさまざまな社会関係を繰り広げる。それを平面上で見られるのが研究材料としての魅力でしたね。
もう少し研究を続けたいと思うようになりました。5 人の息子を育てた母親も、父親代わりに働いてくれていた兄も、末っ子の卒業と就職を楽しみにしていたのですが、一緒に研究していた先輩が京都大学の大学院に進んだのに刺激されて、私も受けてみることにしました。動物学科に行っても就職は望み薄の時代でしたが、合格して柳行李(やなぎごうり)ひとつを研究室に送り、アルバイトで貯めたわずかなお金を持って夜行列車に乗りました。ちょうど下宿させていた京大生が出て部屋が空いてるという家があって、タダも同然で置いてもらえたのです。その学生が、すでにカラコルムなどの探検で活躍していた本多勝一さん(元朝日新聞記者)でした。多くの人がギリギリの生活をしながら、未知のものを目指す明るさをもっていた。そういう時代だったのですね。
生態学は、葉っぱの重さを測ったりしてエネルギーに換算し、物質代謝や食物連鎖を見る研究が流行でしたが、私は、生きものの社会を見たいと思って、サルの研究グループに入りました。1958年、今西錦司先生や伊谷純一郎さんのサルの社会構造の研究が、ユニークな方法論で一気に世に知られた頃でした。

大学時代、植物採集旅行へしばしば行った。青木湖で。

生態グループに所属し、学園祭で食物連鎖の展示をした(中央)。

59 年、京大時代。ロックフェラー財団のアンダーソン博士を嵐山に案内した。

73 年。ハヌマン・ラングールをヒマラヤの高地で調査。森がある限りサルはいる。
京都大学サル学の伝統の中で
指導教官の宮地伝三郎先生に下宿に近い嵐山のサルを見てこいと言われ、観察を始めました。サルは初めてです。これは面白いと思って観察の結果を先輩に報告すると、そんなのオレがとっくに見ていると片っ端から言われ、意気消沈する毎日でした。
2年目には、高崎山に行くように言われました。今西先生や伊谷さんが、九州の幸島や高崎山で、餌付けによって至近距離からの詳細な観察を可能にし、個体識別をしたうえで長期間継続調査するという独特の方法を確立、ニホンザルに社会構造があることを報告して、海外でも高い評価を得始めていました。ボスザルを筆頭にした個体間の順位の存在、サルに文化があるかもしれないという疑問を投げかけた「芋洗い」の発見など、サル学の新しい時代をつくっていたのです。
もっとも、それは伊谷さんの『高崎山のサル』にたいてい書かれていましたから、同じものを見ても新しい発見があるとは思えない。餌付け場所以外の自然状態ではサルがどういう生活をしているかを見直してみようと思い、山の中のサルを追って歩きました。600mの高低差を一日に2 往復するようながむしゃらなフィールドワークで、こんなことをしていて研究になるのだろうかと思うこともたびたびでしたが、サルを追いかけているうちに、リーダーがいて順位のある統制のとれた集団が分裂していく経過を観察できたのです。
「高崎山の群れの分裂」として発表、これが私の最初の論文で、集団の分裂過程を追跡した世界で最初の事例になりました。とはいえ発表当時は、数が増えたから分裂しただけとしか見られず、あまり評価されませんでした。でも、私にとっては、社会構造を理解するには壊れる時を見るのが安定時の追跡と同じくらい大事なポイントだと気づくことができたわけで、大きな収穫でした。その後インドでは、積極的に社会変動の起きそうな場面を探して回り、時には実験的に社会変動を起こしてしまうという方法の下敷きになったのです。個体識別をして長期にわたって観察するのが、日本のサル学の独特な方法だったのですが、それに一つ新しい視点を付け加えたわけです。
霊長類は哺乳綱の中の肉食類や偶蹄類、齧歯類などと並ぶ目(もく)で、真猿と原猿に分かれる。原猿は霊長類の祖先種に近いといわれ、キツネザルなど、いわゆるサルらしくないサルである。
真猿は、中南米に生息する広鼻猿類(オマキザル、ホエザルなど)とアジア・アフリカに分布する狭鼻猿類に分かれ、狭鼻猿類にはオナガザルやニホンザル、ハヌマン・ラングールなどを含むオナガザル上科とヒト上科があり、ヒト上科にはオランウータン、チンパンジー、ゴリラ、テナガザルを含む類人猿とヒトが入る。最近では、チンパンジーをヒト科に入れることもある。
インドでハヌマン・ラングールを調査する
当時南インドで流行していたウイルスによる伝染病、キャサヌール病をハヌマン・ラングールという狭鼻猿類(オナガザルの仲間)につくダニが媒介していることがわかり、宮地先生のところにロックフェラー財団から調査依頼がきました。サルの生態研究といえば日本と思われていたのです。その頃今西先生たちは、ニホンザルの次に類人猿を調査目標にしていましたが、私は、一足飛びにそこまでいかずに、まずニホンザルと同じオナガザル上科のもう一つの枝から研究対象を選びたいと思っていたので、補欠でもインドでの調査に参加できたのは幸運でした。後にも先にも、これほどお金の心配をせずにすんだ調査はありませんでしたし。
61年4月、南インドのダルワールに住居を定め、先行隊として最初の調査をほとんど一人でやりました。高崎山の経験から、まず基本を押さえて、だんだん焦点をしぼっていくことにしたいと思い、毎日森で見つけたサルを逐一記録し、どこにどういうサルのグループがいるかを30kmにわたって把握しました。そのうえで、たくさん群れがいそうなところに集中しようと思ったのです。
3カ月して夏休みになり、川村俊蔵さん(当時大阪市立大学)がやって来た時は集中調査地も決め、これから思いきり精密調査を始めようとしていたところだったので、「まだ個体識別もできていないのか」と叱られたのはくやしかったです。日本のサル研究は、とにかく餌付けによって個体識別をして個体間の関係を見ていくものだという定型ができてしまっていたのですね。そのことによってサル学が急速に発展したということで自信をもっていたのです。私は、それはちょっと狭い、集団内での個体間の関係の面白さに惹かれてしまって、動物の生態という視点が欠けていると思ったので、いきなり少数群のサルの個体識別をするのではなく、基礎的観察から少しずつ進めていくべきだと主張しました。でも受け入れられませんでした。
私が見つけた一番大きい、いいグループを川村さんが選び、私は、何も起こりそうもない小さい群れを担当しました。一方で私は、社会変動が起こりそうな群れを探し回ったのです。幸い広域調査区域の途中に大きな群れを見つけました。2つのグループ間を行ったり来たりの調査はたいへんで、若かったからこそできたのだと思います。結果的には、典型的なグループとかなり変わったグループとを同時に見ることができたことは幸運で、視野を広げるチャンスになりました。もっとも、幸運だったのか不運だったのかは、わずかな機会をどうやってどれだけ引き寄せるかの違いにすぎないのでしょうが。
ダルワールではほとんどのグループが単雄群、つまり、一匹のオスが複数のメスと子供を率いています。オスの子供が大きくなったら複雄群になるはずなのに、大部分が単雄群であるのはなぜか。たくさんのオスはどこに行ってしまうのか。何かが起きるはずだ。複雄群にそろそろなりそうな群れは怪しいぞ。そこに眼をつけたのです。




子殺しの発見
それは、私がドンタロウと名付けたオスの率いる、9 頭のオトナメス(5頭は子持ち)、6 頭の若オス(1 ~4 歳)、3 頭の若メス、5 頭の赤ん坊からなるグループでした。
62年5月31日午後2 時、ドンカラ群と名付けたこのグループをいつものように6 km 歩いて見に行くと、ドンタロウが足から血を流しながら木の上で疲れ切った様子で威嚇の声をあげていたのです。その下では、7頭の離れオスグループがメスたちに近づこうとしており、数頭のメスはすでに侵入者の側につき、なかにはプレゼンティング(発情したメスがオスに交尾を誘いかける行為)をしているものさえいました。それから数日間、オスたちの闘いが続き、結局7頭の侵入者のうちの1 頭(エルノスケ)が勝利を収め、ドンタロウは追い出されたのです。若オスも父親と一緒に出ていき、他の離れオスも追い払われました。エルノスケを核とする典型的な単雄群になってしまったのです。
7日目のことです。赤ん坊が1 匹いなくなり、腹のあたりがざっくりと切れている赤ん坊もいる。そして、2 ヵ月ほどの間に5 頭の赤ん坊がすべて消え、赤ん坊を失った母親はみな発情して6カ月後に子供を産んだのです。
初めは頭の中が混乱しました。しかし、オスが赤ん坊を抱いたメスを攻撃し、赤ん坊が全滅し、やがてメスが発情してオスと交尾し、子供を産むという一連の流れを見ているうちに、これは因果関係があると思わざるを得なくなったのです。何か大変なことを観察しつつある。次はどうなるんだろう、単雄群の社会維持の秘密が今明らかになりつつあるのだと、必死で観察を続けました。
他の群れでも同じことが数例起こり、観察が特殊な事件ではないことをほぼ確信したのですが、ここで前から考えていた実験をやってみました。特定のサルの異常な性格によるものなのか、ハヌマン・ラングールの社会で一般に起きることなのかを証明するためです。担当していたもう一つのグループで、オトナオスを取り除いたところ、9日目に隣の群れのオトナオスが侵入し、2 日間で4 頭の赤ん坊が全部殺され、2 ヵ月の間にすべてのオトナメスが発情して侵入オスと交尾しました。
なぜそんなことをするのか。オスはメスをわが物にしようとして群れを乗っ取ったのに、赤ん坊をもっているためメスは発情しない。それでは目的を達成できないので赤ん坊を殺す。そういう推論を立てました。
64年英語の論文を発表し、モントリオールで開かれたアメリカ科学アカデミーの霊長類シンポジウムで報告したのですが、スギヤマの報告は観察が断片的だとか、異常行動にすぎないなどという反響しかない。「神の使い」のハヌマン・ラングールは平和的な生きものだというのが当時の定説だったのです。これまで誰もやっていない突出した研究をしたと思っていたのに、なんだ、たいしたことなかったのかと落ち込みましたね。結局10年後に、アメリカのフルディさんが追試に成功し、その発表でやっと一般的な議論になり、ようやく認められるようになった。ちょっと早すぎたのかな。それにまだまだ日本人の研究が受け入れられる欧米科学界ではなかったのかもしれません。
子殺しは、その後、チンパンジーやゴリラ、ライオンなどでも次々報告され、いろいろな解釈が出てきました。とくにオスの繁殖戦略、つまり、自分の遺伝子をいかにして残すかという観点でこの現象を見る考え方が流行にさえなりました。当時の私は、あぶれたオスがメスを手に入れようとするという説明で辻褄が合うし、サルの気持ちを一生懸命考えていたんですね。冷たく距離を置いて考える側面が足りなかった、別の言い方をすると科学としての深みが足りなかったとも言えるけれど、でも遺伝子レベルだけで見るのがよいとは思いません。自然現象には近因も遠因もあり、両者を繋ぐ橋があって、初めて進化の中で定着するはずですから。最初の説明が、私は今でも間違っていたとは思っていません。





霊仙山での研究 ―― 順位はなかった
日本のサル学を築いた先輩たちの主張の大きな柱は、個体間には相互に認知した順位があるというものでした。サルに触れ始め頃の私は、サルにも人間のような高度にオーガナイズされた社会があるというのが新鮮で輝いて見えたのですが、実際にサルに接していると、順位がきちんと決まっていて人間社会と相同だという説は、胡散臭いと思うようになったのです。
70年、愛知県犬山の霊長類研究所に移った前後にわたって、京都と犬山の中間にある霊仙山で、独自の調査を始めたのです。サル学は科学ではないと言われるのは明確なデータがないからなので、何とか定量をする。餌付けという人工的状況下だけではなく、自然環境の中でも調査する。この2つが私の考えた方法論です。
実際、餌付けをやめてみると、絶対と思われていた個体間の位にいろいろと違いが出てきたので、いったい順位とは何なのかと考え、それを量的データで出してみようと思いました。子孫をどれだけ残すかが生物の基本ですから、繁殖成功率を測った。すると、餌付けをした時は順位の高い家系ほど生まれた子供の生存率が高く、早く子供を産み始め、出産間隔が短い。たくさん子孫ができる。順位の低い家系との間にどんどん差がつく。順位が高いことが確かに子孫残しに有利に働いていました。ところが、餌付けをやめると、驚いたことに、順位の上下はほとんど繁殖成功率に影響ないことがわかったのです。生物のもっとも基本的な部分に、順位の高低などほとんど関係しないということです。
餌付け環境では、限られた場所で他を排除して餌を独占できるので、それが子孫残し率に響く。そこで高い順位につこうと各自に上昇志向が生まれる。極言すれば、順位や個体間の優劣関係は、餌付けによって人間が拡大してきたものだとも言えるのです。
今西先生や伊谷さんたちは、個体間の関係や、どういう行動をするか、何を考えているかなど社会的、行動的、心理的側面に関心が強く、どれだけ子供を作るかという生物学的側面にはほとんど眼を向けませんでした。一匹一匹の顔を覚え、まるで人間社会を研究するように厳密な個体間の関係を明らかにしたのですが、私は、一度そこから離れる必要があると思って始めた結果、先にお話ししたようなことがわかったのです。
社会構造を明らかにするには、個体間の関係だけでなく、生活の基盤を知る必要があると考え、集団の生態へと軸を移したのです。つまり、環境に適応しながらの生活に眼を向けたわけで、単純に言えば、どれだけ子供を産んでどれだけ育て上げ、何をどれだけ食べるかという基本的な事柄を調べたのです。誰と誰が仲がいいかだけではなく、環境にどう合せて行動しているかを中心にした。個体群生態学、人間でいうと人口学です。
しかし、私の報告に対して、いろいろな形でプレッシャーがかかりました。ニホンザルの研究の伝統を根底から覆す話でしたからね。日本の霊長類学が、ユニークで突出していたことは事実ですが、それと裏腹に、単一起源で、号令一下同じ方向に一斉に走り出す弊害もあったのです。草創期の人たちを高く評価しますが、学問は、次の世代がそれを乗り越えていかなくてはだめでしょう。
また乗り越えさせる先輩でなければ発展は一代限りで終わりです。霊長類研究所には、フィールド系だけでなく、形態学者、遺伝子を扱う分子生物学者、脳の機能の研究者や心理学者など、いろいろな分野の研究者がいて、切磋琢磨しているうちに京都とは違うものができたと思います。私が所長の時には、できるだけ新しい分野や考え方を入れていくようにしました。DNAの分析で父子判定もできるようになり、順位の1 番のオスが必ずしもたくさんの子供を残すわけではないということが明らかになった時には、やっぱり、と思いましたよ。

ボッソウ村では、25 年にわたって継続調査を行なっている。

研究所の前で、現地の所員と。

村人たちとの付き合いも長い。
アフリカチンパンジーの調査 ―― 例外から見る
1976年、野生チンパンジーの研究の発祥地ギニアで、調査地になりそうなボッソウという村を見つけました。当時は東アフリカの200kmほどの範囲内にジェーン・グドール博士のフィールドともう一つのチンパンジーの調査地がありましたが、チンパンジーの分布は5000km離れたところまで広がっている。グドール博士らの場所と反対の端にあるのがボッソウです。
20頭ほどの小さいグループでしたが、道具使用行動がどの調査地よりも多い。また、チンパンジーは他のサル類と違ってオスが生まれた集団に残り、メスが外へ出ていくといわれているのですが、ボッソウではオスもメスも出ていくらしい。単独性の哺乳類に一般的に見られるタイプを示しているのです。
これは、それまでの調査結果とは違う。違うものが出てきた時、たいていの人は「例外」として捨てるけれど、事実それは自然の中にあるのだから、例外を含めた説明が必要だし、それの説明ができて初めて全体像がつかめると思うのです。例外の発見こそチャンスですよ。ボッソウは、半ば孤立しているので、オスが協力して縄張りを守る必要がない。メスの独占には他のオスはいないほうがいいわけだから、結局単雄群になるのでしょう。ここから逆に、他の地域でオスがまとまって群れに残るのは、隣の群れから縄張りとメスを守るためにオス同士で連帯する必要があるからだという説明が可能になるのです。
高崎山の群れ分裂に始まって、私はずっと例外的なことばかり探してきたような気がするな。そしてそれを含めて全体像を描き出そうとするから時間がかかる。それに例外はなかなか人々に受け入れてもらえない。日暮れて道遠しです。25年続けてまだデータが足りないなんて言ってるんですから、実験室研究者が聞いたら、なんと気の長い話よと思うでしょうね。自分でもえらいところへ踏み込んでしまったと思ってますよ。
生態学は自然そのものが対象だから変数が無限にあり、そのなかからどれを取り出すかの見極めは簡単じゃない。それをきちんとやってこなかったから、生態学は長い間、科学として認められなかった。そこを何とか科学にしたいとずっと努力してきました。最近では、データを出し合って比較検討しようという雰囲気が国際的にも出てきました。そういう比較と総合から全体像をつかんでいきたいと思っています。
長い間霊長類学を研究してきて、霊長類そのものを対象にしている時には拙速に人間の行動や社会と結び付けないように気をつけてきたけれど、霊長類学は、やはり人とは何かを理解するためにこそあるべきだし、そういう形で霊長類学を位置づけていくべきだと今は思っています。
今西先生や伊谷さんが、もっぱらサルの中の人間性を突きとめようとして、サルのもっとも人間らしい部分だけを取り上げ、環境など関係ないと言ってこられたことに反発し、できるだけ数量的データを基盤にサルの生物性を把握しようとしてきたのですが、ふと気づいたら、やはり人間に眼が向いていた。霊長類学の成果を基盤にそれを理解したいと考えるようになりましたね。人間の行動には生物としてのバックグラウンドがあるわけだから、霊長類以外の生物にも目を向け、環境への適応という観点も大事にし続けていきたいと思います。これが、今、人文学部に籍をおいて考えていることです。

京都大学霊長類研究所にて。右はチンパンジーのアイ。