年度別活動報告
年度別活動報告書:2010年度
分子系統から生物進化を探る 3-1.イチジク属植物とイチジクコバチとの共生関係と共進化
蘇 智慧(主任研究員) 岡本朋子(奨励研究員)
佐々木綾子(研究補助員) 石渡啓介、宮澤秀幸、上田千晶、長久保麻子、坂内和洋(大阪大学大学院生)
はじめに
様々な生物種から構成される地球生態系のなかでの生物同士或いは生物と環境との相互作用は、生物の多様性を生み出す大きな原動力と考えられる。昆虫と被子植物はそれぞれ陸上で最も多様化した生物群で、その多様化は植物と昆虫とが互いに相互適応的関係を築くことによって促されてきた。その最たる例が1種対1種の密接な送粉共生関係を築くイチジク属植物 (クワ科) とイチジクコバチ科昆虫であり、双方が800種以上の種数を誇っている。我々は現在イチジク属とイチジクコバチの共生関係の構築、維持、崩壊のメカニズム、または種分化の様式などについて研究を行っている。
イチジク属植物は、東南アジア、アフリカ、中南米など熱帯を中心に分布している。日本はイチジク属の分布域の北限にあたり、南西諸島を中心に16種が生息している。イチジク属植物は花嚢とよばれる袋状の閉じた花序をつけ、その内側に多数の花を咲かせる。送粉者であるイチジクコバチは、花嚢にはいった場合、授粉と同時に花に産卵し、ふ化した幼虫は子房を食べて成長する。やがて次世代のコバチの成虫が花嚢内で羽化し、花粉を持って他の花嚢へと移動することで受粉が成立する。このようにイチジクとイチジクコバチの2者は、繁殖を互いに強く依存し合った関係といえる。
イチジク属植物と送粉コバチとの共生関係は、「1種対1種」という種特異性が極めて高いものと言われている。この「1種対1種」関係を維持しながら種分化が起きるとしたら、同調した種分化や系統分化が起こることが予想される。これまで、分子系統学的解析を用いてこの仮説を検証する研究が行われてきた。その結果、イチジク属の節(section)レベルの系統関係とコバチ類の属のそれとがおおまかに一致し、仮説が支持されるものの、種間、種内レベルでは系統関係の矛盾のほかに、送粉コバチの隠蔽種や1種のイチジク属植物に複数種の送粉コバチが共生するなど、不明瞭な点が残っている1, 2)。これまでの我々の研究においても、日本産のイチジク属植物とイチジクコバチでは、それらの分子系統樹の樹形が一致し、「1種対1種」の関係がほぼ厳密に維持されている3)ことが示唆された一方で、メキシコ産の材料では、近縁種間で「1種対1種」の関係と同調的種分化の乱れや宿主転換がある程度おきていることを示している2)。今年度はさらに高次分類群(亜属または節)間の系統関係を複数の分子マーカーを用いて調べたところ、分子マーカーによって明らかに異なる系統関係が示され、雑種形成がイチジク属植物の系統分岐のかなり初期に起きていたことが示唆された。また、日本の小笠原諸島固有種も雑種起源であることが示されたことから、雑種形成がイチジク属植物の種分化をもたらす大きな要因の1つであると考えられる。
また、イチジク属植物が特定のパートナーを花へ呼び寄せるために用いるシグナルとして、主に嗅覚情報である花の匂いが注目されてきた。花の匂いとは、花から放出された分子量300以下の揮発性に富んだ化学物質(の集まり)を指す。イチジクの花嚢の外見は緑色で非常に目立ちにくいため、視覚情報よりも嗅覚情報が有効であると考えられている。本年度は、沖縄県石垣島に生育するイチジク属植物を対象に花の匂いの採集と分析を行い、種特異性維持の鍵になる物質の探索を試みた。
さらに、種特異性維持のメカニズムの解明を目指すと同時に、イチジクとイチジクコバチの相利共生関係維持のメカニズムにも注目して研究を行っている。イチジクとイチジクコバチの共生関係は、広く相利的であると認識されているものの、個体群の密度や個体ごとの形質、またそれらをとりまく環境などの様々な要因によって、時に寄生的にふるまう可能性が考えられる。特に、広域に分布する生物同士の相互作用では、双方の関係性が全く均一である可能性は低く、様々な関係が入り混じり、共生関係を維持している。このような生物間相互作用の実態と動態を把握することは、相利共生関係の維持や崩壊を理解に極めて重要であると考えられているが4)、これまでの研究の多くは、共生者2種の関わり合いのみに注目しており、それらに関わる他の生物種が共生系に与える影響などは十分に検証されていない。そこで、本年度はイヌビワとイヌビワコバチ(Blastophaga nipponica)の共生系に注目し、これら2者の関係の実態の把握を目指し、生態学的研究を行った。
結果と考察
1)沖縄県石垣島に生育する5種のイチジク属植物の花の匂いの組成
本研究では、オオバイヌビワ (Ficus septica) とそれに比較的近縁で同所的に生育するアカメイヌビワ(F. bengutensis)とギランイヌビワ(F. variegata)、さらに系統的に離れてはいるものの同所的に生育するハマイヌビワ(F. virgata) とガジュマル(F. microcarpa)を対象に花の匂いを採集(ヘッドスペース法)し、ガスクロマトグラフ質量分析計で分析し、仮同定を行った。その結果、合計28の物質が検出され、その多くがテルペノイドであった (現在本同定中につき、物質名は示していない)。同所的に生育し、しばしば同時期に花を咲かせる5種の花の匂いは、均一ではなく、種ごとにユニークな組成を示した。また、それぞれの種に共通する物質が存在する一方、種に特異的な物質が少なくとも1つ以上存在することが明らかになった。アカメイヌビワとオオバイヌビワは同じ節(section)に属し、比較的近縁な2種である。これら2種が共通して持つ5つの物質はこれらの共通祖先でその生合成能力をすでに獲得していたと考えられる。しかし、その他の物質に関しては、それぞれが分岐した後に生合成能力を獲得した可能性が高い。このような物質は種特異的なパートナーである送粉コバチとの関わりを通じて進化してきた可能性が高く、今後はそれらの物質に対する送粉コバチの反応を調べることで、種特異性維持の鍵になる化学物質が明らかになることが期待される。また、サンプリングの種数を増やすことでこれまで当研究室で構築した分子系統樹と合わせた議論が可能になり、ひいてはイチジクとイチジクコバチの種分化に関わる化学物質の発見とその進化パターンの解明につながると期待される。
2)イヌビワとイヌビワコバチ送粉共生系の生態学的研究
2-1. イヌビワのイヌビワコバチ受け入れ期間の延長とその仕組み
雌雄異株であるイヌビワは、花粉の生産と送粉コバチの保育に特化した雄株と、花粉を受け入れて種子の生産だけを行う雌株が存在する。これまでイチジクの花嚢はイチジクコバチが利用しはじめると受け入れ態勢を解除し、逆にコバチがはいらなければ2週間程度は延長するということが知られていたが、それがどのようにして成立しているのかは明らかになっていなかった。そこで、本研究では2010年5月に和歌山県にて採集したイヌビワを対象に、雄花嚢の成長度と花嚢内のコバチの有無と花の数をカウントし、イヌビワの花嚢のコバチ受け入れ期間の延長が行われているか、また、それがどのようにして成立しているのかを調べた。その結果、イヌビワではイヌビワコバチが入らない花嚢ほど花の数が多く、同じ大きさの花嚢でも、コバチが入った花嚢では花の数が有意に少なかった。この結果は、イヌビワはコバチがはいらない限り、花嚢のサイズを大きくしながら中の花の数を増やすことで、コバチ受け入れ期間の延長を行っていることを示唆している。ラン科植物などでは、花粉の持ち去りや受け取りが花の寿命を決定づける要因となっていることが知られているが、イヌビワの場合は、花嚢内に咲く多数の花が個々で寿命を延長させているのではなく、新たな花を生産することで花嚢自体の寿命を延長させるという新たなパターンが検出された。また、予備的な調査から、イチジク属植物では種ごとに、花嚢の寿命パターンに違いが見られた。
2-2. イヌビワコバチを捕食するクロツヤバエ (Silba sp.) の発見と、それがイヌビワの繁殖に与える影響
2010年9月の和歌山県紀伊大島のイヌビワ個体群において、クロツヤバエ科の1種 (未記載, Silba sp.) がコバチを捕食していることを発見した。イヌビワの花粉を運搬し、その繁殖を支えるイヌビワコバチの被食は、コバチ自身の生存だけでなく、イヌビワの花粉分散に大きな影響を与えると予測され、イヌビワ-イヌビワコバチ共生系に多大な負の影響を与えると考えられる。本研究ではクロツヤバエがイヌビワの繁殖に与える影響を調べるため、1つの花嚢あたりのイヌビワコバチとクロツヤバエ幼虫の個体数をカウントし、クロツヤバエとイヌビワコバチの関係を調べた。その結果、クロツヤバエが見られた花嚢では、コバチの羽化率が低くなる傾向がみられた。また、個体群内において、クロツヤバエ発生の時期は、コバチを放出する雄株個体が極めて少ない時期と重なっており、さらにその個体におけるクロツヤバエの寄生率は極めて高かった。これらのことから、和歌山県の個体群では、クロツヤバエによるコバチの捕食はイヌビワの花粉の分散を妨げ、イヌビワの繁殖成功に著しい負の影響を及ぼす可能性が考えられる。また、これらクロツヤバエは和歌山県と沖縄本島からのみ見つかり、沖縄県石垣島のイヌビワ個体群からは見つかっていない。これは、イヌビワとイヌビワコバチの共生系に関わる要因が、本州・沖縄本島と石垣島で著しく異なり、共生系が均一でないことを示唆している。今後のさらなる調査により、それぞれの共生系の維持戦略の解明が期待される。
3)イチジク属植物の種分化における雑種形成
3-1. イチジク属植物の高次分類群の分岐初期における雑種形成
イチジク属植物の高次分類群(亜属或いは節「Section, 亜属の下位の分類単位」)間の系統関係を解明するために、葉緑体DNA、核ITS領域、核Aco1遺伝子と核G3pdh遺伝子を用いて系統解析を行った。日本、中国、メキシコを含む5つの亜属 (Ficus, Synoecia, Cycidium, Urostigma, Sycomorus) に属する複数種のサンプルを解析に用いた。特に、Urostigma 亜属は複数の節に分類されており、今回の解析には3節(Urostigma, Conosycea, Americana)のサンプルが含まれている。遺伝子ごとに系統解析を行った結果、明らかに異なる2つの樹形が得られた。
3-2. 小笠原諸島固有種の雑種起源
典型的な海洋島である小笠原諸島には、大陸から分布を拡大した生物が島内で独自に進化を遂げた固有種が多くみられ、イチジク属も3種の固有種(トキワイヌビワ、オオトキワイヌビワ、オオヤマイチジク)が生息している。これらは、イヌビワ Ficus erecta とそのコバチが移入して、単一の祖先が島内で種分化したものと考えられていた。しかし、核と葉緑体DNAの塩基配列を用い、日本、中国と台湾に分布する近縁種を含めた分子系統解析を行ったところ、葉緑体DNAの塩基配列による系統解析では、固有種がイヌビワの八重山集団に最も近いことが示されたが、核遺伝子(G3pdhとAco1)、ITSによる植物の系統解析では、イヌビワと固有種は姉妹群を形成しない結果となった。また、ミトコンドリアCytB遺伝子と28SrRNA遺伝子によるコバチの系統解析の結果からも、固有種のコバチはイヌビワコバチに由来しないことが示唆された(図5)。これらの結果から小笠原固有種はイヌビワを母系とする雑種起源であることが考えられる。そのシナリオは下記のように考える。まず小笠原に祖先種のイチジク属植物とそのコバチが分布していた。イヌビワの種子が鳥によって八重山から小笠原に運ばれ、そこでイヌビワの木が生える。そして、小笠原祖先種のコバチがそのイヌビワに送粉し、交雑個体が作られ、その後、コバチが交雑個体にも繰り返し送粉して戻し交雑が進む。次第に交雑個体が分布を広げ、小笠原祖先種は絶滅に追われる。現在の3種の種分化も恐らくこの過程で起きたと思われる。本研究の結果は、イチジク属植物とコバチの種分化は地理的要因だけでなく、雑種形成やそれに伴う生物間相互作用の適応進化等の生態的要因が大きな役割を果たしていることを示している。
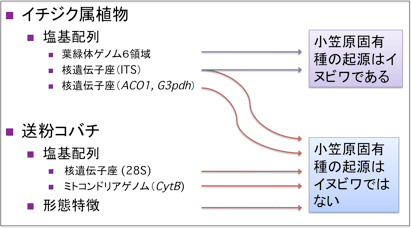
図5 複数の分子マーカーから見た小笠原固有のイチジク属植物とそのコバチの起源
おわりに
イチジク属とイチジクコバチとの共進化と共種分化のメカニズムを解明するためには、これまで分子系統解析と集団遺伝学的解析の手法を用いて行ってきた。両者の間に、同調的な種分化が示される一方、一致しない結果も見られた。これはコバチによる異種間の送粉による雑種形成がもたらした結果であると考えられる。また、この雑種形成はイチジク属植物とコバチの種分化・多様化にも大きな影響を与えていると本研究の結果から言える。今年度は、さらに植物の花の匂い物質の成分分析や、花の成長とコバチ以外の共生者に関する生態的な調査も行い、イチジク属植物共生系の維持と多様性のメカニズムの解明を目指している。花の匂い物質の生合成パターンの進化と種分化がどう関わっているのかを解明していきたい。また、送粉コバチ以外の共生者が共生系の維持にどう影響しているのかについても、今後生態的な視点から研究を進めていきたい。
